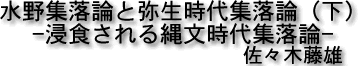
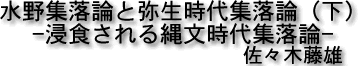
今回紹介する佐々木藤雄さんの論文は、1996年3月に「異貌」第15号(共同体研究会)に掲載されたもので、まさに「力作」です。既に3年半の時間を経過していますが、当時既に下記のようなするどい「警告」を発していることに驚かされます。
「全国各地で巨大遺跡・遺構”の新発見が相次ぐ今日、縄文時代集落論は、少なくとも第三者の眼には、かつてない高揚と自己変革の波の中にあるかのようにみえる。
しかし、戦後半世紀にわたって営々と積み重ねられてきた集落研究のこれまでの成果をほとんど顧みることもなく、しかも、検出された膨大な遺構群の時空的な分布や内容に対する十分な検討もなされないまま、二〇m、五〇〇人、一五〇〇年、神官層、縄文都市、縄文文明といったS・Fもどきの野放図な言葉となし崩し的な結論の一人歩きを許容しているたとえば三内丸山遺跡をめぐる“議論”の現状は、率直にいってきわめて無責任であり、そこには地に足の付いた、縄文時代集落論の将来の方向を真摯にみすえた新しい問題提起や提言の類はまったくといってよいほど認められない。
むしろ、そこから垣間みえてくるのは歴史科学としての考古学の集団自殺であり、マスメディアと一体となって垂れ流される恣意的かつ一方的な情報の数々は、この時代を中心とする研究者の主体性と創造性、何よりもその実践的立場に改めて鋭い問いを投げかけている。」
今回は元になるテキストデータを佐々木さんより提供していただき、案内人がそれをWEBに載るように最小限度の手を加えました。本来は縦書きのため年号などは漢数字が使用されていました。今回は誤変換を避けるため、あえてそのままとしましたので、ご了承下さい。最後になりましたが、データの提供と公開のご承諾をいただきました佐々木藤雄さんにこの場をお借りして、厚くお礼申し上げます。なお、原本に掲載されていた図版は、都合により省略しました。
IV 和島集落論と水野集落論
1 第一世代の集落論
縄文時代集落論第一世代を代表する研究者であり、黎明期の原始・古代集落研究のパイオニアでもある和島誠一と、集落論第二世代の旗手であり、縄文時代集落研究のいわば少年期を青年期へと向けて疾走することになった水野正好。ともに体系的・総合的と形容されるこの二人の集落論の内容は相似的であり、相似的でありながらきわめて対照的である。
弥生・古墳時代を舞台とする世帯共同体論および家父長制大家族論とあわせて、縄文時代における母系的な氏族共同体の解明を自らの集落研究の中心的な課題に据えることになった和島の一連の分析作業の概要については、すでに前号に詳しい(109)。その中でも、とりわけ「原始古代集落論の原型」(110)と位置づけられる一九四八年の『原始聚落の構成』(111)を例にとれば、本論文の対象は、中央広場を伴う定型的集落の存在と一体となった共同規制の問題、前期以降顕著となる集落規模の拡大と労働力=人口の増大、協業や分業の一定の進展に伴う生産力の発展と定住性の高まり、住居形態・規模の変化と大形住居の性格、女性土偶や埋葬様式のあり方等々、当該期のみに限定してもきわめて多岐にわたっており、今日的な集落研究の核心に連なる基本的なテーマの大半がここには明瞭な形をとって登場していたといっても決して過言ではない。(112)
さらに鶴見川の支流に位置する神奈川県横浜市南堀貝塚の調査成果をふまえた『横浜市史』(113)所収の『南堀貝塚と原始集落』では、前記の諸課題に加えて大形石皿や「火焚場」をもつ共同広場、貝塚などの「ごみ捨場」�、湧水池と「飲み水」�、それに地形から推測される「海岸への降り道」や「船置場」など、後の水野の作業とも交差する立体的・景観的な分析視点を示し、全体として「集落を立地・形態・規模・内的構成・生産用具・生業形態・自然環境などあらゆる面から有機的・総合的に究明する姿勢」(114)を明らかにしている。(図7)
特に注目されるのが、和島集落論全体を通して認められる生産力および生産諸関係の歴史的な発展段階の把握と一体となった生業形態や生産用具のあり方に対する積極的な問題意識である。その代表例が生産経済転換以前の原始共同体に関する包括的な理論的素描を試みることになった一九六二年の『序説―農耕・牧畜発生以前の原始共同体』(115)であり、この中での和島は、集団的な狩猟・漁撈などの「共同体的な協業」や地域的あるいは世帯間の分業を中心に、労働用具の発達に伴う「個人的労働」や世帯の主体性の強化といった問題にも照明を与え、氏族社会の基礎となる「自然物採取経済に本源的な資源の集団的所有」(116)下における矛盾の分析にアプローチする姿勢をみせている。また、本論文と対をなすものとして同時に発表された『東アジア農耕社会における二つの型』(117)でも、明確な灌漑・排水施設が検出された静岡市登呂遺跡(118)の水田遺構や木製農具のあり方に言及し、その分析を通して、氏族社会に後続する弥生式水稲農耕社会の歴史的特質の剔出を、天水農耕地域として知られる中国・華北地方の初期農耕社会との対比において試みている。
和島の場合、しかも分析上のこのような特徴は、日本考古学が“神代史”の深い呪縛の底にあった戦前にまで遡って明瞭に認められる。日中戦争前年の一九三六年暮れから三七年にかけて渡部義通・伊豆公夫・早川二郎・秋澤修二・三澤章ら唯物論研究会東洋史部会に集まった研究者によって刊行された『日本歴史教程』第一・第二冊は、皇国史観がもたらす各種の抑圧の下で史的唯物論に立脚する科学的原始社会研究の自立が模索された歴史的な作業として知られている(119)。特に、「当時勃興期にあった考古学の成果を積極的にとりいれ、科学的な歴史叙述の中に生かそう」(120)とした試みなどは、ひとり考古学のみが孤立しているかにみえる近年の『岩波講座日本通史』と比べても遥かに先進的であり、革新的でさえある(121)。この画期的ともいえる“日本通史”の中で『金属文化の輸入と生産経済の発展』(122)を担当し、「農業及び諸生産の発達」や「分業及び交換の発達」など、ようやく問題の所在を鮮明にしつつあった諸課題に対する意欲的な取り組みをみせていたのが三澤章、すなわち若き日の和島であり、第二冊所収の『古墳文化と考古学』(123)でも、栗山一夫(赤松啓介)の兵庫県播磨加古川流域における“集団的組織的調査方法”にもとづく成果(124)などを援用しつつ、耕地の開拓や集落の形成と古墳群との関係、古墳に「埋葬された少数の人々」に対する「古墳を築いた人々」の文化状態、古墳築造にかかわる労働力のあり方などに言及している。
同時代における生産論的視座からの試みとしては、この他にも、先の『日本歴史教程』グループを代表する渡部や禰津正志らの先駆的な業績は有名である(125)。また、日本考古学における「土器偏重の傾向」を批判し、「経済的な社会構成」の復元こそが考古学研究の第一の目的であるとした、いわゆる“ひだびと論争”における赤木清(江馬修)の問題提起も、学史上、重要な位置を占めている(126)。しかし、全体としてみれば、未消化な理論や原則的立場の呈示、不十分な考古資料の引用にとどまることが少なくなかった戦前の諸作業に比べると、和島の戦後の一連の作業は、生産論的視座以外のものをも含めて、より具体的かつ論理的であり、何よりも問題意識は明晰である。それらを支えていたのが、自ら調査を手がけた東京都板橋区志村や登呂、南堀、それに同じく集落論第一世代に属する宮坂英弌による長野県茅野市尖石・与助尾根遺跡(127)などの新たな発掘資料と、渡部義通の社会構成論や藤間生大・石母田正らの共同体論・古代家族論の成果であり、両者の一体化の過程で集落研究のその後の発展に向けての基礎が、しかも特殊「考古学」の狭隘性(128)を打ち破る方向において整備されつつあったことは特筆に値する。
すでに明らかなように、和島集落論の意義をとりわけ豊潤かつ確かなものとしていたのは、その先駆性・体系性に高い論理性を加えた、以上のようなすぐれて主体的な研究姿勢にほかならず、それは、遠く東アジアから奈良時代までをも透視する広汎な視野の存在とも相俟って、先行する諸研究とはもちろん、戦後の多くの研究とも峻別される確かな軌跡を閉ざされた王国、縄文時代集落論という名の“独立王国”に印していたのである。
2 第二世代の集落論
これに対し、祭祀・宗教構造と一体となった集落の内的構成の解明を自らの課題の中核に据えることになった水野正好の作業は、全体的に「民族学的・人類学的な色彩」(129)が強いといわれる一方、「労働編成との関係で集団関係を論じる視点が弱い」(130)ことは従来から指摘されている通りである。
“二棟一家族論”および“三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論”の出発点となった一九六三年の最初の論文�、『縄文式文化期における集落構造と宗教構造』(131)を例にとれば、題名にもある通り、水野の分析は前出の茅野市与助尾根遺跡の合計二八軒の住居群からなる中期後半期集落の解析にもとづく集落―大群―小群という集落構造の復元と、広場および葬送・石柱・石棒・土偶の各祭式の解析にもとづく宗教構造の把握に向けられており、生産活動に関係するものとしては、わずかに「狩猟神」や「穀神」�、「消費単位」といった言葉が各祭式や大群との関連で使用されていただけにすぎない。
さらに、前号でも詳述した『縄文時代集落復原への基礎的操作』(132)の場合には、水野集落論が総合的・体系的な相貌とともに本格的な登場を果たす一九六九年のこの論文の構成は、「住まいとしての住居」をはじめとして�、「住まいのうごき」�、「住まいの流れ」�、「村の歴史」�、「村の構造と機能」�、「村のうごきと領域」等々、重層する多様なテーマにまたがっており、この中には「共同狩・漁撈に基く食料の分配」�、「原初的な農耕」、家族単位の畑」�、「狩場や漁場」などの言葉がいくつか含まれていることが注意される。しかし、労働編成や生業形態に関する以上のより直接的な記述も、水野にとってはあくまでも「村の中での家族のうごき」や「村の構造と用益の形態」を説明するための副次的な材料として取り上げられているだけであり、この問題に対する具体的な資料にもとづいた水野自身の分析は本論文のどこにもみあたらない。
事情は同じ年の『縄文の社会』(133)でも同様である。ここでの水野は「山間の村々と海浜の村々」の生業形態の違いを取り上げ、「鹿角斧を用いる植物栽培」�、「石錘による浅海性の網漁法」�、「組合わせ銛頭による刺突漁法」�、「マグロ漁を中心とする専業的漁労村」などに言及しているが、それぞれの内容や根拠の説明は不明瞭であり、やはり主題は各生業形態に対応する宗教形態の側に置かれている。
その一方、水野集落論に色濃く認められた祭祀論的視座は、和島集落論においては逆に希薄である。和島は、前述したようにかれの一連の作業で縄文時代の埋葬様式や土偶の問題に繰り返し触れており、『序説―農耕・牧畜発生以前の原始共同体』の中には抜歯風習や貝輪・耳飾りなどの装身具のあり方に言及した個所がみられる。ただし、これらの記述は、いずれも縄文時代における氏族社会の内容や性格との関連で登場をみていただけであり、埋葬様式や抜歯風習そのものの解明に和島の直接の目的があったわけではない。生産論的視座にもとづく水野の作業とまったく近似した状況が祭祀論的視座にもとづく和島の作業には看取されるのである。同じく宮坂英弌の尖石・与助尾根の調査成果などを共有しながら、縄文時代集落論にかかわる二人の問題意識や分析視点には著しい隔たりがあったといわなければならない。
祭祀論を重要な核とした水野の分析作業は何よりも個性的であり、東日本を中心とするそれまでの縄文時代集落研究には決してみられない発想の柔軟性と融通性とを備えている。古墳を舞台とする埴輪祭式の復元を試みた一九七一年の『埴輪芸能論』(134)は、自らは縄文集落のフィールドをもたないまま、西日本という独自の研究風土の中で独自の体系を作りあげることになった水野のもう一つの成果といえるものであり、さらにそれは、縄文・弥生・古墳各時代の“祭式・呪術・神話”の再構成が試みられた四年後の『祭式・呪術・神話の世界』(135)において、より大きな実を結ぶのである。
3 自然発生的血縁集団と集団婚
和島集落論と水野集落論、この新・旧二つの世代を代表する集落研究を一層際立たせていたのが二人の特徴的な家族―婚姻観である。
和島誠一の縄文時代の家族論は、いうまでもなくかれの母系的な氏族共同体論と一体のものとして提出されている。それらを特徴づけているのは、当該期を集団婚、つまり多夫多妻婚ともいうべき原初的な婚姻形態に支配された「古い無階級の氏族社会」(136)として位置づけ、同居制を基調とする個別的な家族形態は未だに成立をみていなかったとする主張の独自性と、「父の認知が不確実になるので母系制が本来」(137)であるこうした氏族的な構成のその後の行方を、後続する弥生・古墳・奈良時代を通観する視野から広く追求していこうとした作業の統括性であり、それらが相俟って、前述した生産論的視座と並ぶ大きな柱を和島集落論の内部に形づくっていたことはよく知られている通りである。
以上の家族論にかかわる和島の基本的な立場は、登呂遺跡の観察から「日本に於いては所謂大家族なるものは嘗て存在せず」とした社会学者戸田貞三に対する、個々の住居の成員を直ちに独立的な小家族とする考えを批判した『原始聚落の構成』冒頭の、「住居址とその成員が如何なる性格の聚落に属し、またその聚落の構成部分として如何なる機能を果すかを、具体的に従ってまた歴史的に追求する必要がある」という有名な言葉に端的に示されている(138)。本論以外にも、もちろん『南堀貝塚と原始集落』や『序説―農耕・牧畜発生以前の原始共同体』�、『東アジア農耕社会における二つの型』�、『考古学からみた日本のあけぼの』(139)、『弥生時代社会の構造』(140)�、『住居と集落』(141)、『集落と共同体』(142)など、和島の家族論の舞台となった論文は多く、その中味も決して一様ではないが、前号でも詳述した和島家族論の全体像を段階を追って改めて示せば、ほぼ次のようにまとめられる。
一、資源の集団的な所有と集団婚の基礎の上に立つ縄文時代にあっては、女性土偶などからもうかがわれるように集落それ自体が母系的な氏族共同体的性格をおびた一つの「強固な統一体」(『構成』)として存在し、住居の配置から生産・祭祀・埋葬の各面にわたる強い規制力を発揮する。
二、このような、いわば「自然発生的な血縁集団」(『構成』)の内部にあっては、とりわけ戸田が考えるような同居制にもとづく独立的な小家族の形成を想定することは困難である。住居内の炉によって表徴される一世帯はあくまでも「同質の劣弱な単位」(『構成』)にとどまっていたのであり、わずかに生活の構成の面においてある程度の独立性を発揮しうるにすぎない。
三、ただし、前号では触れられなかったが、「同じ棟の下に一つの炉を囲んで住む一団の人々」『構成』の具体的な内容についての和島の発言は不明瞭であり、跛行的である。一九四八年の『構成』の場合には、個々の竪穴の成員数に関する記述はあっても、成員の中味に関する具体的な説明は一切みあたらない。一方、一九五八年の『原始集落』には「一竪穴の成員は、ひとつの血縁集団のなかでの自然家族を単位とするものと思われる」という記述があり、本論文および一九六二年の『序説』では、右の問題に関連して「男二人、女二人と一人の子供が、中毒死か何かで折り重なって倒れていた」千葉県市川市姥山遺跡B9号住居址内遺棄人骨資料(143)の引用が行われている。しかし、一九六六年の『住居と集落』では、与助尾根における水野の集落分析結果を援用する形で一集落内部の居住域が男性と女性、それに長老の属するグループ毎に分割されていた可能性が呈示されており、わずか四年の間に見解の大幅な変更・修正が図られているようにみえることが注意される。(144)
四、いずれにせよ、この時期の通婚や交換関係などを通して恒常的な接触を保ち、緊密な結びつきをみせることになった各集落は、採集経済の発展とともにやがて「地域社会」(『序説』)を構成するようになる。とりわけ後・晩期の土器型式にうかがわれる相対的に小さな地方色は以上の範囲を暗示するものとしてあるが、こうした「小社会」(『あけぼの』)がこれまでのべてきたような氏族の広がりを示すものなのか、それとも「部族的結合」(『序説』)といった存在を意味するものなのかについては、現状では推測の域を出ない。
五、これに対し、「父権が母権の強い抵抗をうけながら、覇権を確立しようとした時代」(『二つの型』)、すなわち、一方で前代からの集団婚的な伝統を残しながら、すでに対偶婚が行われつつあった時代とされるのが続く弥生時代であり、水稲農耕の開始とその発展に伴う私有財産や萌芽的な階級分化の動きと照応するようにこれまでの氏族共同体的な関係が解体し、生産の面でも消費生活の面でも一定の独立性をもった水田経営の主体たる小集団が集落の内部に分岐する。
六、「全体が一つの単位」(『二つの型』)をなす縄文時代には決して認められることのなかった以上の「新しい小集団」(『構成』)こそは、数軒の住居を単位とする「世帯共同体」と呼ばれるものであり、「家族の前身」(『あけぼの』)をなすものにほかならないが、しかしそれは、集落の構成要素としてなお「生産の統一体」(『二つの型』)たる集落全体に依存し、その規制を多く受ける立場にとどまっている。なお、『構成』では、和島はこの「世帯共同体」の構成員数を福岡市比恵の環溝集落(145)の「一群」をもとに約二〇〜三〇人と見積もっている。また、『二つの型』では、登呂の東区と西区の二つの「集群」をもとに「世帯共同体」の具体的な構成を住居一〇軒以上、五〇人前後のまとまりとしてとらえている。
七、ただし、この「新しい小集団」の性格も、階級分化の現実的な進行とともに変質し、古墳時代の後半には、大小の規模を異にするいくつかの住居の集合体である「小世帯の群」(『構成』)の出現をみるに至る。以上の「小世帯の群」こそは、下総国葛飾郡大島郷の養老五年(七二一年)の戸籍に示される「郷戸」の母胎ともいうべき血縁的な大家族の一単位、そしてまた「それぞれの竪穴は郷戸を構成する房戸」(『集落と共同体』)にかかわるものであり、母系制の名残りともいうべき夫婦別居制の伝統を強く残したかかる家父長制的な大家族の登場の中に、「やがては更に後世の小家族発生の前奏曲」(『構成』)をわれわれは見出しうるのである。
すなわち、以上を要約するならば、集団婚を経て対偶婚、家父長制大家族、そして小家族へ、というのが和島の想定する原初的な家族の大まかな発展の図式であったことは確実であり、さらに『序説―農耕・牧畜発生以前の原始共同体』では、旧石器時代の古い段階を舞台にした、「おそらく数人か十数人の血縁者」の集団、L�・H�・モルガンらが原始的な乱婚状態にあるとした「群(Horde)」の問題についても言及を試みている。つまり、より大きな血縁集団からより小さな血縁集団へ、であり、そこには『家族・私有財産・国家の起源』におけるF・エンゲルスの、モルガンの『古代社会』に啓発された血縁家族―プナルア家族―対偶婚家族―家父長制家族―一夫一婦制家族という進化主義的家族観の強い影を容易にみてとることができるのである。(146)
4 集落―大群―小群と部族―家族―小家族
一方、水野正好が想定する家族―婚姻観の大まかな輪郭は、かれの最初の試論、『縄文式文化期における集落構造と宗教構造』の中にすでに明確な形をとってあらわれている。それが、先にものべた水野のいわゆる“二棟一家族論”と“三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論”であり、以後、両者は、提出年代による微妙なトーンの違いをのぞかせながらも、水野集落論全体を貫く基本的なモティーフとして今日へと続いていることは周知の事実である。(147)
一九六三年四月の日本考古学協会大二九回総会における研究発表要旨として提出された本試論の記述は、表1にもみられるようにごく簡潔であり、内容的に多くの不備を残している。特に炉縁石の有無や住居の重複関係をもとに二八軒の住居群を与助尾根前期と与助尾根後期に分ける一方、「内に(2棟×3小群×4大群=24棟)の住居を計画造成」というように、一見、二時期区分を否定しているかのようなあいまいな記述の認められること注意されるが、ともあれ、与助尾根遺跡に対する宮坂英弌の調査成果や分析手法をも援用しながらまとめられた水野の原基的な家族論の特徴は、同じく次のように要約することができる。
先ず第一点は、縄文時代では集団婚が支配的であるとした和島に対し、当該期には同居制にもとづく、おそらくは単婚的な「小家族」がすでに登場をみていた可能性がはっきりと指摘されたことであり、しかも、「性別ないし機能集団」としての性格も考慮されるかかる「小家族」は二軒の住居を一単位として成立するものであったことを、与助尾根集落におけるいわゆる「小群」の分析結果にもとづいて明らかにしたことである。
第二点は、二軒を単位とする「小家族」のさらに上位には、水野が埋葬・消費・政治の基本単位であるとした「家族」が存在していた可能性を、六軒の住居、つまり三小群から構成される「大群」との関連において指摘したことである。
第三点は、こうした三小家族―六軒の住居を包摂する「家族」すなわち「大群」は、東群と西群の併存現象にもうかがわれるように与助尾根では合計二群存在し、両群が一体となって「部族」としての「集落」全体を構成するという、すぐれて立体的な縄文集落像を呈示したことである。
さらに第四点は、集落―大群―小群という重層的な群構成と部族―家族―(単婚?)小家族(または性別ないし機能集団)というレベルの異なる社会集団とを重ね合わせた水野が、続けて与助尾根における祭式を集落そのものに基盤を置く「広場祭式」、集落〜大群間に基盤を置く「葬送祭式」、大群〜小群間に基盤を置く「石柱・石棒・土偶祭式」の三類に分類し、全体として与助尾根の集落構造と宗教構造とを一体的に復元する総合的な分析視点を呈示したことである。
そして第五点は、住居出土の特殊な付属施設をもとに措定した大群〜小群間に基盤を置く各祭式の性格を、狩猟神・祖家神にもとづく男性祭式としての石柱祭式、性神・成育神にもとづく同じく男性祭式としての石棒祭式、穀神・母神にもとづく女性祭式としての土偶祭式としてそれぞれ位置づけ、内容・形態を異にする以上の各祭式が各小群に分掌されるという、まさしく祭祀論的視座に大きく立脚した特異な家族像の描出を試みていたことである。すなわち、“三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論”の成立である。(図8)
和島が水野の家族および集落論をどのように評価していたのか、現在残されている資料からは、この点に対する十二分な解答を引き出すことはできない。しかし、一集落内部が男性と女性、それに長老の属するグループの
三者によって分割居住されていたという先の和島の一九六六年の発言は、いうまでもなく水野の第五点をふまえた指摘としてあり、集落論第二世代の登場が先行する和島に与えることになった影響には決して小さくないものがあったことを教えている。和島にとっては、しかし、水野のいう「小群」は、単婚的な「小家族」ではなく、あくまでも「性別ないし機能集団」的な性格をもつ限りにおいて確かな意味を有していたのであり、ここに縄文時代の家族論にかかわる二人の固有の姿勢がうきぼりにされていたことは明らかである。
5 父系外婚集団と大家族
「小群」の厳密な性格、「小家族」と「家族」との関係など、最初の試論では不明瞭であった点を含めて当該期における家族の問題に再度、積極的な取り組みをみせていたのが一九六九年の『縄文時代集落復原への基礎的操作』である(148)。縄文時代という枠内とはいえ、和島と比べて遥かに多様な分析視点をこの記念碑的な論文において呈示することになった水野は、特に一九六三年の問題提起に対する論理的・資料的な補強といくつかの内容上の変更とをこの中で試みている。
このうち、前者を代表するのが「一棟に家長夫妻と幼児、多の一棟に家長と出自を同じくする男子や子どもが居住していた」という、いわゆる住み分け論の提唱である。すなわち、本論文において中部・関東地方を中心とする早期〜後期の集落資料に分析を加え、与助尾根にみられた二棟を一単位とする小群の分布がほぼ縄文時代に一貫して認められる普遍的な現象であり、「時に一棟が附加的にある」ことを指摘した水野は、続けて「二棟が住まいとして共通の流れと常々の密接な交渉をもたなければならない」理由として前述したような特徴的な居住様式をあげ、試論では与助尾根のみにとどまっていた“二棟一家族論”の舞台と内容の拡大・拡充を一体となって進めている。
さらに注目されるのが、こうした住み分け論を介して示された夫方居住にもとづく単婚的な色合いの強い家族形態の存在である。試論における「小家族」と並ぶ「性別ないし機能集団」という「小群」の性格付けは、ここにおいてはっきりと否定されるのであり、以上を通して和島の“集団婚―母系的氏族共同体論”との距離を一層鮮明なものとした水野は、家族の構成員はそれぞれ固有の「座」を住居内に有していたこと。各家族は住まいや埋葬の場をはじめとする共同規制を強く受ける反面、消費や一部の生産の面で一定の独自性・自立性を獲得しつつあったこと。早期にはすでに出現をみる「二棟一小群」という集落の「型」のその後の変化をふまえるならば、縄文時代の集落は「早期には一家族程の地縁集団で構成され、中期には基本的には三家族、六家族の地縁集団で構成された」蓋然性が高いこと等々、各方面にわたるきわめて多彩な家族論を次々に展開している。
その一方、一九六三年の試論でもあいまいであった「大群」と「小群」との内容的な区別はここでも依然として不明瞭であり、「大群―家族」という先の言葉を含めて本論文からは大群の性格を想定させる一切の記述は消滅している。また、同じく単婚制に基礎を置いていたとしても、「家長と出自を同じくする男子」を含めて二棟の住居に住み分ける本論文における小群のあり方は「小家族」という範疇を少なからず逸脱しており、試論とのニュアンスの違いをのぞかせている。
事情は「集落―部族」の場合でも同様である。前号でものべたように八ヶ岳西南麓の例から当該期の集落の「領域―テリトリー」を三〜四平方?qと推測し、さらに以上の領域のいくつかが一つの「圏」を作りあげていたことを指摘した水野は、この「圏」が部族としてとらえられる可能性に触れている。「宗教的にも、婚姻上からも、また経済上からも相互にコミュニケイトされた」とする水野の「部族」観は、その地理的範囲を広げつつ、基本的な訂正が図られていたことは間違いない。
こうした内容上の変化がより顕著に看取されるのが“集落の分割構造論”で知られる一九七四年の『集落』である(149)。本論文における家族の記述はごく部分的であるが、ほぼ一九六九年の住み分け論に沿った形式をとっており、「恐らく二棟のうち一棟は戸主棟であり、一棟は兄弟などの主とする棟」であること、二棟を分有する一家族の構成員は一〇人前後を数えることなどがのべられている。問題は水野集落論の原点ともいえる与助尾根遺跡の評価であり、それまで二大群からなる集落の典型としてとらえられてきた本遺跡は、ここでは隣接・相関しあう二つの集落の実例として取り上げられている。すなわち、従来、集落を構成する基本単位として重要な意義を担い、「他の集落跡においても充分指摘しうるものである」(150)とされてきた「大群」という概念は、水野の新たな与助尾根集落像の呈示とともにその機能を完全に停止するのであり、また、そうした動きと軌を一にするように、「小群」という用語法も本論文中より姿をまったく消してしまうのである。“部族―家族―小家族”に対する“集落―大群―小群”という試論以来の水野集落論の重層的な枠組みは、その外皮のいくつかを除いて、ここに根本的な転換を促されていたとみなければならない。
それにかわって新たに試みられていたのが、大林太良や長崎元広の問題提起(151)、とりわけ大林の民族学的作業を強く意識したと思われる父系外婚組織論の導入である。前号でも指摘したように、その舞台となったのが与助尾根と千葉県船橋市高根木戸、松戸市貝の花の中・後期の三つの遺跡であり、本論文で「二棟三単位の類型」をもつ二集落の隣接例に変更された与助尾根に対し、集落の分割線から「二棟四単位二分割の類型」をもつ集落例として後二者をとらえることになった水野は、それぞれにみられる二分あるいは三分割の構造を双分組織・双分制、三分組織・三分制と結びつける考えを示している。水野自身の詳しい説明はないが、先の大林論をふまえるならば、二分、三分割構造に対応する以上の双分、三分組織こそは、単なる儀礼上の対抗集団という次元を超えた、おそらくは父系的な外婚集団に対比されうるものにほかならず、当該期の婚姻関係は、したがってかかる集団を単位に同一集落内、もしくは隣接・対応する二〜三集落間というごく限られた範囲において成立していたというのが夫方居住婚に立脚する水野の通婚観の概略であったことはすでに明らかである。
もちろん、氏族そのものが内部における婚姻が禁止された外婚単位として機能していたことにも知られるように、母系、父系の違いを別にすれば、双分的な外婚組織自体は、実は和島が想定する集団婚を基礎とした「古い無階級の氏族社会」の段階からすでに認められる。「外婚制および氏族の出現の問題は、本質的に、通婚関係にある二氏族よりなる体系、すなわち双分=氏族組織の出現の問題である」。旧ソ連邦の歴史学者であり哲学者でもあるユ・イ・セミョーノフは、『人類社会の形成』の中で右のように書いている(152)。また、エンゲルスも、自身がセネカ族の養子であったモルガンのアメリカ・インディアンに関する研究や氏族=プナルア婚起源説(153)などを引用しながら、「部族が当初分裂してできた本源的な氏族」としての二つのフラトリー(胞族)の問題に触れている。(154)
しかし、和島の氏族共同体論の中には、「この族外婚の原則によって分けられた単位集団として氏族(Clan)が成立する」(155)という新石器時代以前の血縁集団を対象としたわずかな記述を除けば、集団婚の具体的な形態や内容に直接言及を試みた部分はみられず、何よりも一九七一年の秋に六二年にわたる生涯を閉じることになったかれからは、水野の双分組織・三分組織論に関するどのような評価もついに与えられることはなかった。当該期の集落を母系的な自然発生的血縁集団とみなし、土器型式にみられる地方色と通婚関係とを対比させる視点を示すことになった和島の相対的に広域的な通婚観に対し、この時代の集落を数家族、数十人からなる地縁集団としてとらえ、せいぜい隣接する数集落間において小群をもっとも基本的な単位とした女性の交換が執り行われていたとする水野の父系外婚組織論は、紛れもなく集落論第二世代の“業績”といえるものであり、以上の衝撃的な仮説の登場とともに、水野集落論は、その“高い想念と問題意識”に支えられた体系化の作業をほぼ完了することは前号でものべた通りである。
V 群別作業の系譜とその問題点
1 塚田光の一棟一家族論
和島誠一が他に先駆ける形で自己の集落論の全体像を整え、水野正好の集落論が日本考古学の新たな地平を切り拓きつつあった一九六〇年代は、和島の“集団婚―母系的氏族共同体論”とも、水野の“二棟一家族論”とも異なる、もう一つの縄文時代家族論が成立をみることになったことでも知られる。水野と同時代に属する塚田光の、一軒の住居を単位とする明快な単婚小家族論がそれである。
和島の『原始聚落の構成』から一八年、水野の『縄文式文化期における集落構造と宗教構造』からも三年、塚田の家族論の舞台となった一九六六年の『縄文時代の共同体』(156)は、当然のように先行する二人の研究を強く意識した内容と構成とをとっている。
たとえば塚田は、本論文の冒頭において「共同体の研究をさらに推しすすめるためには、まず考古学研究の成果の中から共同体を理解する上で、その第一義的な資料を提示することが先決であり、その後に民族学、社会学など、関連する学問の助力を得ることが出来る」と書いている。また、前・中期の共同体に関連した部分では、与助尾根遺跡のあり方などにも触れながら、「前期以後に発掘される多数の竪穴住居址群はしばしば大集落址として誤解されるが、これは、幾多の重複による最終の結果にほかならない」とものべている。
直接、名指しこそ避けているものの、前者が和島と水野の二人の集落論に色濃く認められる演繹的な論理と分析手法、また後者が、二人を含めたこの時期の研究者全体に広く認められる同時存在住居数を大きく見積る傾向(157)に向けられた批判の言葉であったことは確実であり、そこには集落論の今日的な水準にも通じる塚田の高い問題意識と先見性とを容易にみてとることができる。
とりわけ注目されるのは、同じく本論文冒頭における、「家族の全成員をそこに結集すると同時に、家族相互間の混淆を防ぐ役割をはたすものである」という住居の本質的な機能に関する塚田の発言である。先の『原始聚落の構成』における「住居址とその成員が如何なる性格の聚落に属し、またその聚落の構成部分として如何なる機能を果すかを、具体的に従ってまた歴史的に追求する必要がある」という和島の原則的かつ慎重な立場に比べると、この問題に対する塚田の立場はきわめて実際的かつ積極的であり、むしろ和島が先に批判を試みた戸田貞三の社会学的考察とも重なり合う視点を示しつつ、「共同体内の“家族”の有無」と「内容」の解明を中心とした分析作業に取り組んでいる。
ここではその詳細にまで触れる余裕はないが、以上の作業にあたって塚田が着目するのが住居内遺棄人骨と屋内炉の二つの考古資料であり、特に後者を「食物の受用」と深いかかわりをもつものとする基本的な立場から、「家族を欠除する血縁共同体」、つまり和島のいう自然発生的な血縁集団の存在が想定されるのはあくまでも屋外炉が一般的であった早期までであること。屋内炉が普遍的になる前期以降については「家にもとづく共同体を、共同体内の最小の一単位と考えることが出来る」こと。かつて和島が自然家族を示すものとした、「何等カノ事情ノ為、同時ニ横死」(158)をとげたと考えられる姥山遺跡の「成人男女と子供という組合わせは、婚姻関係にある一世代と、未婚の子女という推論が成り立つ」可能性が高いこと。「一竪穴住居に住んだ“家族”は一世代または二世代の同居から成る小家族であり、前・中期の一集落はこうした家にもとづく小家族数戸からなる共同体がその基本的な内容」であること。土器一型式によって時期と地域を限定された多くの集落を山内清男らの指摘(159)にもあるように部族の構成単位としての「一つの胞族」として理解するためには、なお多岐にわたる証明が必要であること等々、従来の家族論の枠組みを超える意欲的な見解を各分野にわたって明らかにしている。
すなわち、一軒の住居を一家族の住まいとすることについては共に否定的であった和島の“集団婚―母系的氏族共同体論”と水野の“二棟一家族論”に対する、いうならば“一棟一家族論”であり、しかもその構成を一世代または二世代の同居からなる単婚小家族として明確に規定することになった塚田の問題提起は、以後、和島や水野の二人の提起とともに、縄文時代家族論を代表するテーゼの一つとして現在に至る影響を日本考古学に与えつづけていく経緯は以前にものべた通りである。(160)
2 住居内遺棄人骨資料と複婚家族
ただし、それぞれの学史的意義の高さにもかかわらず、このような三人三様ともいえる和島誠一、水野正好、塚田光の家族論のその後の展開は、以上の中味にもまして多彩であり、決して看過できない大きな差を内在させていたといわなければならない。
先ず、前節で取り上げた塚田論についていえば、後年、春成秀爾も自らの家族論の根拠とする姥山などの住居内遺棄人骨や屋内炉に照明をあてたかれの作業は、すぐれて具体的な資料がもたらす説得力と一棟一家族という明快な論旨のもつ具体性においてもっともぬきんでた存在としてある。
しかし、その反面、塚田が想定する単婚小家族の「内容」や意義に関する詳しい説明は本論文のどこにもみあたらず、住居の機能や屋内炉に関する過大ともいえるかれの評価に対してもこれまでに多くの疑問が寄せられている。「家族の全成員をそこに結集すると同時に、家族相互間の混淆を防ぐ役割をはたすもの」とする塚田の住居観に対する「静止した社会学的方法」にすぎないという堀越正行の批判(161)はその一例であり、三上徹也も、塚田論の限界性を「炉の等質機能論に立脚する竪穴住居の均一機能論」という点に求めている。(162)
塚田に対する批判は三上のいう「炉の等質機能論」の側からも加えられている。屋内炉は「竪穴住居の出現とともに殆んど不可分の施設として存在したと考えるべき」であるとして塚田論を否定する同世代の小林達雄の試みがそれであり、小林は、ここでは、「人工的かつ永続性のある居住空間」である竪穴住居が明確な出現をみる縄文時代早期にこそ「家族の主体性確立の画期」は求められるべきであるという見解を提出している。(163)
さらに注意されるのが姥山の五体の遺棄人骨にみられる偏った年齢構成のあり方であり、何よりも本例を五人同居=五人同時死亡を示すものとしてきた従来の通説の妥当性である。
堀越は先の批判に続けて塚田の姥山例の解釈についても疑問を呈し、住居内遺棄人骨がその住居に起居した人間の実態を知る上での唯一の資料であること自体は首肯しつつ、姥山の五体の人骨を即、一まとまりの家族へと短絡的に結びつけようとする塚田らの考えに大きな警鐘を発している(164)。その根拠にあげられていたのが、和島を含めた多くの研究者が一家族の内容、もしくは同一住居の居住員数を復元する上での良好な指標として位置づけてきた五体の人骨にみられる年齢構成の偏りであり、年齢差の小さい成人男女各二人に幼児一人という本例の構成と塚田の単婚小家族論との間の矛盾を指摘した堀越は、その上で、「このような住居内人骨からみた成員構成が、一般的なものであったか否かは、もう少し類例を加えてからにした方がよさそうである」というきわめて慎重な姿勢を表明している。
特に前出の春成は、塚田論を真っ向から否定し、年齢差の小さい成人男女各二人の同居という不可解な問題の解明を一夫一婦制にかわる新たな家族形態の導入によって試みている。それが、抜歯型式や装身具着装原理の分析、小泉清隆による年齢再鑑定結果などをふまえた春成の独自の複婚家族論の提唱であり、以上のデータをもとに、従来、母親と未婚の子女とされてきた女性同士を姉妹としてとらえかえすことになった春成は、姥山例についてはそうした「妻同士は姉妹の一夫二妻と一妻二夫の結合した形態」、もしくは「兄弟二人と姉妹二人との間に成立するプナルア婚」であった可能性こそが考慮されるべきであるというきわめて大胆かつ斬新な仮説を提出している(165)。集落論第二世代としてはもっとも若い年代に属する家族論であり、一九八一年における春成の提起とともに、縄文時代家族論は、その内容・形態とも、以前とは比較にならないほどの多様化と複雑化をとげるようになることはよく知られている通りである。
しかしながら、誤解を恐れずにいえば、姥山例を援用した塚田の家族論の問題点は、堀越と春成が指摘する五体の年齢構成に対する塚田の解釈の仕方そのものとはまったく別個のところにある。塚田論の最大の誤謬は、姥山例を五人同居=五人同時死亡を示すものとする調査時以来の一貫した見解、いわば“幻の前提”を自らの家族論の基礎に据えていたことであり、そのような意味では、塚田を批判する堀越と春成の二人も、実は塚田と同様の誤りを姥山例の評価をめぐって揃って犯していたことは否定できない。
すなわち、一九二六年の東京大学人類学教室の調査によって姥山B9号住居から発掘されることになった五体の人骨は、これまで広く考えられてきたように本住居の成員だけで構成されていたわけでも、食中毒などが原因で同時死亡した遺体だけで構成いたわけでも決してない。五人を数える居住者全員が瞬時に横死をとげ、異常な死を恐れた人々によって家屋ごと放置されることになったというこれまでの通説は、姥山例の皮相的な観察結果にもとづく誤った常識であり、まさしく“幻の前提”にほかならない。
むしろ、その実体は、これまでほとんど等閑視されてきた第三者による何らかの埋葬行為を示すと思われる硬質の褐色土の存在や各種の生活用具の除去行為などにもうかがわれるように、前後2回にわたって行われた二つの人骨グループの本址への遺棄、ないし埋葬の最終的な姿として考えるのがもっとも妥当であり、床面西寄りに単独分布していた1号女性(20〜29歳)は、比較的整然と
したその遺存状態からみてもいわゆる屈葬の範疇(図9)でとらえられうる可能性が高いことは近年の佐々木の作業が明らかにしていた通りである。(166)
1号女性と残る四体との間には両者を隔てる空間の距離にもまして大きな差が横たわっている。五人同居=五人同時死亡論に立脚した家族論は、自然家族、単婚小家族、複婚家族の別にかかわらず、いずれも“幻の前提”にもとづいた誤った推論であり、その成立は等しく困難である。従来からいわれているような不慮の事故にもとづく同時死亡の可能性、したがって同一住居への同居の可能性が考慮されるのは、あくまでも入口部と思われる床面南寄りに折り重なるように倒れていた2号男性(20〜24歳)�・3号男性(30〜39歳)�・4号幼児(5〜7歳)�・5号女性(30〜40歳)の四体の人骨であり、そうであれば春成が1・5号の二体の成人女性を姉妹とみることによって止揚を図った前述の年齢構成上の矛盾も、一挙にその過半を解消することが知られるのである。(167)
塚田の家族―婚姻観は、ともあれ、その論理と実証の両面から根本的な見直しを迫られていたといわなければならない。
3 和島の母系的氏族共同体論の陥穽
それでは、和島の家族論の場合はどうであろうか。
渡部義通や藤間生大、石母田正の社会構成論、古代家族論に加え、K�・マルクス、F�・エンゲルスらの古典理論をも自らの基盤に据えることになった和島誠一の体系的な集落研究、とりわけその先頭に位置する氏族共同体論に対する研究者の支持は、和島の作業を直接視野に入れた一連の後継的な作業、いわゆる“ポスト和島集落論”の存在が端的に物語っていたように、現在でもなお根強いものがあることはよく知られている。
しかし、こうした“ポスト和島集落論”を含め、明確な理論と問題意識の下に「科学的原始社会研究の自立」(168)を図ることになった和島の氏族共同体論は、実はその成立当初から、自らの立論にかかわる重大な矛盾や問題点を奧深くに抱えていたのであり、しかもそれらは、今日、きわめて畸形化された氏族共同体像の登場をみるまでに深刻なものとなっていたことに注意を払わなければならない。
問題点の一つは、和島の氏族共同体論の中核を占める集団婚論の是非である。
「L�・H�・モルガンの研究に関連して」という副題をわざわざ添えることになったエンゲルスの『家族・私有財産・国家の起源』とは異なり、モルガンの業績を高く評価しながら、かれの提起する集団婚論に対してマルクスが早い段階から懐疑的であったことは広く知られている。しかも、マルクスのこうした見通しの正しさは、その後の民族学や人類学の発展に伴う集団婚の実在性の全面的な否定によって確かな裏付けを与えられている(169)。前述したようにエンゲルスの『起源』に多くを依拠し、血縁家族とプナルア家族という二つの集団婚のうち、縄文時代についてはおそらく後者(170)を想定していたと思われる和島の集団婚論の成立は、理論的にも、また、実証的にもまったく困難である。むしろそこには、「多分に文献史家によって展開された古代家族論という理論で、考古学的現象をつつみ込むという傾向を内在させていた」(171)という、先に甲元眞之が批判を加えた弥生〜古墳時代を舞台とする世帯共同体論や家父長制大家族論と共通する土壌を見出しうるといっても誤りではない。
もう一つは、右とも深くかかわる問題であるが、和島の作業全体を通して認められる考古学的な証明の不十分性である。
塚田光の先の批判にもある通り、時代の大きな制約の下で育まれることになった和島の一連の研究はきわめて理論先行的であり、「不十分な資料がこれに追随するといった傾向」(172)を強く内在させている。獲得経済社会をめぐる矛盾のあり方に照明があてられることになった『序説―農耕・牧畜発生以前の原始共同体』を例にとれば、縄文時代における協業や分業に対する本稿の分析は、和島自身が直接調査に従事した登呂の水田遺構をふまえた『東アジア農耕社会における二つの型』での弥生時代の労働編成解明作業や、後の『集落と共同体』における「竪穴生活の自律化をしめす内部施設」(173)とされた古墳時代のかまどや貯蔵穴資料に対する分析作業などに比べると著しく具体性に欠けており、“試論”的な色彩の強かった『原始聚落の構成』における問題提起との間にも際立った違いは認められない。
特にこうした傾向が顕著に指摘されるのが、今、問題となっている縄文時代の家族論に関する部分であり、テーマそのものの重要性とは裏腹に、結局のところ和島の分析は大半が概念的なレベルで終わっている。何よりも親族・婚姻原理をふまえた直接的な議論といったものは、前号でも触れたように何故かほとんどみあたらず、同時存在住居群の配置状態などから集団構成への接近が試みられた弥生〜古墳時代を対象とする田中義昭や金井塚良一との共同作業とも看過しがたい差異をのぞかせている(174)。むしろ、「こうした社会構成こそは、血縁共同体あるいは氏族共同体といわれるものである。そして、縄文時代が氏族共同体であったからこそ、その全期間をとおして、個々の住居はいうにおよばず、生産と消費がつねに等質な社会が維持されたのである」(175)という、ポスト和島集落論を代表する勅使河原彰のきわめて肥大化された公式的・教条的な氏族共同体観が図らずもうきぼりにしていたように、単独作業となった縄文時代をめぐる和島の分析手法はとりわけ演繹的な色合いが強く、母系的な氏族社会というかれの仮説、いわば「演繹的な論理」(176)に考古学的な修飾を施すための一つの手段として女性土偶や埋葬様式などの考古資料の大雑把な引用が試みられていたといっても決していいすぎではない。(177)
『原始聚落の構成』にはじまる和島集落論の基本的な立場が、先行する共同体論や古代家族論などの業績をふまえながらも「日本に於ける原始聚落の実相とその変遷」(178)を幅広い視野から歴史的・具体的に追求しようとした点にあり、したがってそこには、マルクスやエンゲルスらの素描する古典的な原始共同体像の援用だけで個別縄文社会の全体像を概括しえたとする文献主義的な誤謬、さらには特殊「考古学」の狭隘性からの脱却に賭ける和島の強い意志がみてとれることは改めてのべるまでもない。
しかし、そうした熱意や、絶対的な資料不足を補って余りある豊かな先見性と鋭い着眼点にもかかわらず、自らの前提にかかわる多くの考古学的未証明状態、とりわけ理論と実証との間の埋めがたい亀裂をあいまいにしたまま押し進められることになった和島とその周辺の作業は、ポスト和島集落論を中心とする教条主義的な論理・方法の一方的な適用とも相俟って、和島自身が一貫して希求してきた「科学的原始社会研究の自立」(179)、何よりも和島集落論の科学性そのものを根底から損なう方向に帰結する。また、そのことによって、縄文時代集落論の今日的な停滞の最大の要因を和島に代表される「マルクス主義歴史学の理論的枠組」に求めようとする羽生淳子のきわめて偏狭な史的唯物論“批判”の温床を形づくる結果に陥っていたことは、きわめて皮肉であったとしかいいようがない。(180)
近年、勅使河原は、平等原理のみの一方的な強調に偏してきたこれまでのポスト和島集落論を修正し、婚姻原理や家族構成に対する歴史的な視点がまったく欠落しているという佐々木からの批判(181)にも答える形で、「少なくとも縄文時代の住居の構成員は、一夫一妻からなる単婚家族を基本として、その単婚家族の1人を共通成員として結ばれた二つ以上の単婚家族からなる複合家族、さらに単婚家族の複数が組み合わされる複婚家族から成り立っている」(182)という、新しい、しかし非常に煩雑な家族論を提出している(図10)。その当否、および家族の概念規定上の問題はともかく、勅使河原の右の言葉がはしなくも示していたのは和島の集団婚論の全面的な否定であり、和島にはじまる母系的氏族共同体論・自然発生的血縁集団論の内側からの変質・崩壊であったことは論をまたない。(183)
三人の多様な家族論の中でも、もっとも実践的ともいえる熱く広い支持を得ることになるのは、いわゆる“群別作業”の盛行にも知られるように、明快な図形性と「考古学的な追証」(184)性に裏付けられた、水野正好の“二棟一家族論”であった。
4 進展する群別作業
和島誠一の“集団婚―母系的氏族共同体論”をめぐって色濃く認められた先の演繹的な分析手法は、もとより、ひとり和島論のみに特有のものとしてあったわけでは決してない。「和島は、日本列島のなかで成立していた氏族共同体、という前提にもとづいて論理を組み立てた。水野の発言は、見かけのうえでは混沌とした縄紋時代の集落も、いくつかの「型」に整理できるはずだ、という前提にもとづいている」。この問題に関連して林謙作も右のようにのべ、かかる「演繹的な論理」の存在こそは「両人の論文のもっとも大きな共通点」であったとさえいいきっている。(185)
ただし、同じく林も指摘するように、「共同体理論のレベルで演繹的な論理を展開」した和島に比べると、「遺構の読みとりレベルで演繹的な論理を展開」することになった水野正好の作業は遥かに多様性と立体性に富んでおり、従来の研究の枠組みを超える斬新な集落像にあふれている。
すなわち、誤解を恐れずにいえば、理論的な孤立を余儀なくされていた戦前のいわゆる原始共産制社会論の母斑を依然としてまとっていた和島集落論に対し、日常生活の一断面に至るまで縄文社会の構造を詳細かつ具体的に描写しようとする水野の集落研究は、それまでの集落論のスタイルを根本から変える内容を各所に含んでいたことは広く知られており、とりわけ“三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論”や“集落の分割構造論”など、水野の作業全体を貫いて認められる視覚性豊かな問題提起がもたらすことになった影響力には、「それまで住居群を漠然と一つのまとまりとして捉え」(186)てきた同世代の研究者を中心にきわめて大きなものがあったといってよい。
一九六三年の水野の最初の分析作業によって「与助尾根集落がはじめて見えたという強い印象」(187)を与えられたという戸沢充則の述懐については、すでに前号で紹介した通りである。
一方、長野県塩尻市平出遺跡などの資料をもとに平安時代の“村うちの道”の分析・復元を一九八四年の論文(188)において試みることになった桐原健も、「水野正好氏が尖石与助尾根遺跡の長尾根南斜面に営まれた縄文集落の内に道を設定、眼から鱗の落ちた思い」のあったことを『自著自註』の中に書いている。(189)
ともに集落論第二世代に属する二人の研究者の言葉は、水野論が縄文時代の集落研究に投げかけることになった衝撃の大きさと深さの証しにほかならず、事実、水野の“二棟一家族論”に触発される形で当該期の集落を対象とした各種の群別作業が、一九六〇年代後半以降、にわかに盛行をみるようになることはよく知られている。
その代表的な例が、八ヶ岳西麓地域を間近に仰ぎみる諏訪湖の北岸、長野県岡谷市海戸遺跡を舞台とした群別作業(190)であり、中期後半期を主体とする本遺跡の二四軒の住居群の分析を試みた前出の戸沢は、「径100m前後をかぞえる海戸遺跡の縄文時代中期の環状集落」は全体として同時期の一〜三軒前後の住居を単位とする「10前後の住居址群から構成されている可能性が強い」ことを指摘するとともに、「海戸集落における最小の単位集団」であるこれらの「群」のいくつかのまとまりを「血縁的な世帯共同体」として位置づけている。(図11) また、桐原も、尖石・与助尾根を含めた八ヶ岳山麓地域における中期勝坂期と加曽利E期の集落構成の差異に言及し、集落立地や住居プラン・規模、宗教的施設のあり方と水野の与助尾根分析結果などをリンクさせながら、前者における血縁的紐帯の強い「氏族共同体」は、後者の段階に至って「単婚家族単位の小グループに分解をしたかにも思われる」という考えを提出している。(191)
しかし、この種の作業が裾野を急速に拡大するのは水野の『縄文時代集落復原への基礎的操作』が発表された一九六九年以降のことであり、しかもそこでは、戦後団塊世代を中心とする、若手の集落論第三世代をも含めた多彩な群別作業が一気に花を開かせることが注意される。
戸沢が取り上げた海戸遺跡の埋甕の分布を視野に入れた渡辺誠の分析(192)、東京都町田市本町田遺跡の前期集落を対象とした村田文夫の分析(193)、高根木戸遺跡
の中期集落に加えて静岡県浜松市蜆塚遺跡の後期集落を対象とした向坂鋼二の分析(194)、長野県茅野市茅野和田遺跡の中期集落を対象とした宮坂光昭の分析(195)、南堀貝塚をはじめとする前・中・後期集落を対象とした菅原正明の分析(196)などは一九七〇年代を特徴づける群別作業といえるものであり、一九八〇年代には、神奈川県川崎市潮見台遺跡の中期集落を対象とした丹羽佑一(197)や藤野修一(198)らの作業が、先行する研究を追いかけるように相次いで提出をみる。
さらに一九九〇年代に入っても、鵜飼幸雄の茅野市棚畑遺跡の中期集落の分析(199)、新津健の高根木戸遺跡の再分析(200)、三上徹也の東京都八王子市滑坂遺跡、長野県塩尻市爼原遺跡などの中期集落の分析(201)等々、群別作業の流れは依然として健在であり、かえって一層の個性化を進めつつあったことが指摘される。特に、先の丹羽は、水野が縄文時代集落論にかかわる問題提起をとりやめた八〇年代後半以降も精力的に群別作業に取り組み、千葉県松戸市子和清水、群馬県赤城村三原田、岩手県紫波町西田遺跡をはじめとする中期集落を中心に“集落の分割構造論”の新たな展開を試みている。(202)
詳細はそれぞれの論文に譲るが、分析の対象や視点、方法とも決して一様とはいえないこれらの作業にほぼ共通する特徴は、簡潔にいえば「一住居、一単位で示される世帯(核家族的な)からいきなり集落(共同体)というのではなく、その中間の結合段階がいくつかあることを強調」(203)しようとした点に求められる。改めて三上の言葉を援用するならば、「炉の等質機能論に立脚する竪穴住居の均一機能論、ひいてはそこから導かれる一棟一家族論という、ともすると半ば定説化しつつある縄文時代の居住システム」(204)観に対する批判であり、その考古学的な検証に向けての並々ならぬ情熱が、反対意見をも含めた研究の輪のかつてない広がりの中で傾けられたことといえるだろう。
「一九七〇年代以降、縄紋時代の集落の問題をとりあげた論文で、この論文に言及していないものはない」(205)。『縄文時代集落復原への基礎的操作』に関する林謙作の指摘は、右の状況をもっとも的確に表現したものとして存在している。しかもそれらは、同じく林によれば「二棟一小群を基本とする住居の群構成が認められるかどうか、ほとんどその一点だけに議論が集中」するという、あるいは丹羽によれば「基礎単位によって組み立てられる集落論は魅力的であるだけに集落研究を呪縛し、研究者の関心事をその基礎単位が事実であるかどうかの一点に絞らせる」(206)という弊害をも一方で惹起しつつ、大規模開発に伴う大型発掘の一般化が進行する七〇年代を中心に、縄文時代集落論のかつてない高揚を演出することになるのである。
都出比呂志が「第二の出発」と表現した、近藤義郎の“単位集団論”の提起にはじまる弥生時代を舞台とした集落研究の高揚が認められるのも、ほぼ、この前後の時期のことであった。(207)
5 混迷する群別作業
「水野の提唱した「住まいの流れ」をたどる―言葉を変えれば「群構成」を手がかりとして集落の構成を復元する方法・・・が集落復元の定石のひとつとなっている理由は、二棟一小群・三小群一大群というモデルが、ブラック・ボックスとしてきわめてすぐれた効果を発揮しているからにほかならない。」(208)
「近藤の提示した単位集団論は構造的であり、しかもより具体性をもつゆえに考古学的な追証を可能にし、錯綜した集落址の分析にすこぶる有効性をもち、また他方では古代家族論や共同体論に対しても再検討をせまるものであった。」(209)
縄文時代と弥生時代という違いを超えて内容的な同質性を感じさせる右の二つの文章のうち、前者は水野正好の“二棟一家族論”、そして後者は近藤義郎の“単位集団論”をそれぞれ評した、林謙作と甲元眞之の二人の言葉である。
近藤の単位集団論については、かつてそれを「普遍的な理論・吟味された概念」による自己検証を放棄した“考古学における実証主義”、もしくは“考古学至上主義”にすぎないとする原秀三郎の手厳しい批判があったことは前号でも紹介した。(210)
これに対し、林のいう「ブラック・ボックス」、甲元のいう「考古学的な追証」は、表現上の差はあれ、歴史学者の視点から原が否定的な評価を下すことになった“考古学における実証主義”の考古学における優位性を、いわば水野と近藤二人にとっての共通の先駆者である和島誠一のすぐれて原則的な立場との対比において改めて鮮明にするものであり、とりわけ水野論にみられる二棟一小群という明確な単位の設定は縄文時代を舞台とした群別作業の特質を一層際立たせるものとして存在している。男女分棟という新しい視点から水野集落論の「追認」を目指した前述の三上徹也の作業はこうした「ブラック・ボックス」のありようを具体的に示す好例の一つであり、ここでの三上は「優勢炉、劣勢炉という炉形態の相違」をもとに“二棟一対型集落”の存在を重ねて主張している。(211)
問題は、しかし、林自身もその弊害を認めるように、近視眼的な偏った議論をも一方で輩出することになった水野の集落モデルをブラック・ボックスとする群別作業の質であり、優位性の中味にほかならなかったといわなければならない。
水野集落論の提起にはじまる一連の群別作業を「集落の内的構成から、集団構成を究明しようとする実践的研究」と位置づけ、「環状だとか馬蹄形あるいは弧状だとかいった静的で外観的な旧来の集落形態論を止揚して、外部と内的構成とを統一的に把握する新しい局面」を開くことになったという評価を与える長崎元広は、しかし、それに続けて、「こうした作業に用いられてきた方法と基準は何によって保証されてきたのだろうか。その点についての反省と点検が現在、おおいに必要と思う」という言葉を付け加えている。(212)
一九八〇年のこの長崎の発言を待つまでもなく、“考古学における実証主義”を背景とした縄文時代をめぐる群別作業は、実はきわめて早い段階から、その表向きの華やかさや優位性とは裏腹に自らの立論にかかわる数多くの矛盾や亀裂を露呈していたのであり、また、そのことによって、他ならぬ自らの実証性そのものに対する研究者の信頼をも大きく損なう結果に陥っていたことを決して忘れてはならない。(213)
第一の問題点は、集落の内的構成の解明を目的としたかかる群別作業の多くは、先の長崎の指摘にもあるように、その基準や方法が研究者一人一人によってまちまちであったことであり、中には水野の“二棟一家族論”の安易な受け売りや単なる数字合わせとしかいいようのない恣意的な分析の一人歩きに終わっている例も少なからず認められる事実である。
村田文夫の本町田遺跡に対する一九七〇年の分析を例にとれば、この作業における村田は本遺跡を前期諸磯期の二棟単位三小群の集落としてとらえ、「前期中葉から後半期にかけては二棟三組六軒という、中期に普遍的な集落形態が確立されたという蓋然性は極めて高い」という明確に水野集落論に沿った見解を示している(214)。しかし、村田も執筆に加わった本町田の報告書(215)によれば、かれが同時に存在したとする六軒の住居のうち、2�・3�・4号は諸磯a〜b期、1号は諸磯c期の住居としてまとめられていたものであり、残る5�・6号の二軒もいわゆる土器集中個所について村田が住居であった可能性を指摘していただけにすぎない(図12)。ふれいく同人がかつて命名した「あるはずだ」論(216)の典型的な例であり、あらかじめ決められた結論に合致するように「図上の住居跡の分布状況を想念で分割したり組み合わせたりしたもので、実態からはほど遠い」(217)ものといわざるをえない。
第二の問題点は、以上の当然の帰結でもあるが、こうした群別の結果や「群」の解釈には、同一集落を対象とした、しかも時には同一研究者による作業の場合にも、しばしば無視できない差異が看取されていたことであり、第一点とあわせて群別作業そのものの客観性や蓋然性に大きな疑問符が突き付けられていた事実である。
やはり本町田遺跡を例にとれば、先の村田の二棟単位三小群という群別結果に対し、わずか一ヶ月違いで発表された水野の論文は本町田を二棟一小群という早期以来の型をもった集落として位置づけ、「四号→三号、二号→一号という流れがあり、四・二号、三・一号住居跡の共存関係が時間的に流れをもつこととなる」というまったく正反対の考えを呈示している(218)。“二棟一家族論”の提唱者とその追随者がたまたま垣間みせることになったこうした亀裂は皮肉以外の何物でもなく、群別作業そのものにとっても単なる見解の相違では済まされない重要な問題を内包している。
同様の矛盾を露呈していたのが高根木戸・貝の花両遺跡をめぐる群別作業であり、一九七四年の論文で“集落の分割構造論”を提唱することになった水野が、その舞台となった高根木戸と貝の花の二つの遺跡について二棟四単位二分割の集落類型とする見解を明らかにし、あわせて以上の前提にある“二棟一家族論”の再構成を図っていた経緯は改めてのべるまでもない。しかし、“二棟一家族論”が確立された一九六九年の論文における水野は貝の花を二棟単位三小群の集落として実は位置づけていたはずであり(219)、また、水野と前後するように高根木戸の分析を試みた何人かの研究者の群別作業も水野とは必ずしも相容れない結果を導き出している。
たとえば菅原正明の一九七二年の作業は、高根木戸を北・東・南・西の四群、各群1時期七〜八軒からなる集落類型としてとらえている(220)。同じく向坂鋼二の一九七九年の作業は南・北二群、南群が四支群六軒、北群が欠失部分を含めて四支群五軒からなる集落類型(221)、新津健の一九九三年の作業は南・北二群、うち南群が五小群、北群が四小群、各小群多くとも1時期一軒からなる集落類型(222)というように、本遺跡をめぐって提出された群別結果は三者三様ともいえるあり方を示しており、しかも水野の二棟一小群というモデルとは揃って微妙な食い違いをみせていたことが注意される。(223)
さらにこうした矛盾の存在を一層際立たせていたのが「群」の性格付けにかかわる問題であり、群別作業を通して示される「群」の解釈は、比較的初期の段階を除くと、水野の提起とほとんどクロスすることもないまま、年を追って個別化・分散化の傾向を鮮明にしている。
すなわち、すでにこの問題に関しては、群別作業がまだ萌芽的な段階にあった一九六〇年代の例として戸沢充則の「血縁的な世帯共同体」と桐原健の「単婚家族単位の小グループ」の二つの解釈について紹介を済ませている。両者とも説明は十分であったとはいいがたいが、イメージ自体は明瞭であり、そこには「小群」を(単婚?)小家族もしくは性別ないし機能集団としてとらえようとした水野の一九六三年の提起や、それに先行して「大群」を「血縁的な世帯共同体の一集団�」として性格付けようとした一九六二年の坪井清足の提起(224)の強い影をみてとることができる。
しかし、「一棟に家長夫妻と幼児、他の一棟に家長と出自を同じくする男子や子ども」が居住していたという水野の独自の住み分け論が提出される一九六九年以降の例をみると、群別作業自体の盛り上がりとは裏腹に「群」の社会的性格に対する問題意識は研究者による差を大きくしており、中には「群」を単に「家族」とだけ記したものや、村田の本町田遺跡の分析作業のように最初から「群」の性格付けを放棄したものも登場する。
それとともに「群」の歴史的性格や概念規定に問題を残すもの、内容や構成のより難解かつ複雑なものが増加することも看過できない重要な特徴であり、高根木戸を舞台にした前出の菅原や向坂の「居住家族」、�「同居集団」(225)という一九七〇年代の発言と、「1棟の住居に親子関係を有する2世代程度の複数夫婦が居住し、2棟間におじ―おい夫婦間の関係が想定される」という西田遺跡を舞台にした丹羽佑一の一九九四年の発言(226)との間には、到底、同一の範疇ではとらえきれない質的な隔たりが横たわっていたといっても過言ではない。
「おそらく、一集落内には、家族集団・血縁集団・祭祀集団・年齢集団や、生産にかかわる種々の作業集団、そのほか様々な集団が恒常的あるいは一時的に形成されていたはずである。これらが有機的に関連し合って一集落あるいは近隣集落とかかわっていたであろう。このうち、いかなる集団をめざすのか、その目的を明確にしておくことが正しい分析を可能にするのである」(227)。長崎は、先の群別作業に関する指摘の最後を右のような言葉で結んでいる。
縄文時代集落論に中間的な結合単位という斬新な視点を呈示し、その少年期から青年期への発展をもっとも力強く支えることになった群別作業は、しかし、三〇年を超える歩みを通してなお、ともに語るべき自らの基準、自らの方法、自らの解釈、そして自らの分析の目的を確立できないままにある。
群別作業が抱える矛盾は大きく、しかも本質的であるにもかかわらず、問題解明に向けての群別作業者相互の議論は何故かほとんどみられず、ただ一方的に流布される群別の“成果”は、「考古学的な追証」よりも、それぞれの断層、それぞれの亀裂の深さを逆に証明している。
群別作業は、これまでも、そして現在も未成熟であり、しかもその長い分裂と混迷の歴史は、それらの「ブラック・ボックス」としてある水野の集落復元作業、何よりも水野の“二棟一家族論”の蓋然性と有効性をも、その根源から揺り動かしていたのである。
VI 水野集落論の光と影
1 新しい群別作業とカリエラ体系
「しかし、1棟も、2棟も、3棟以上も事実である。つまり、住居群には1棟の最小単位より大きな単位が存在して、これが2棟の場合、3棟以上の場合があり、2棟の頻度が高いということである。2棟の頻度がなぜ高いのか、私達はこれを問題とすべきであった。この様な問題設定の集落論の中に、縄文社会はその実態を明らかにするであろう。�」(228)
以上は群別作業の三〇年を総括した丹羽佑一の言葉である。自らの作業の反省をもふまえつつ、その「衝撃」と「魅力」の故に群別作業全体を強く「呪縛」してきた水野正好の集落論、とりわけ“二棟一家族論”のいわば修正論的な発展を主張しているかにもみえる丹羽の総括は、水野が縄文時代に関する具体的な発言を取りやめた一九八〇年代後半以降も一貫して“集落の分割構造論”に立脚した独自の分析を押し進めてきた研究者による提起として、きわめて象徴的な意味合いをもっている。
しかし、前節でものべた通り、これまでの群別作業が内包する矛盾や問題点はすぐれて構造的・複合的なものとしてわれわれの前にあらわれている。こうした矛盾が、たとえば丹羽がいうように、研究者各自の分析視点や問題意識の多様化をふまえた新しい群別作業の実践によって解消できるほど単純なものであったかどうかはきわめて疑問であり、まして「この様な問題設定の集落論の中に、縄文社会はその実態を明らかにするであろう」というようには、その将来を到底楽観視できない。
むしろ、群別作業そのものの裾野の広がりとは裏腹に、その創造的な発展と矛盾の止揚に向けての研究者同士の相互的な議論の掘り下げは、何故、これほどまでに不活発であるのか。何よりも丹羽自身は、群別作業全体を強く規制する水野集落論の「呪縛」からはたしてどれほど自由であったのか。丹羽がもっとも問題とすべきは、先ずこれらの点であったと考える。
こうした視点からも改めて注意を促したいのがカリエラ体系と呼ばれる特徴的な四分組織の提起で知られる一九八二年の丹羽の群別作業であり、潮見台の中期集落の分析を試みたこの論文の丹羽は加曽利E期の九軒の住居群を四分割し、本集落では以上の分割に対応する四つの外婚集団を単位に夫方居住にもとづく女性の交換が行われていたという結論を導いている(229)。先の大林太良や水野の双分組織論、三分組織論を意識しつつ、以上にもまして縄文時代の集落が複雑な親族原理と内部構成とを保持していた可能性を指摘した画期的な作業であり、考古資料の解釈にあたって民族学の成果が積極的に援用された例としても、学史上、重要な意義を有する。
しかし、その反面、本論文における丹羽の四分組織論は、埋甕型式からみて少なくとも三段階に分けられる加曽利E期のすべての住居群の同時存在と斉一的離村という実現不可能な仮説を前提としている。また、仮にそうした前提を受け入れたとしても、丹羽の想定する女性の交換は、すべての外婚集団を合わせてもわずか五〇人前後のごく限られた集落構成員の枠内で行われなければならないという、やはりきわめて現実性に乏しい論理の上に辛うじて成立をみていたことはすでに旧稿でも指摘を加えた通りである。(230)
すなわち、カリエラ体系のモデルとなったオーストラリアのカリエラ族を例にとれば、かれらは本来的には七五〇人ほどの多数の部族員から構成されており、さらに「ホルド」と呼ばれる二〇から二五ほどの地域集団は、それぞれセクションを異にする通婚可能な他の集団とチェス盤のように隣り合う特徴的な配置(図13)を示していたことは、他ならぬラドクリフ=ブラウンの民族調査報告(231)が教えていたところである。最大でも同時存在住居数が五軒を超えることはない潮見台集落との間には、集団の規模においても、地理的な範囲においても、そこには絶対的といえるほどのギャップが存在していたのであり、丹羽が呈示する集団をたとえば儀礼における対抗集団とでもみなさない限り、縄文時代を舞台にした四分組織論は、単なる机上の空論として終わるほかはなかったことはあまりにも明白である。
潮見台遺跡の再分析結果をもとに丹羽論の正当性を主張する藤野修一は、「私の今までの説明は、ある婚姻から男女一人ずつの子どもが生まれるという前提から出発している。これは、実際には、実現しない場合も在り得るだろう」という実に驚くべき論理を明らかにしている(232)。求められているのは「体系の観念的な見方と、それが実際に働いている場合との間」(233)にある相違点への明瞭な認識であり、それらの区別をあいまいにしたまま、およそ科学的原始社会研究という言葉とは無縁な恣意的・感覚的な作業がまかり通っている現状にこそ、群別作業が未だに自らの未成熟性を克服しえない理由の一つはあったのである。
2 男女分棟と優勢炉・劣勢炉
丹羽は群別作業の総括を試みた一九九四年の論文でも西田遺跡を舞台に独自の住み分け論を展開し、「1棟の住居に親子関係を有する2世代程度の複数夫婦が居住し、2棟間におじ―おい夫婦間の関係が想定される」という結論を示している(234)。方形柱穴列に囲まれた西田遺跡の環状墓壙群の分析から二基を一単位とする墓壙小群の存在を導き、それらと水野の“二棟一家族論”とを対応させながら水野の抽出した「縄文集落住居群の基礎単位―隣接する2棟1単位の集積」の再構成を目指した労作であるが、前節でものべたように丹羽が描く家族の内容はきわめて難解かつ煩雑であり、こうした“二棟一家族”が、たとえ西田のみであれ、一つの集落内で、しかも何世代にもわたって普遍的な存在としてありつづけたとする考えに対しては、先の四分組織論の場合と同様、現実と丹羽の“想念”との大きな乖離を感じずにはおられない。(235)
このことは、従来の群別作業とは一線を画する斬新な視点から“二棟一対型集落”の再検証が試みられた三上徹也の一九九三年の論文についてもあてはまる。(236)
塚田光に代表される“一棟一家族論”を�「炉の等質機能論」および「竪穴住居の均一機能論」に立脚するものとして退け、それにかわるものとして民族例をふまえた独特の分棟型居住システム論を提唱する三上論の基本的な特徴は、かれ自身の言葉にもあるように、従来�、「等質」なものとしてとらえられることの多かった屋内炉を投下労働量や調理機能などをもとに優勢炉と劣勢炉の二つに分け、以上の分類を手がかりにさらにそれぞれの炉をもつ住居間にも優劣の差を認めようとした点に求められる。特に注目されるのは、三上の群別作業が新たな�「グルーピングの基準」として「炉という比較的客観的な資料」を採用していたことであり、そのことによって住居群の空間的な分布を中心としたこれまでの群別作業が抱える問題点の克服を図った三上は、優勢・劣勢二つの炉形態の分布から導かれた「等質ではない二棟が一対住居群の集成を通して水野の呈示した“二棟一家族論”の外形的な追認へと至っている。
すなわち、当該期の集落にあっては優勢炉と劣勢炉を伴う二軒の住居に一家族、おそらくは単婚を基本とする「多人数家族」が住み分けていた。ただし、分棟の基準は性別であり、優勢炉をもつ住居に女、劣勢炉をもつ住居に男がそれぞれ住み分け、調理は女の住居の優勢炉において主として行われることになったというの三上の男女分棟論の概要である(237)。分析の視点から方法、解釈の各面にわたって独自の試みが模索された意欲的な作業であり、とりわけ三上は、この「調理により積極的に携わった人の家」という考えは、姥山例をはじめとする住居内遺棄人骨資料には「家族の住み分けを具体的に示唆するような例はまったくみあたらない」という佐々木の“二棟一家族論”を批判した発言(238)に対する、群別作業の側からの「反証」という意味をもあわせもっていたことを付記している。
しかし、こうした姿勢とは別に、具体的に呈示された分析結果の側に目を移すと、実際の集落資料から「優勢炉を持つ住居と劣勢炉を持つ住居が対をなして存在する現象」を抽出する肝心の三上の作業は有効性に乏しく、かれのいう「より客観的な実証的裏付け」からは率直にいって程遠い状態にある。
本論文で三上が群別作業を実施した集落は中部・関東地方の七遺跡に及ぶ。いずれも中期前半期の資料であり、そのすべてについて「等質ではない二棟が一対をなす」例が確認できたと三上はのべている。しかし、同時期の複数の住居群の中から優勢炉と劣勢炉を伴う特定の二軒の住居を結びつけるかれの根拠は結局のところ主観的・視覚的であり、中には滑坂遺跡や爼原遺跡のように、一対と認定された二軒が他の住居、時には中央の広場を挟んで四〇〜六〇mも離れて分布するという奇妙な例さえ少なからず認められる(図14)。�「優勢住居では調理と共に家族が食事を共にした」という三上の論理が正しいとすれば、径一〇〇m前後の集落の内部で、何故、一つの家族が、これほどの距離を隔てて別々に住まわなければならないのか。きわめて不可解というほかはない。
もちろん、三上が男女分棟の根拠として取り上げる民族誌の中には、タンザニア・マンゴーラ村のダトーガ族のように男の家(フーランダ)と女の家(ゴーリダ)が分離して営まれる例は確かに存在する。しかし、その場合でも、二つの家の間の距離は二〇mほどである。しかも両者はボーマと呼ばれる垣根によって区画された共通の屋敷地内に構築されていたのであり、滑坂や爼原例との同一視はまったく困難である。(239)
空間の恣意的な分割と単なる数字合わせ的な作業の一人歩きに終わることの多かったこれまでの群別作業の問題点は、三上においても依然として未解決である。すなわち、丹羽と並んで水野集落論の新しい展開を模索することになった三上の新しい群別作業は、従来の“面の群別”にかわり、“線の群別”にもとづく新しい形の矛盾を縄文時代集落論へともたらすことになったのである。 群別作業の終わりなき分裂と混迷の歴史にもかかわらず、群別作業者は、何故、かくも強く水野の二棟一単位という命題にとらわれつづけなければならないのか。 群別作業を軸として縄文時代集落論そのものをこれほどまでに「呪縛」する水野集落論の「衝撃」と「魅力」の実体とは、一体、何であったのか。
群別作業誕生の舞台となった与助尾根集落に今一度立ち戻った上での水野集落論、とりわけ水野の“二棟一家族論”そのものに対するより広い視野からの再検証作業が必要であったといわなければならない。
3 呪縛される縄文時代集落論
一九八四年刊行の『縄文文化の研究』第一〇巻において縄文時代研究史のまとめを行った岡本勇は、“想念”の集落論、水野正好の集落論を評して次のようにのべている。「水野正好は、縄文時代集落の問題について大胆な考えを提示され、少なからぬ反響を呼んだ。・・・しかし、この水野の考えは、いわば発掘された遺跡をめぐる1つの解釈であり、問題を実践的に解決しようとした所論ではない。この考えに対していくつかの批判が寄せられたが、その批判の前に水野説はやがて影を薄めていったことは確かである�」。(240)
水野集落論の影響は、しかし、岡本が批評するようには決して遠い過去のものではない。
水野集落論を「縄文時代集落論の新しい出発点を画するものとして高く評価」しつづける戸沢充則は、一九八八年の『縄文集落研究の「原点」』の中で、水野論が抱える問題を「たしかに事実の誤認があったり、結論をあまりにも図式的に整理しすぎたりして、実証性を最大の美徳とする研究者から、一時はげしい批判を受けたこともある」という言葉とともに片付けている。(241)
コンピュータ考古学による縄文時代の復元を目指す小山修三も一九八四年の啓蒙書で水野集落論を縄文時代集落論の代表例として紹介し、当該期の家族は一〜三軒の住居を分有していた可能性が大きいことを指摘している(242)。また、一九九三年の『岩波講座日本通史』第二巻の『狩猟採集時代の生活と心性』でも小山は水野の与助尾根遺跡の分析を取り上げ、向坂鋼二の高根木戸遺跡の分析とあわせて縄文集落の説明を行っている。(243)
さらに戸沢らより若い世代に属する丹羽佑一と三上徹也の二人も、既成の群別作業の見直しを唱える言葉の一方で水野の“三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論”を積極的に援用し、二棟一単位からなる住居群の性格付けの根拠を二棟の一が宗教的遺構・遺物を伴うとした水野の与助尾根遺跡の分析結果に求めるという大きな矛盾を演じている。(244)
和島集落論と並ぶ総合的・体系的な集落論として位置づけられる水野集落論に対するごく一般的な次元からの批判・批評は、その是非にかかわらず、ほとんど無意味である。水野集落論、とりわけ与助尾根の中期後半期集落の歴史的な分析にはじまる水野の“二棟一家族論”は、その有効性・蓋然性を問う数多くの批判を乗り越えてすぐれて現在的なテーマとして存在している。むしろその「衝撃」と「魅力」は、「与助尾根という個別遺跡での過ち」(245)を認める新しい研究者をも含めて群別作業全体を強く「呪縛」しつづけていたのであり、かかる特異なパラドックスを解き明かす点にこそ、水野の与助尾根集落論批判を試みる大きな意義と目的の一つがあったことはすでに明らかな通りである。
それでは、水野集落論を支えるこのような独特の「呪縛」の構造は、一体、どのようにして形成されることになったのであろうか。すなわち、与助尾根集落論の登場を促すことになった時代的な背景や研究の土壌をも視野に入れた包括的・多面的な分析視点の確立が求められる理由であり、以上の作業をあいまいにする限り、水野集落論の全体的な相貌、何よりもその光と影の二つをうきぼりにすることはついに困難なのである。 さて、“二棟一家族論”および“三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論”�、“集落の分割構造論”などに代表される水野の一連の集落分析作業の概要についてはすでに第?V・第?W章に詳しいが、一方、以上の作業が抱える問題点については、井上裕弘・堀越正行・小田野哲憲・鎌田俊昭・鶴丸俊明・長崎元広・安藤洋一らのふれいく同人(246)、塚田光(247)、後藤和民(248)、それに佐々木(249)などによる批判がこれまでに試みられている。「実証性」にもまして「論理性」を大きな「美徳とする研究者」がむしろ中心であり、作業年代も一九六〇〜一九七〇年代を中心にごく最近のものまで多岐にわたっている。(250)
内容的には水野の資料操作や解釈の恣意性をもとに水野集落論、とりわけ一九六三年と一九六九年の水野の与助尾根集落分析作業の客観性・蓋然性を問題にしたものが大半であり、水野が本集落の時期区分の根拠として取り上げていた炉縁石の有無は必ずしも住居の動きとは一致しないこと、報告者の宮坂英弌が埋甕炉や住居形態のあり方から中期初頭の可能性を指摘していた西群の二号住居の問題が水野論ではまったく考慮されていないこと、同じく二号住居と北東の一号住居との重複関係が宮坂の報告とは正反対にとらえられていたこと、東群の六号住居に出土報告のない土偶の分布が想定されていたことなどに疑問が寄せられている。
とりわけ多くの批判が集中していたのが、与助尾根遺跡を前・後期に二分する水野の土器型式によらない「集落復原」と、土器型式にもとづく集落分析との間にみられる大きな時間のズレである。
いわゆる“井戸尻編年”の存在にも知られるように、八ヶ岳を中心とする中部山岳地帯の中期土器編年の整備は、一九六五年の長野県富士見町所在の井戸尻遺跡群の報告書の刊行を契機として飛躍的に進行する(251)。与助尾根遺跡の報告書が提出された一九五七年当時は当該期を含めた細かな土器編年はなお未整備の状態にあり、報告者の宮坂は、土器型式に加えて住居や炉址の形態、付属施設のあり方などをもとに中期初頭の可能性のある二号住居を除いたすべての住居を中期終末期に位置づけ、全体として本遺跡をほぼ三段階に区分する考えを明らかにしている(252)。この宮坂の呈示した炉縁石の有無や住居の重複関係を手がかりとする時期区分を援用し、与助尾根の二八軒の住居すべてを中期後半期の前後する二時期の所産とする集落編年案(図15右)を示すことになったのが水野であり、特に与助尾根後期とした二・四・六・七・八・一二・一三・一五・一九・二二・二六・二八号の一二軒の住居の分析をもとに集落全体(二大群一二軒)―大群(三小群六軒)―小群(二軒一単位)という水野の画期的な集落分割案が導かれることになった経緯は改めてのべるまでもない。(253)
しかし、報告書に掲載された不十分な土器資料に対するその後のふれいく同人や佐々木の検討作業(254)によれば、宮坂が三段階説、水野が二段階説を唱えた与助尾根の集落は、実は中期初頭、塚田のいう平出第3類Aに
はじまり、中期後半期の曽利?U、?V、?W期に至るまで少なくとも四段階への細分が可能であったことが明らかになっており、このことは報告書未掲載土器資料を含めた
本集落の見直し作業が行われた一九八六年刊行の『茅野市史』によっても再確認されている。(255)
佐々木の作業を例にとれば、中期初頭=二号、曽利?U期=一・五・六・七・八・一一・一四・一六・一七号、曽利?V期=一二・一五号、曽利?W期=三・四号、時期不明=九・一〇・一三・一八〜二八号というのが以上のおおよその内訳(256)であり、時期不明なものを除けば、与助尾根前期に一括された一六軒の住居中、五軒は曽利?U期、一軒は曽利?W期に、同じく与助尾根後期に一括された一二軒の住居中、一軒は中期初頭、三軒は曽利?U期、二軒は曽利?V期、そして一軒は曽利?W期に属していた可能性をそれぞれ指摘することができる。(図15左)
すなわち、水野の呈示する前・後期あわせて一二単位の「小群」中、同時期に属する、しかも重複関係にない住居の併存現象が辛うじて確認されるのはA小群の一四・一六号、a'小群の七・一七号、b'小群の八・一一号の、いずれも曽利?U期に伴う各二軒にすぎない。しかも、水野の群別作業では、これらの対応する各二軒の住居は、ともに前期に分類されていたA小群の一四・一六号を除いてすべて前後する時間的位置を与えられていたのであり、さらに六小群がそれぞれ分掌するとされた石柱・石棒・土偶の各祭式も、曽利?U期=石柱・土偶の二例、曽利?V期=石柱の一例、曽利?W期=石棒の一例、不明=石棒の一例というように、中期後半の三つの時期に「分嘗」ならぬ分割されてしまうことが知られるのである。二大群隣接・二集落隣接のいずれにかかわらず、一体、どのような詭弁を弄すれば、数十年から数百年という時間幅をもつ二八軒の住居群の、しかも同時存在を前提とした分析作業は成立するのであろうか。
本町田遺跡や高根木戸遺跡の分析に象徴的にあらわれていた群別作業をめぐる数々の矛盾・問題点は、まさしくその出発点としてある水野の与助尾根集落分析作業そのものの中に、すでにその原型の多くをはらんでいたことが改めて確認されるのである。(257)
4 虚構の中の与助尾根集落論
水野の与助尾根集落論は、さらに以上の諸点以外にも、これまでほとんど注意されたことのないいくつかの重要な誤りを含んでいたことを付け加えなければならない。
その一つは戦後の五次にわたる正式調査以前に発掘された石囲炉の問題である。
前号でものべたように、与助尾根遺跡の発見は戦前の一九三五年五月にまでさかのぼる。その端緒となったのが東嶽第四七三四番第三〇八四号に所在する原野から出土した一基の石囲炉であり、開墾を手伝いながら当該炉址の調査にあたった宮坂は、「この炉址を中心とする竪穴住居址がある筈であるが、当時私にその知識がなかったので、石囲炉発掘のみで終ってしまった」ことを報告書の中に明記している(258)。土地所有者の反対もあり、本地点約二五二坪については現在に至るまで正式調査は実施されないままになっているが、炉の形態や面積、五号と二二号住居にはさまれるという立地条件などを勘案するならば、この付近には数軒の、それもおそらくは中期後半期に属する住居群が分布していた蓋然性はきわめて高いとみるのが妥当であろう。(図16)
ところが、水野の与助尾根遺跡に関するこれまでの分析作業の中には、以上の可能性はおろか、一九三五年の石囲炉出土の事実に触れた記述は何故か一切みあたらない。それは水野が呈示する与助尾根集落全体図の場合でも同様であり、石囲炉出土地点にあたる西群中央のB・C小群にはさまれた区域は、二八軒の密集分布する住居群の中で、まるでそこだけがぽっかりと穴が空いたような奇妙な空白域を二五m近くにわたって形づくっているのである(図15右)。一体、宮坂の発見した石囲炉はどこに消えてしまったのであろうか。きわめて不可解というほかはない。(259)
もう一つは与助尾根遺跡が占地する台地北斜面に広がる“無遺構区”の問題である。
与助尾根遺跡の住居群は尖石遺跡に北接する東西に長い舌状台地の南斜面に一五〇m前後にわたって帯状ないしゆるやかな弧状に分布しており、全体としてほぼ環状の構成を示す尖石の住居群とは対照的な様相をみせている。水野の分析作業は、もちろん、南斜面に残された二八軒が本遺跡に残されたすべての住居群にあたるという前提に立脚した上で進められており、勅使河原彰も、先の『茅野市史』の中で、与助尾根遺跡に「日本における最初の原始集落の全掘」例という輝かしい学史的評価を与えている�。(260)
しかし、一九五七年の報告書『尖石』によれば、台地北斜面に対する発掘は一九四九年の東嶽第四七三四番第一三四号付近を対象としたごく限定的なトレンチ調査例(図16)があるだけであり、報告者の宮坂自身も「与助尾根にては充分の発掘調査をなし得なかった」ことをはっきりと認めている(261)。さらに宮坂の学友ともいえる藤森栄一も、「与助尾根は、いな南傾斜面の発掘のみで・・・馬蹄形又は環状集落を形成するか、又はその弧状のみの集落かはわかっていない」という記述を一九六六年の論文に残している(262)。勅使河原、そしてもちろん水野は、与助尾根集落のもっとも基本的な構成にかかわる宮坂らの証言を、一体、どのように受けとめていたのであろうか。
先の石囲炉例を引き合いに出すまでもなく、与助尾根遺跡が「日本における最初の原始集落の全掘」例であったという“定説”は、調査当事者も預かり知らないところで作り出された水野らのまったくの“創作”でしかない。与助尾根遺跡は、なお未完掘の、しかも中期初頭から中期終末期近くまで少なくとも四段階に区分が可能な集落例として存在していたのであり、実際に全面発掘が実施された場合の本遺跡は、従来とは異なる集落像、従来とは異なる集落分析結果、したがって従来とは異なる与助尾根集落論を縄文時代の研究にもたらす可能性を確実に秘めていたことが注意されるのである。(263)
すなわち、誤解を恐れずにいえば、水野がこれまで様々な分析を加えてきた与助尾根集落は、人為的に改竄された畸形的な集落であり、しかもその畸形は、東西の径一五〇mほどの集落を三〇年以上にもわたって二倍の三〇〇mの規模に拡大したままであるように、水野自身の与助尾根集落復元図(図15右)から水野論を紹介した多くの与助尾根遺跡関連図(図17)に至るまで、きわめて広範囲に及んでいる(264)。水野論の誤りは構造的かつ本質的であり、単なる「事実の誤認」という域をすでに大きく超えている。不完全な集落を対象とした、不完全なデータにもとづく、不完全な分析作業は、その根本から速やかに修正されるべきであり、それでもなお具体的な論拠を示さないまま、水野論を一方的に正当化する声が日本考古学の中にあるとすれば、それはもはや科学ではなく、宗教である。
すなわち、水野の“二棟一家族論”、とりわけ与助尾根集落資料を唯一の手がかりとした水野の“三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論”の破産はあまりにも明白であり、ただそれは、水野の与助尾根集落分析作業を聖域化しようとする研究者の“想念”の中でのみ、その歪んだ生を享受していたのである。新しい群別作業は新しい与助尾根集落論からはじめられるべきであろう。(265)
5 変貌する水野集落論―双分・三分組織と通婚圏
水野正好の与助尾根集落論の歴史的・資料的な破綻にもまして大きな矛盾をうかびあがらせていたのが“二棟一家族論”の内容と論理的な構成にかかわる問題である。
一九六三年の最初の試論で呈示されることになった集落―大群―小群と部族―家族―小家族という与助尾根集落論の基本的な骨格を構成する重層的な枠組みが、その後のほぼ一〇年間のうちに外形、内容とも大きな変更を余儀なくされる運命にあったことは先にも指摘した通りであり、「集落―部族」という組み合わせは一九六九年の論文では「圏―部族」に取って変わられ、さらに「大群―家族」という組み合わせは、与助尾根遺跡そのものの二大群隣接例から二集落隣接例への変更とともに、一九七四年の論文中よりその姿をまったく消し去っている。
水野によるこうした内容変更の試みは、前二者ほどではないにしても、“二棟一家族論”の基礎としてある「小群―小家族」の場合にも認められた。(単婚?)小家族もしくは性別ないし機能集団という一九六三年の「小群」の説明に対する、「一棟に家長夫妻と幼児、他の一棟に家長と出自を同じくする男子や子どもが居住していた」(266)という一九六九年の記述、同じく「恐らく二棟のうち一棟は戸主棟であり、一棟は兄弟などの主とする棟」(267)であるという一九七四年の記述がそれであり、明らかに当初の小家族という範疇を逸脱した二軒を分有する一家族の構成員に、後者の論文では一〇人前後という具体的な数字も与えられている。
以上の変更の理由や根拠を水野は一切明らかにしていないが、与助尾根集落論をめぐって認められる上記の矛盾・破綻は、もちろん、この種の変更・修正の如何にかかわらず、動かしがたい事実として存在しており、むしろ水野の“二棟一家族論”の蓋然性に対しては、与助尾根集落の歴史的な評価とはまた別の面からもさらにいくつかの疑問点を指摘することができる。
第一点は、三上徹也の男女分棟論の項でも触れたことでもあるが、先の姥山例をはじめとして、これまでに発見された住居内遺棄人骨資料の中には、水野が想定するような家族の住み分けを示唆する資料はまったくみあたらないことであり、その矛盾は、三上の「調理により積極的に携わった人の家」(268)という新しい視点の導入によっても決して解消されることはなかったという事実である。
第二点は、水野自身よりも最近の群別作業者に特に注意を促したいことであるが、これまでの群別作業はいずれも分析の対象が竪穴住居にのみ偏り、近年とみにその性格が注目されつつある方形柱穴列資料など、“非竪穴系の建物”に居住した可能性のある人間に対する視点がまったく欠落していた事実である。(269)
第三点は、二棟を一単位とするきわめて特徴的とも特異ともいえる居住様式と構成とをもった家族形態が、歴史的発展段階を異にする早期から少なくとも後期までの長期間にわたってつねに主体的な存在としてありつづけたという水野の指摘はいかにも現実性に欠けていることであり、しかもこうした考えが、背景となる各時代・各地域の歴史的・社会的条件に対する検討をまったく捨象したまま、唐突に導かれていたことである。(270)
そして第四点は、以上の独特の家族形態を支える社会的な基盤として水野が想定する当該期の婚姻関係の成立が、“二棟一家族論”同様、歴史的にも、そしてまた論理的にも、非常に危うい状態にあったことである。
「大群―家族」概念の消滅と与助尾根遺跡そのものの二集落隣接例への変更にも明らかなように、与助尾根および高根木戸・貝の花の各遺跡の分析にもとづく水野の一九七四年の双分組織論・三分組織論の提起は、かれの与助尾根集落論総体にとってもきわめて重要な位置を占めている。すなわち、与助尾根遺跡をはじめとする縄文時代の集落はその内部に複数の外婚集団を包摂しており、当該期の婚姻関係は、したがってかかる集団を基本単位に同一集落、もしくはせいぜい二〜三集落間というごく限られた範囲内で取り結ばれていたというのが水野の一連の作業から導かれる双分・三分組織論の概要であり、二棟を分有する一家族の歴史的な性格を父系的な外婚集団との関連でより鮮明なものとすることになったこうした独特の親族組織論は、その八年後に提起される丹羽佑一のカリエラ体系の中にもその衝撃の余波をとどめていたことは改めてのべるまでもない。
しかし、本来、双分組織や三分組織、それに四分組織と呼ばれる社会組織は、婚姻から経済的な交換、社会、儀礼の各分野を包括した互酬的な構造の全体系としてとらえられるものであり、水野らが想定する父系的な外婚集団を媒介とした女性の交換は、こうした体系の中の重要ではあるが、あくまでも一つの構成要素として存在しているにすぎない(271)。仮に縄文時代の集落の分析から何らかの分割構造を導くことができたとしても、それらをすぐれて親族的な原理としての双分、三分あるいは四分制といった問題へと昇華することができるかどうかは、より高次の検討を必要とする別個の課題なのであり、しかもこうした親族組織が実際に機能するためには、それに見合った十二分な人口の確保が不可欠であったことはすでにカリエラ体系をめぐって指摘している。与助尾根を例にとれば集落構成員わずか三〇人ほどの、しかもたかだか二〜三集落という小舞台で生存を許されることになった水野の双分・三分組織論はまさしく畸形的であり、ミニアチュア的であったといっても誤りではない。
すなわち、縄文時代のごく限られた集落のまとまりの中で双分・三分・四分組織といった特徴的な親族組織が形成され、しかもその枠内において円滑な婚姻関係が長期にわたって維持されつづけたという水野らの考えはあまりにも非現実的であり、“二棟一家族論”と共通する集落の恣意的な空間分割から導かれた、いわば想念の家族論に対する想念の親族論を縄文時代集落論の中に形づくるものであったことはこれまでにも批判を繰り返している通りである。むしろこの時代の集落規模の下で、なおかつ婚姻適齢期にある男女の絶対数の不足という矛盾を解決するためには、当該期の集落は、不可避的に水野らの枠組みを大きく超えた広域的な親族・婚姻システムをとらざるをえないのであり、とりわけ土器分布圏の外縁部の場合には、こうした広域的なシステムは、いわゆる在地埋甕と異系統埋甕の共存現象にもみられるように、土器型式を異にする他地域の集落をも包摂した重層的な構造を示すまでに高められていたことに注意しなければならない。(272)
死亡した幼児の葬送にあたって埋設土器の選定にもっとも大きな影を落とすことになったのは、その生誕から再生に深くあずかる立場にあった幼児の母親の集落内における社会的位置であり、それは幼児の母親と密接なかかわりをもつ土器、いいかえれば母親の出自系統を象徴する土器を意識的に土器棺へと転用するという形を通して埋甕儀礼全般を広く規制することになった。(273)
女性原理としての妊娠呪術を基盤においた異系統埋甕論の詳しい内容については省略するが、特に与助尾根遺跡が所在する八ヶ岳西麓地域と海戸遺跡が所在する諏訪湖盆の両地域は、同じく中期後半期の神奈川県地域と並んで以上の現象が典型的に認められるエリアとしても知られている。与助尾根、与助尾根南、尖石の各遺跡では唐草文系土器の出土(図16)が確認されただけで異系統埋甕そのものの分布は現在までのところ不明であるが、茅野市よせの台、棚畑(274)などの諸遺跡からは諏訪湖盆や松本平・伊那谷に分布の中心をもつ唐草文系土器を使用した異系統埋甕が、また岡谷市海戸、花上寺遺跡(275)などからは逆に曽利式土器を使用した異系統埋甕が検出され、土器分布圏を接した両地域の集落では、土器の系統を異にする他地域の女性をも自らの構成員として迎え入れていた可能性をそれぞれうきぼりにしている。両地域をめぐって従来から指摘されてきた活発な相互交流の中には、明らかに地域を超えた通婚関係という問題が含まれていたといってよい。
もちろん、たとえこのような現象が指摘されるとしても、一集落内部における婚入者の主体はあくまでも同一の土器分布圏内の女性によって占められていたとみるのが妥当であり、既婚女性全体に占める他地域の女性の割合は、異系統埋甕の分布率を手がかりとする限り、ほぼ一割から最大でも三割前後にとどまっている。しかも、八ヶ岳南麓や山梨県地域では唐草文系土器を使用した異系統埋甕の分布が一部の例を除いて不明瞭になることにもみられるように、この問題は、各集落・各小地域を取り巻く地理的・歴史的条件や当該土器分布圏そのものの広狭・強弱、何よりも中心部と外縁部の差異などによって決して一律にはとらえきれない様相を示している。さらに埋甕を分析の対象とする限り、一方における男性婚入者の問題ははじめから捨象されてしまう恐れがあったことは否めない(276)。しかし、以上の制約を認めたとしても、この時代の通婚関係が遠近の集落を包摂した地域内・地域間という重層的な構造を獲得することになった意義は大きく、その背景には、前述した婚姻適齢者の絶対数の不足という問題に加え、交易や通婚といった地域を超えた各種の交流が当該集落の存続・発展にとっての不可欠の要件を占めるまでに至ったという歴史的な事情が存在していたことは確かであろう。
土器型式の分布と通婚や「胞族」�、�「部族」との関係については先にも和島誠一や山内清男、塚田光などの意見を紹介しているが、通婚圏をあくまでも共通する土器型式の広がりの枠内でとらえようとしてきた従来の通説は率直にいって一面的であり、むしろ、より広範な視野に立脚したそれらの再検証作業の中にこそ、土器分布圏の時空的な変化のメカニズムとも一体となった当該期の親族さらには部族関係の実態解明へと至る水路は、いずれその一端を垣間みせることになるものと考える。(277)
「恐らく村人はこの群内のテリトリーで一生を送り、歴史の流れも地上の変化も全てその領域内に生起したものと思われる」(278)。一九六九年の論文の終わり近くで、水野は、以上のようなきわめて固定的かつ閉鎖的ともいえる独特の領域―通婚観を披瀝している。縄文時代の集落と人々をいたずらに限られた世界の中に閉じこめ、その誕生から死もしくは離村に至るまで、かれらに等しく規格化された一生を演じさせることになったのは、他ならぬ縄文時代の研究者の側であった。(279)
6 崩壊する水野集落論―拡大家族と訪妻婚
ところが、水野正好のこのような“二棟一家族論”、およびそれらと一体のものとして呈示されることになったかれの親族―婚姻論は、双分・三分組織論の歴史的な提出の九年後の論文においてさらに決定的ともいえる大きな変貌をとげることは、何故かほとんど注意されていない。『歴史公論』掲載の一九八三年の論文、『縄文社会の構造とその理念』である。(280)
題名にもある通り、縄文時代の集落に関する水野の最後の体系的な作業ともなった本論文の内容は従前にもまして観念的であり、中央広場や住居群の配列、集落の型などからうかがわれる各種の共同規制を�「集落法」、祭式の分掌や抜歯などからうかがわれる男と女、戸主夫妻と他の家族員、成人と未成人とを厳然と隔てる格差を�「家族法」、男女の労働分担や集落のテリトリーなどからうかがわれる強い境界の論理を�「日常法」という言葉でそれぞれとらえ直すことになった水野は、その上で、縄文社会の構造と理念の解明を後続する社会、環溝・環濠をはじめとする多様な「溝」と「政治的規範力」で特徴づけられる弥生社会との対比において試みている。以上の詳細や是非についてはここでは触れることはしないが、現在の問題との関連においてとりわけ看過できないのが「家族法」の中の次の記述である。
水野は書いている。「二棟の竪穴住居を一家族とみなすばあい、一棟はこのような戸主夫妻を中核とする家族員が、のこる一棟には戸主の父母・兄弟姉妹といった家族員が居住することと理解してよいであろう。この兄弟は他集落に住む妻子のもとにおもむき、姉妹は他集落に居住する夫を迎える形で同居せぬ型の家族を構成しているかと考えられるのである。�」
すなわち、本論文において「縄文法」の一環をなすものとして「家族法」という概念を設定し、以上とのかかわりあいにおいて「縄文家族の構造」に言及することになった水野は、ここで改めてかれの“二棟一家族論”の正当性を主張するとともに、二軒の住居を分有する一家族は一〇人前後で構成されること、各構成員は住居内にそれぞれの定められた座をもつことなど、これまでの論旨に沿った指摘を繰り返している。しかし、肝心の一家族の中味はといえば、戸主夫妻と同居する「戸主の父母」は以前にはまったく知られていなかったものであり、「兄弟姉妹」のうちの「姉妹」も今回がはじめての登場である。しかも従来の論文では、戸主夫妻を除けば、家族構成員の中には既婚者は一切含まれていなかったのである。そうした家族論をも同じく“二棟一家族論”という枠内でとらえることが妥当であるのかどうか。率直にいって大きな疑問が残るといわなければならない。
すなわち、水野がここで描いている、親子・兄弟という血縁的な紐帯で結ばれた複数の核家族の集合体は、いうまでもなくG・P・マードックの分類による“拡大家族”の範疇に入れられるものであり、一夫多妻あるいは一妻多夫にもとづく“複婚家族”とともにいわゆる“複合家族”の一つに位置づけられる(281)。当初の小家族とはもちろん、一九六九年、一九七四年の論文にみられる大家族的な構成と比べても、その間の差異は単なる数的な次元を超えてまさしく質的であり、“二棟一家族”という外皮を除けば、水野の家族論はその内容をまったく一変させていたといっても誤りではない。
しかし、水野の集落研究を批判する者、肯定する者のいずれも、水野の家族論が年を追ってこのように大きく変質・変身していることにほとんど無関心、もしくは無知であることは奇妙かつ滑稽であり、縄文時代集落論をめぐる緊張感の弛緩と混乱に一層の拍車をかけている。
宮下健司は一九九四年の『考古学研究』第四一巻一号掲載の『教科書に登場する遺跡 尖石遺跡』の中で水野の与助尾根分析に触れ、「与助尾根遺跡における南北の2群(東西の誤りであろう―筆者註)に分かれた各群は2棟1組の3つの小群に分別され、それが部族、家族、小家族という集団に対応」することが水野によって解明されることによって「日本の縄文集落研究が体系化される」ことになったとのべている(282)。すでに明らかなように、宮下が紹介しているのは水野の一九六三年の与助尾根集落論―“二棟一家族論”の亡霊であり、もっとも多くの研究者のイメージの中にある水野の与助尾根集落論は、他ならぬ水野自身の手によってすでにその密やかな死を強いられていたのである。
ところが、本論文でさらに驚かされるのは親族―婚姻論に関する水野の次の言葉であり、従来のきわめて閉鎖的・排他的な領域―通婚観を手直しした、ほとんど別種といってもよい見解を、水野はあたかも当初からの一貫した主張であるかのようにのべている。「こうした明確な領域の意識が指摘できるなかで、時に領域を超越する諸事象がみられるのである。たとえば婚姻がそれである。婚姻が一集落内で賄いえぬことは、二棟三単位計三〇人ほどの集落規模からみて、ただちに察知しうるところである。したがって領域を超えた他地に配偶者をもとめることとなり、男性がおりおりに妻を訪ねる婚姻型態が普遍化しているようである」という「日常法」の一節がそれであり、同様の指摘は、先の「兄弟は他集落に住む妻子のもとにおもむき、姉妹は他集落に居住する夫を迎える形で同居せぬ型の家族を構成している」という「家族法」の記述の中にも認められる。一体、これほど自己矛盾に満ち満ちた論文を、残念ながら佐々木は知らない。
前節での説明にもある通り、「婚姻が一集落内で賄いえぬこと」こそは、双分、三分、四分制の原理的な理解とあわせて、佐々木が水野や丹羽たちの親族・婚姻論に対して批判を繰り返してきたもっとも重要な問題点であったことはまさしく多言を要さないところである。水野がいうように、本当にそれが「ただちに察知しうる」はずのものであったとするならば、そうしたごく常識的な親族・婚姻論を提出するだけのために、水野は、何故、二〇年もの長い歳月を費やさなければならなかったのか。�「男性がおりおりに妻を訪ねる婚姻型態」は、いつ、どこで、どのような形で論証されたと水野はいうのか。こうした“訪妻婚”に対し、いわば「同居する型の家族」を構成する「戸主夫妻」にみられる「婚姻型態」は、従来の通り、夫方居住婚にあるものとして理解することが可能であるのか。「戸主の父母」と同居していたはずの、かれの、あるいはかの女の年老いた「兄弟姉妹」は、はたしてどこで余生を送ることになるのか。そもそも水野が与助尾根や高根木戸、貝の花などを舞台に提起することになったあの特異な双分・三分組織論は、一体、どこへ消え去ってしまったのか。そして何よりも、水野が想定する特徴的な拡大家族が縄文社会に出現するに至った歴史的な必然性や背景とは、一体、何であったのか。
すなわち、水野の一九八三年の論文の中には、水野による親族―婚姻論の突然の変更の理由はもちろんのこと、それらがもたらすことになった新たな疑問点・矛盾点に対する具体的かつ真摯な説明は、先の“二棟一家族論”の場合と同様、まったくみあたらない。これまでの議論の経緯、とりわけ自らに向けられた数多くの批判に一方的に目を閉ざしたなし崩し的な議論の進め方はまさしく不誠実であり、もはやそこには、現代から未来に連なる主体の確立を主張し、「民主主義の旗頭新体制の歴史学と期待された」(283)日本考古学の保守的体質に鋭い問いを投げかけることになった、かつての実践的批判と自己変革の精神にあふれた水野集落論の面影は認められないのである。水野集落論は、その内面奧深くからも着実に崩壊を進めつつあったということができるだろう。
水野集落論にとっては、しかし、“想念”に頼ったかれの双分・三分組織論と“二棟一家族論”の論理・実証両面にわたるほころびを取り繕うためのこうした変更劇の数々は、同時に、もう一つの集落論、縄文時代に後続するもう一つの集落論の歩みとも不可分のものとして実は存在していたのである。
VII 水野集落論と都出比呂志のネオ単位集団論
1 水野の与助尾根集落論と西日本
水野集落論の形成とその性格をめぐっては、水野正好の分析作業にみられる民族学的・人類学的色彩の濃さを指摘する声が従来より強い。長崎元広はすでに一九八〇年の『縄文集落研究の系譜と展望』(284)の中でこの点への注意を喚起しており、都出比呂志も、水野の親族論に関連して「水野の立論は豊富な民族誌の知識に裏づけられたものと考えられるが、論証の手続きにおいて一切それを使用しなかった」と一九八九年の『日本農耕社会の成立過程』に書いている。(285)
しかし、こうした傾向が水野集落論の中に強く看取されるようになるのは、厳密には「住居の間取り」論が呈示される一九六九年から一九七四年の双分・三分組織論提出の前後の時期というべきである。水野集落論の背後に一貫して認められるのは弥生時代の集落論、弥生時代の家族論の強い影であり、その影は、水野自身の意識のありようにかかわらず、今日へと連なっていることに注意しなければならない。
それにもまして、縄文時代研究者の多くは、水野集落論の登場が何よりも弥生時代の家族・集落論との密接な結びつきの下に実現をみることになった点ついてはほとんど無頓着である。
坪井清足は、水野の与助尾根集落分析作業の存在をはじめて明らかにすることになった一九六二年の『縄文文化論』の中で、水野の三小群から構成される「大群」を「血縁的な世帯共同体の一集団」、二大群から構成される「集落」を「氏族集団」という言葉とともに紹介している(286)。坪井の『縄文文化論』は、いうまでもなく近藤義郎の単位集団論の総合的な展開が試みられた『弥生文化論』(287)と対をなす論文として『岩波講座日本歴史』の第一巻を飾っている。水野の縄文集落に関する最初の試論、『縄文式文化期における集落構造と宗教構造』の要旨が、その発表の一年も前に他の研究者、しかも水野とフィールドを同じくする坪井によって紹介されたこと自体、前号でものべたようにきわめて異例であり、水野集落論が形成されることになった西日本を中心とする研究風土、さらにはその学史的背景などを考える上からも象徴的である。
水野集落論、とりわけ水野の与助尾根集落論の形成をめぐっては、かれの本来の研究土壌からいっても、東日本を中心とした縄文時代集落論にもまして西日本を舞台とした弥生時代集落論の強い影響力の介在を考慮するのがもっとも妥当であり、実際的にもかれの集落論の登場を弥生時代の家族・集落研究の成果と重ね合わせる形で受けとめることになったこの時期の研究者は少なくない。坪井の一九六二年の「大群―世帯共同体」と水野の「大群―家族」との厳密な異同は明らかではないが、水野の与助尾根集落の分析を高く評価する戸沢充則は、しかし、一九六八年の海戸遺跡の群別作業に際して、「海戸集落における最小の単位集団」である「群」のいくつかのまとまりを前述したように坪井に倣って「血縁的な世帯共同体」としてとらえている(288)。さらに戸沢は、一九八三年の『長野県史』の海戸遺跡の記述の中でも、以上の「群」に相当する縄文時代の最小単位の集団に「世帯」、弥生時代の三軒一単位の住居のまとまりに「世帯共同体」という呼称をそれぞれ与えている。(289)
ただし、このことは、水野の家族・集落論と和島誠一のいわゆる世帯共同体論との結びつきを意味するものではまったくない。和島にとっては、血縁的な大家族・家父長制大家族の前身をなす世帯共同体は縄文時代における母系的な氏族共同体の分裂の結果、「全体が一つの単位」をなす縄文時代には決して認められることのなかった「新しい小集団」としてようやく弥生時代に登場をみるのであり、縄文社会はあくまでも自然発生的な血縁集団と集団婚の支配した時代にとどまっていたことは第?U・第?W章でも指摘を繰り返してきた通りである(290)。対偶婚は、やはり和島によればようやく弥生時代になって形成されるのであり、消費や一部の生産の面で一定の自立性をもった単婚小家族や拡大家族の出現をすでに縄文時代にさかのぼって想定する水野論との距離は、何よりも二人のもっとも明確に意識するところであったといってよい。
2 単位集団と二棟一家族―沼と与助尾根を結ぶもの
水野の家族・集落論を語る上でとりわけ看過しがたいのは、西日本の弥生時代集落を舞台にした、しかも水野の与助尾根集落論と相前後するように発表されることになった単位集団論との間の強い結びつきである。
前号でも紹介した赤松啓介の発言(291)にもあるように、弥生時代をめぐる和島の「世帯共同体」と近藤義郎の「単位集団」という二つの概念は、呼称の違いを除けば、一九五九年の単位集団論の提起(292)の当初より内容的に近似したあり方を示していたことが注意されており、和島自身もしばしば自らの著作の中で「世帯共同体」と「単位集団」という言葉を併用している。特に一九六四年の『集落と共同体』では、和島は両者の歴史的同質性を認める発言さえ行っている(293)。しかし、ほぼ一貫して世帯共同体論の縄文時代への適用には否定的であった和島に対し、後年の近藤は単位集団論を旧石器時代にまで積極的にさかのぼらせる試み(294)を呈示しており、また、それと前後するように、単位集団論を縄文時代へとさかのぼらせようとする試みも、都出比呂志や菅原正明、後藤直などの弥生時代研究者の手によって実践されている(295)。それらを可能にすることになったのは、いうまでもなく理論先行的な和島の世帯共同体論に対する、“考古学における実証主義”(296)とまで評された近藤の単位集団論を特徴づける明快な図形性とすぐれた「考古学的な追証」(297)性の存在であり、しかも縄文時代の場合、こうした単位集団論の適用は、水野の家族・集落論とのつながりを強く意識した形式をとりつつ、いずれも模索されていたことに留意しなければならない。
とりわけ示唆的であるのが一九七〇年の『農業共同体と首長権』であり、この中で�「農耕へ転換する以前の縄文社会の社会編成についての研究」の好例として水野の与助尾根集落分析作業に「和島誠一の古典的研究」を遥かに上回る高い評価を与えることになった都出は、さらに水野の“二棟一家族論”と近藤の単位集団論という、時代を異にする二つの“集団”論のあり方に言及し、次のようにのべている。「この�「単位集団�」が水野の指摘する縄文時代の�「二棟三単位の小集団�」と同質なものかどうかについては、縄文晩期から弥生前期への移行期の実態が不明なために性急な結論は危険である。しかし、水稲農耕の開始期にこのような小集団が農業経営の基礎単位となったことは疑いない。農業経営の基礎単位と認められるこの小集団は、いくつかの世帯をふくんだ血縁関係の強い集団とも想定されるから、これを、�「世帯共同体」という、原初的家族の古典的概念で把握してよいだろう。」(298)
すなわち、弥生時代研究者、殊に西日本の弥生時代研究者にとっては、水野の家族・集落論は決して遠い過去、遠い地域を舞台とした疎遠な議論として存在していたわけではない。むしろ都出の想定の中にある水野の家族・集落論と弥生時代の家族・集落論の両者は、構造的に一体といってもいいようなきわめて親縁的な関係をあからさまに示していたのであり、それは、本来、水野の与助尾根集落論が単位集団論と同質の研究土壌、同質の研究基盤を有していたと考えるのであれば、少しも意外な事態ではないことが指摘されるのである。
先に岩崎卓也は和島の世帯共同体論の提起に端を発した弥生そして古墳時代をめぐる集落分析作業の概括を試み、�「同時共存と判定された大小の住居址から相接近するものをグルーピングし、それが弥生時代の所産であれば世帯共同体を、また古墳時代後期のものであれば家父長制的大家族を想定しようとするなど、分析の安易さに、自戒の声があがってきたのである」とその問題点を要約している(299)。さらに世帯共同体論の舞台となった登呂遺跡や志村遺跡をめぐる和島の分析作業の誤りについては、同じく佐々木が第?U章で触れている。(300)
しかし、岩崎がここで描いている教条的な群別作業の過熱ぶりは、実はそのまま近藤の単位集団論をめぐる追証作業についてもあてはまる問題であったことはよく知られている通りであり、弥生集落に対する決して客観的とはいいがたい分析から導かれた住居群のまとまりを「単位集団」の枠内においてすべて一律的・短絡的にとらえようとする悪しき傾向が東日本を含めた弥生時代集落論全体を広く覆い、自由な発想にもとづく新しい集落分析作業の形成を妨げる要因として働いていたことは縄文時代の群別作業における水野の“二棟一家族論”の場合と同様である(301)。特に、水野の“二棟一家族論”と近藤の単位集団論の両者が、それぞれの出発点に位置する与助尾根遺跡と岡山県津山市沼遺跡(302)の分析作業の蓋然性をめぐってともに今日に至る大きな疑問点を残していたことはきわめて暗示的かつ皮肉というべきであり、近藤が谷水田の開拓に従事した弥生中期後半の「単位集団」の実例として紹介する本遺跡の住居群は実は論文や研究者によってその数が五〜六軒と一定せず(図4)、それらの同時存在性も発掘調査段階ではほとんど未確認のままであったことを決して忘れてはならない。
しかし、自らは「単位集団」を家族論との関連でとらえることにはきわめて消極的であり、縄文時代における「単位集団」の具体相についてはついに積極的な発言を試みることのなかった近藤(303)に対し、水野の家族・集落論と弥生時代の家族・集落論との不可分な関係をもっとも明瞭かつ完成された形で呈示することになるのが都出比呂志の新しい単位集団論である。
3 世帯共同体あるいは世帯群―二つの拡大家族論
都出比呂志は前出の一九八九年の『日本農耕社会の成立過程』において、東日本の前・中期を中心とする集落では「一般には数棟の竪穴式住居が一つの単位であり、大きい集落の場合には数棟を基礎とする一単位が広場を中心に二単位程度併存していることが多い」とのべ、生産活動や領域占有の単位であるこうした「単婚家族としての小世帯」の「複合体」、すなわち�「世帯共同体�」や�「世帯群�」は、縄文時代に先行する初期の段階から農耕社会に至るまで、人類社会の古い時期のもっとも基礎的な単位をほぼ一貫して形づくってきたというきわめて大胆な仮説を展開している。(304)
さらに一九九四年の『トイレの考古学』と題した座談会では、縄文時代の家族を二〜三軒の住居からなる�「複合家族�」、二〇人ほどで一つにまとまった�「大家族�」としてとらえている。(305)
都出自身は明言を避けているが、かれの縄文時代をめぐる家族・集落観は明らかに水野論との整合性を強く意識したものとして存在しており、さらにその背後には、弥生時代を舞台とした近藤義郎の単位集団論の強い影を容易にみてとることができる。
都出は『日本農耕社会の成立過程』の四四八頁で「水野正好は長野県与助尾根遺跡の縄文時代中期の集落は、二棟を一単位とする三単位を併せた六棟構成の集団二つからなり、二集団は住居構成や祭式においてほぼ同様の構造をもつことを根拠として、これら二つの共存を双分組織を示すものと主張した」と書いている。また同書の二一六頁では、『魏志倭人伝』の「父母、兄弟、臥息処を異にす」の記述をもとに、大型住居を含めた弥生時代の数軒の住居の集合体、つまり近藤のいう「単位集団」の内容を「近親者が世帯別に数棟の住居にそれぞれの幼児とともに住みわける姿」として把握し、これに「世帯共同体」あるいは「世帯複合体」という呼称を与えている。さらにさかのぼれば、一九八四年の『農耕社会の形成』では、都出は弥生時代の「世帯共同体」は「家長世帯を核とし、その兄弟や父母の世帯をあわせた�「複合家族�」である可能性が高い」とものべている。(306)
縄文時代の�「世帯共同体�」に関する都出の一九八九年の説明と水野の与助尾根集落分析との厳密な区別はまったく困難であり、さらに都出の縄文時代の�「複合家族�」―�「大家族�」に関する一九九四年の説明と弥生時代の「単位集団」―「世帯共同体」に関する一九八四・一九八九年の説明も、「一棟はこのような戸主夫妻を中核とする家族員が、のこる一棟には戸主の父母・兄弟姉妹といった家族員が居住する」(307)という水野の一九八三年の拡大家族―複合家族論との際立った類似性をうかびあがらせている。ほとんど唯一の違いは、一〇人と二〇人という構成員数の差であったといっても誤りではない。
すなわち、誤解を恐れずにいえば、人類社会の古い段階の基礎的な単位を考究する都出論の最大の目的は、数軒の住居を分有する拡大家族―複合家族の時代を隔てた存在という姿を通して縄文時代と弥生時代の二つの「世帯共同体」の歴史的な同質性・一体性をうかびあがらせる点にあったことは確実であり、またそのことによって、近藤が不十分な提起で終わらせることになった単位集団論の通時的・普遍的な展開という課題の体系化が都出によって図られていたことは間違いない。
しかし、自らは藤間生大や石母田正らの古代家族論からの考古学的な自立と理論的な孤立を深め、また、「単位集団」を「家族体」(308)という漠然とした理解にとどめることになった近藤の単位集団論に比べると、「単位集団」―「世帯共同体」に関する考古学的な検証作業をマルクスやエンゲルスらの古典的理論の批判とあわせて包括的に押し進めていこうとする都出の試みは同質的であると同時に異質であり、しかも、近藤が「独立または孤立」せず「集合してのみ存在」(309)するとした単位集団を構成する個々の住居の消費生活における一定の自立性を積極的に認めていこうとするところに、都出の単位集団―世帯共同体論の独自性、いわば“ネオ単位集団論”の所以、根拠があったことは明らかである。
都出の“ネオ単位集団論”の新しさは、もちろん和島誠一の世帯共同体論との比較においても指摘できる。
集団婚にもとづく自然発生的な血縁集団から対偶婚にもとづく新しい小集団へ、共同居住と集団労働から個別的居住と個別的労働へ。和島の縄文時代を舞台とした氏族共同体論と弥生時代を舞台とした世帯共同体論の大きな理論的基盤が、藤間・石母田らの古代家族論に加えて、モルガンやエンゲルスらの進化主義的家族観に据えられていたことは繰り返すまでもない。しかし、大きな血縁集団から小さな血縁集団へ、そして小さな地縁集団から大きな地縁集団へというエンゲルスらの歴史的な命題に対し、小世帯の複合体としての小集団と、それらを単位とする相対的に小規模な居住および労働の普遍性を強調する都出の提起の内容はまさしく画期的かつ革新的であり、その正当性を裏付ける前半部の根拠として直接・間接に援用されていたのが水野の与助尾根集落論、水野の縄文時代をめぐる家族・集落論であったことは疑いない。 ただし、その論理は革新的であったとしても、実際の分析作業、とりわけ縄文時代の分析作業における都出の“ネオ単位集団論”は水野のそれにもまして保守的かつ演繹的であり、かれの『日本農耕社会の成立過程』の中には、一九七〇年の『農業共同体と首長権』(310)のように水野の「二棟三単位の小集団」と「単位集団」の同質性を示唆する発言はおろか、かれが当然熟知していたであろう水野の与助尾根集落論の立論上の問題点に言及した部分、何よりも「数棟を基礎とする一単位」の構成、および二単位程度が広場を中心に併存する大型集落のあり方について縄文時代の具体的な資料にもとづくかれ自身の論証が試みられた部分はまったく認められない。
しかし、東日本の、しかも中期を中心とする縄文時代集落研究にとっても大きな空白域として残されている「縄文晩期から弥生前期への移行期の実態」に対し、他ならぬ都出自身が与える歴史的な評価とは、一体、何であるのか。「性急な結論」づけを戒めた一九七〇年のかれ自身の言葉にもあるように、そもそもこのような歴史的転換期が当該期の基本的な集団構成に及ぼすことになった影響を考慮しない縄文・弥生二つの時代の直截的な比較に、一体、どれほどの有効性があると都出はいうのか。それにもまして都出や水野らがフィールドとする西日本の縄文社会は、はたしてどのような集落構成と原理とを東日本の縄文社会に対して示していたというのか。
すなわち、西日本縄文社会の構造は、その全般・全域を通して大半がなお深い闇に閉ざされたままであったことはよく知られている通りであり、何よりも当該地域を舞台とした“与助尾根集落”の発掘、「数棟を基礎とする一単位」の発見は遠い課題である。如上の諸点に対する意識的な取り組みと具体的な解答を回避したまま進められる集落復元作業は、たとえそこにどのような理論的検証作業を介在させようとも反科学的であり、それぞれの時代、それぞれの地域、さらにいえばそれぞれの集落が内包する個別的な問題や不均等発展に対する歴史的な視点をあいまいにしたまま、単位集団論へと収束されることになった西日本の弥生時代の集落構成を先行する各時代、各地域へといたずらに普遍化しようとする“逆発展史観”以外の何物でもない。
それらを許しているものがあるとすれば、それは誤った“西日本中心史観”であり、“弥生時代中心史観”であろう。(311)
水野集落論、とりわけ水野の与助尾根集落論は、かれ自身の意識の如何にかかわらず、西日本の研究者によって東日本を中心とする縄文時代集落研究に打ち込まれた歴史の楔である。
4 ネオ単位集団論と“ゆるやかな単婚家族”
縄文〜弥生時代の社会組織に関するこれまでの研究の理論的総括を独自の視点から試みることになった一九九一年の『縄文時代に階級社会は存在したのか』の中で、小杉康は次のような興味深い見解を明らかにしている。�「社会組織解明に向けての、�「共同体論�」から�「親族組織論�」への新展開のためには、次の点に関しての探求が必要である。本来、�「親族組織論�」とは一線を画する�「共同体論�」ではあるが、新たな分析方法を開発することによって、考古資料として把握することが可能な一定の地理的な広がりをもった仮設的な集団の性格を、親族組織との関係において捉え直すことである。そこで、縄文時代については水野正好の研究に、弥生時代では都出比呂志の研究に、その可能性を見出してゆきたい。�」(312)
かれ自身の高い問題意識とは裏腹に多くの「先入観」と論理的な誤謬で満たされた小杉の理論的検証作業(313)は、しかし、故意であれ偶然であれ、水野論と都出論に対する誤った評価と引き換えに、縄文〜弥生時代の社会組織をめぐる研究のもっとも重要な一側面を確かにいいあてている。いうまでもなくそれは水野の家族・集落論と都出の“ネオ単位集団論”との時代を超えた親縁性であり、構造的な同質性である。
とりわけ両者の相補的・一体的な関係をうかびあがらせていたのが、前節でものべたように水野と都出二人の縄文時代を舞台とした拡大家族―複合家族論と都出の弥生時代を舞台とした単位集団―世帯共同体論との間の際立った類似性であり、西日本という縄文集落の良好なフィールドをもたない都出の革新的な“ネオ単位集団論”は、特にその前半部に関する限り、同じく西日本をフィールドとする水野の与助尾根集落論、“二棟一家族論”の存在があってはじめてその生と根拠を与えられていたといっても過言ではない。否、むしろ単位集団論の普遍性・先行性と水野の“二棟一家族論”をめぐる一連の奇妙な変更劇とを考慮に入れるのであれば、水野の家族・集落論こそは、本来的に縄文時代版単位集団論、いわばミニ単位集団論とでも呼ぶべき存在としてあったとみるのが妥当であり、その大本となる単位集団論、正確には都出の“ネオ単位集団論”の体系化の動きと軌を一にするように、自らもまた、単婚小家族から単婚家族が複合した拡大家族へとその姿を変化させてきたととらえることも決して不可能ではないだろう。(314)
かくしてわれわれは、水野批判に対して繰り返される都出のあいまいな沈黙とあいまいな否定の本来の意味をようやく理解するまでに至る。水野集落論、何よりもかれの“二棟一家族論”は、都出にとっては永遠の生をもった不死鳥でありつづけなければならなかったのである。それは、しかし、歴史的にも論理的にも大きく破産し、わずかに水野の与助尾根集落論を聖域化しようとする群別作業者の“想念”の中でのみ、その歪んだ生を享受していたことは前述した通りである。水野の“二棟一家族論”の死は、すなわち縄文時代を舞台とした都出の拡大家族―複合家族論の死であり、それらを核とした都出の実体なき世帯共同体論、“ネオ単位集団論”の基本構造の瓦解であったことはいうまでもない。(315)
佐々木は、これに対し、縄文時代においても家族形態の基本は一軒の住居を単位とした一夫一婦からなる単婚家族によって占められていた蓋然性はきわめて高く、しかもかかる家族は、住居を単位とした個別的労働とその成果の個別的占有の一定の発展にもみられるように集落内にあって相対的な個別化・自立化とその不均等化を進め、それに伴ってもたらされた集落内外の矛盾・緊張の狭間で激しく揺れ動いていたものと考える。(316)
また、当該家族は夫方居住婚を基本とし、前述した異系統埋甕の分布にも明らかなように、遠近の集落を包摂した地域内・地域間という広域的・重層的な通婚関係を少なくとも中期後半段階には獲得していたものと考える。
しかし、佐々木がここでいう単婚家族は必ずしも一組の夫婦と未婚の子女という小家族的な限定された構成のみを意味するものではない。むしろ、個々の具体的な事例においては、未婚・既婚の別を問わず、兄弟姉妹や両親などが同居することになった可能性についても相応の配慮が加えられるべきであり、こうした、一種の核家族から二つ以上の世代に核家族が連なる拡大家族までをも包括した、いうならば“ゆるやかな単婚家族”こそが、この時代のもっとも一般的な家族像にほかならなかったと結論づけることができる。(317)
拡大家族の無原則的な増殖を阻害する大きな要因があったとすれば、その一つは、縄文人の平均寿命の絶対的な低さであろう。(318)
5 結―侵蝕される縄文時代集落論
全国各地で巨大遺跡・遺構”の新発見が相次ぐ今日、縄文時代集落論は、少なくとも第三者の眼には、かつてない高揚と自己変革の波の中にあるかのようにみえる。
しかし、戦後半世紀にわたって営々と積み重ねられてきた集落研究のこれまでの成果をほとんど顧みることもなく、しかも、検出された膨大な遺構群の時空的な分布や内容に対する十分な検討もなされないまま、二〇m、五〇〇人、一五〇〇年、神官層、縄文都市、縄文文明といったS・Fもどきの野放図な言葉となし崩し的な結論の一人歩きを許容しているたとえば三内丸山遺跡をめぐる“議論”の現状は、率直にいってきわめて無責任であり、そこには地に足の付いた、縄文時代集落論の将来の方向を真摯にみすえた新しい問題提起や提言の類はまったくといってよいほど認められない。
むしろ、そこから垣間みえてくるのは歴史科学としての考古学の集団自殺であり、マスメディアと一体となって垂れ流される恣意的かつ一方的な情報の数々は、この時代を中心とする研究者の主体性と創造性、何よりもその実践的立場に改めて鋭い問いを投げかけている。
その一方、既成の集落研究の根本的な見直しを主張し、三内丸山をめぐる“議論”の輪からはもっとも遠い場所に位置するはずの“横切りの集落研究”(319)やプロセス考古学(320)の側も、伝統的な集落観、あるいは空想的集落観にかわりうる斬新かつ豊饒な縄文社会像については、未だにそれを呈示できないままにある。それぞれの溝は深く大きく、さらにそれらの間には、学史や考古資料・歴史理論の正しい評価と相互批判とを欠如した、論争なき数多くの研究が横たわっている。
新たな世紀へと向かう時代の慌ただしい明滅の中、集落論の停滞・混迷に対する危機意識も日増しにその影を濃くしつつあるが、それらの出口を明示する視点、個々の下向的な分析作業を総合化し、列島史の端緒へと高めていく透徹した理論・方法の在処は現在に至るまで不分明であり、何よりも東日本の縄文集落へと向けられる西日本の弥生研究者の熱く冷静な眼差しとは対照的に、東日本の縄文研究者の眼は自らの閉ざされた集落論をとらえつづけるものの貌へとは決して向けられることはない。
縄文時代集落論、すなわち幻想の中の“独立王国”は、その内と外から、着実に侵蝕されつつあったといわなければならない。(321)
註
(109)佐々木藤雄「水野集落論と弥生時代集落論(上)―侵蝕される縄文時代集落論」『異貌』一四 一九九四
(110)長崎元広「縄文集落研究の系譜と展望」(前掲註32)
(111)和島誠一『原始聚落の構成』(前掲31)
(112)以上の内容については、特に旧稿に詳しい。佐々木藤雄「和島集落論と考古学の新しい流れ―漂流する縄文時代集落論」(前掲註1)
(113)和島誠一・岡本勇「南堀貝塚と原始集落」『横浜市史』一 一九五八
(114)長崎元広「縄文集落研究の系譜と展望」(前掲註32)
(115)和島誠一「序説―農耕・牧畜発生以前の原始共同体」(前掲註37)
(116)和島誠一「原始聚落の構成」(前掲註31)
(117)和島誠一「東アジア農耕社会における二つの型」(前掲註36)
(118)日本考古学協会『登呂 前編』、同『登呂 本編』(前掲註6)
(119)渡部義通ほか『日本歴史教程』一、二 一九三六、一九三七
(120)原秀三郎「日本における科学的原始・古代史研究の成立と展開」(前掲註40)
(121)「全時代にわたって、日本列島とその周辺を舞台に展開した歴史の大きな流れをとらえ、新しい日本史の全体像を打ち立てるとともに、各時代や各地域の特徴的な問題を解明して現代の課題につなげる」ことを謳った一九九三年九月に始まる『岩波講座日本通史』の中には、しかし、列島史の端緒を飾る旧石器や縄文時代を直接対象とした“考古学研究者”による意欲的な論考は一切みあたらない。わずかにそこに認められるのは、アボリジニを中心とする民族誌や民俗学の記録で考古資料の欠を補うとした小山修三の、“第二巻古代1”所収の論説『狩猟採集時代の生活と心性』の一編のみであり、しかも“社会人類学者”の手になる本論考は、後にものべるように時代遅れの、あるいは生半可な考古知識にもとづく恣意的・偏向的な原始社会像で満たされ、まともに批判を加えるのもためらわれるといっても誤りではない。
未消化な考古知識の使用は同巻の通史編を担当した鬼頭清明の『六世紀までの日本列島』でも同様であり、たとえば小山がこの場合は草創期・早期・前期・中期・後期・晩期の六期にわけられるとした縄文時代の時期区分を、鬼頭は早・前・中・後・晩期の五期として紹介している。まさに通史としての統一性の欠如も甚だしく、鬼頭の五期区分の根拠もいわゆる草創期を縄文時代以前とみるためなのかどうか、具体的な説明はどこにもみあたらない。しかも、以上の時期区分を示すものとして掲載された挿図1「土器型式群の分布圏と石器組成の地域圏」も、一九八六年の『岩波講座 日本考古学』五所収の戸沢充則の『縄文時代の地域と文化―八ヶ岳山麓の縄文文化を例に』からの引用であるにもかかわらず、同講座所収の戸沢の『総論―考古学における地域性』からの引用と誤って記されている。“通史”と“日本考古学”という違いはあれ、『岩波講座』同士にみられるこのような基礎的なチエックの誤りはあまりにも安易かつお粗末であり、その科学性や資料的整合性に対する信頼を大きく損なうものといってよい。
責任の一半は、もちろん、列島史としての総合化・体系化への努力を怠ったところでとみに細分化・専門化を進めつつある日本考古学の側にもあったことは確かである。縄文時代、とりわけ当該期の集落研究についていえば、「議論の普遍性と視点の総合性を保証する体系的な理論」に無関心を装ったまま�、今日、その多くが「時代を貫く統括的な課題よりも、時代に沈潜した個別的な課題の探求」へと自らを駆り立てつつあった事情は冒頭でも指摘した通りであり、また、そのことが、現在みられるような縄文時代集落論の停滞と混迷の大きな要因を形づくっていた可能性は、同様にきわめて強いものとしてある。先ずもって試みられるべきは以上の否定的な事実に対する真摯な反省であり、その点を欠如した、いたずらな主体性の主張は、かえって歴史科学としての考古学の創造性を閉ざし、その復権を遠いものとするだけであろう。しかし、たとえそうした問題を差し引いたとしても、今回の『岩波講座日本通史』における旧石器〜縄文時代の記述は、内容・構成・問題意識ともにきわめて不十分であり、特に“通史”の添え物にしかみえないような旧石器社会の扱いは、担当者の選択をも含めて大きな疑問を残している。一体、何をもって、様々な領域で生み出されつつある「創造的な営為を個別の領域にとどまらせることなく、日本史全体の歴史叙述のなかに含みこんで新しい日本史像に結実させ」たと編著者はいうのか。以上に指摘した部分をみる限り、科学的な通史形成に向けての若く清新な模索が試みられた前述の『日本歴史教程』はもとより、芹沢長介『旧石器時代の諸問題』、坪井清足『縄文文化論』�、近藤義郎『弥生文化論』�、小林行雄『古墳文化の形成』と各時代にわたって労作・問題作が揃えられた一九六二年刊行の戦後最初の『岩波講座 日本歴史』に比べても、全体を貫く衝迫力や内面的な緊張感は着実に低下の一途を辿っていたといわざるをえない。鬼頭清明「六世紀までの日本列島―倭国の成立」 小山修三「狩猟採集時代の生活と心性」『岩波講座日本通史』二 一九九三
(122)三澤章「第四章 金属文化の輸入と生産経済の発展」(前掲註29)
(123)三澤章「第一章第二節 古墳文化と考古学」『日本歴史教程』二 一九三七
(124)栗山一夫「播磨加古川流域に築造されたる古墳及び遺物調査報告(一)〜(三)」『人類学雑誌』四九―七〜九 一九三四他
(125)渡部義通「日本原始共産社会の生産及び生産力の発展」『思想』一一〇〜一一二 一九三一 同『日本古代社会』一九三六 禰津正志「原始日本の経済と社会」『歴史学研究』四―四、五 一九三五
(126)赤木清「考古学的遺物と用途の問題」『ひだびと』五―九 一九三七
(127)宮坂英弌「尖石先史聚落址の研究」(前掲註33) 同「八ヶ岳西山麓与助尾根先史聚落の形成についての一考察(上)(下)」(前掲註86) 同『尖石』 (前掲註79)
(128)原秀三郎「日本における科学的原始・古代史研究の成立と展開」(前掲註40)
(129)長崎元広「縄文集落研究の系譜と展望」(前掲註32)
(130)都出比呂志「農業共同体と首長権」『講座日本史』一 一九七〇
(131)水野正好「縄文式文化期における集落構造と宗教構造」(前掲註88)
(132)水野正好「縄文時代集落復原への基礎的操作」(前掲註92)
(133)水野正好「原始社会?@ 縄文の社会」(前掲註96)
(134)水野正好「埴輪芸能論」『古代の日本』二 一九七一
(135)水野正好「祭式・呪術・神話の世界」(前掲註96)
(136)F・エンゲルス、戸原四郎訳『家族・私有財産・国家の起源』岩波文庫 一三〇頁
(137)和島誠一「序説―農耕・牧畜発生以前の原始共同体」(前掲註37)
(138)和島誠一「原始聚落の構成」(前掲註31)
(139)和島誠一「考古学からみた日本のあけぼの」(前掲註39)
(140)和島誠一「弥生時代社会の構造」(前掲註47)
(141)和島誠一・田中義昭「住居と集落」(前掲註47)
(142)和島誠一・金井塚良一「集落と共同体」(前掲註47)
(143)松村瞭・八幡一郎・小金井良精『下総姥山ニ於ケル石器時代遺跡』東京帝国大学人類学教室研究報告五 一九三二 なお、ポスト和島集落論に立つ岡本勇も姥山例のあり方に触れ�、「ある血縁集団のなかでももっとも近親的な関係にある小集団、すなわち「自然家族」とみなしておきたい」という考えを明らかにしている。岡本勇「原始社会の生産と呪術」『岩波講座日本歴史』一 一九七五
(144)以上の事実は、おそらく和島自身が住居構成員の考古学的な解明に非常に苦慮していたことを示すものであろうが、和島の一九六二年の『序説―農耕・牧畜発生以前の原始共同体』は、前号でも触れた通り、「世帯共同体」概念をめぐるいくつかの混乱がみられた論文としても注意される。本論文には、この他にも「竪穴に住む家族」という、前後の論文とは明らかに矛盾する記述が縄文中期段階について残されており、和島集落論全体に占める本論文の評価を大変難しいものにしている。いずれにせよ、世帯共同体論を中心とする和島論の理論的検討を試みた先の大塚実の言葉にもあるように、「多くの業績を残された優れた研究者の見解は、その研究の深化進展とともに発展的にとらえる」(大塚実『古代共同体論』前掲註39)必要がある、ということであろう。註68参照
(145)鏡山猛「環溝住居址小論(一)」 同『北九州の古代遺跡』(前掲註35)
(146)L・H・モルガン、青山道夫訳『古代社会』岩波文庫 F・エンゲルス、戸原四郎訳『家族・私有財産・国家の起源』岩波文庫
(147)水野正好「縄文式文化期における集落構造と宗教構造」(前掲註88)
(148)水野正好「縄文時代集落復原への基礎的操作」(前掲註92)
(149)水野正好「集落」(前掲註101)
(150)水野正好「縄文式文化期における集落構造と宗教構造」(前掲註88)
(151)大林太良「縄文時代の社会組織」(前掲註102) 長崎元広「八ヶ岳南西麓の縄文中期集落における共同祭式のあり方とその意義(上)(下)」(前掲註103)
(152)ユ・イ・セミョーノフ、中島寿夫他訳『人類社会の形成 上巻』一九七〇
(153)「氏族は、時代的にはプナルア家族の最初の出現より遅かったのであるが、その起源において、人類発達の低い段階に、そしてまたきわめて古い社会状態に属している。氏族が実質的には氏族の成員と一致する人々の集団からなるこのプナルア家族から生じたことはきわめて明瞭である�。�」 L・H・モルガン、青山道夫訳『古代社会』岩波文庫 二二二頁
(154)F・エンゲルス、戸原四郎訳『家族・私有財産・国家の起源』岩波文庫 一一八頁
(155)和島誠一「序説―農耕・牧畜発生以前の原始共同体」(前掲註37)
(156)塚田光「縄文時代の共同体」『歴史教育』一四―三 一九六六
(157)「当初、宮坂氏は、尖石全竪穴群の数を五百ほどに推算し、そのまたがる土器形式移行を三時期とみ、同時存在戸数を約百数十戸と考え、私もその説に賛同し、現農村にも勝る規模の大集落、そんなものが、はたして拾集経済で存立し得るだろうか。私のその後、幾変転して行くことになった、縄文中期文化が原始的な植物栽培による社会機構としか考えられないという推論の出発点となったわけである。むろん、その後の吟味、芹沢長介氏の教示により、その過大評価はあきらかであるが、さりとて、同時存在二十戸を降るものとは、現在も思っていない」。塚田論が掲載された同じ『歴史教育』誌上で藤森栄一は以上のようにのべている。また、時期は下がるが、小山修三も尖石と与助尾根とを本村・分村の関係にあるものとしてとらえ、尖石周辺には二百を越える人間が居住していたという考えを、その根拠をまったく示さないまま、明らかにしている。塚田とはまさしく対照的な発言であるが、尖石をめぐる同時存在住居数の問題については先に佐々木自身も分析を試み、従来、調査者の宮坂英弌によって中期後半期を主体とする第一形式から第三形式までの三分割案が示されてきた本集落は、実は中期中葉から末葉に至る六型式期以上に細分される可能性が強いこと、各細分型式期毎の集落規模は、したがって宮坂らの予想よりも遥かに小さなものとなる可能性も否定できないことなどを指摘したことがある。現在、尖石周辺では特別史跡保存整備事業にかかわる試掘調査が進行中であるが、その結果も時間的構成に関する佐々木の見解の妥当性を大筋で裏付けており、試掘調査で検出された住居群は中期初頭から後半のものまで時間的に幅をもつこと、これまで遺構の分布が希薄と思われてきた北東地区からもかなりの数の住居が出土しており、今後の調査次第では尖石そのものが大きく三個所に分けられる可能性も十分考えられること、その場合には「本遺跡と与助尾根南遺跡・与助尾根遺跡も含め、5つの東西に長い集落が、存在していた」可能性も考慮されることなどが報告されている。縄文時代集落論の原点に位置し、多くの研究者によってその規模や構造、隣接する与助尾根・与助尾根南両遺跡との関係などが様々に論議されてきた本遺跡の評価をより正確なものとする上からも、ともあれ、試掘調査の今後の行方を注目したい。藤森栄一「原始古代聚落の考古学的研究について」『歴史教育』一四―三 一九六六 佐々木藤雄「与助尾根集落論の再評価」『異貌』九 一九八一 小山修三『縄文時代―コンピュータ考古学による復元』一九八四 茅野市教育委員会『尖石遺跡―保存整備事業に係わる試掘調査報告書』一九九四
(158)松村瞭・八幡一郎・小金井良精『下総姥山ニ於ケル石器時代遺跡』(前掲註143)
(159)山内清男「縄文式文化」『日本原始美術』一 一九六四
(160)佐々木藤雄「縄文時代の家族構成とその性格―姥山遺跡B9号住居址内遺棄人骨資料の再評価を中心として」『異貌』一二 一九八八
(161)堀越正行「縄文時代の集落と共同組織」『駿台史学』三一 一九七二
(162)三上徹也「縄文時代居住システムの一様相―中部・関東地方の中期を中心として」『駿台史学』八八 一九九三
(163)小林達雄「縄文時代の居住空間」『國學院大學大学院紀要』一九 一九八七
(164)堀越正行「縄文時代の集落と共同組織」(前掲註161)
(165)春成秀爾「縄文時代の複婚制について」『考古学雑誌』六七―二 一九八一 なお、周知のように春成は、縄文時代からさらには弥生時代を含めた家族・親族構造について、これまでにも東・西日本を見通した幅の広い、しかも集落論第二世代に属する塚田や水野ともまったく異なる独自の視点からの積極的な発言を続けている。ここで取り上げた縄文時代をめぐる複婚制の問題も、もとより「日本原始の婚姻制度」の全体的な解明をめざす春成の、今日ではもっとも体系的ともいえる作業の一部をなすものとして存在するが、本稿の性格上、その詳細にまでは立ち入ることができなかったことを明記しておきたい。
(166)佐々木藤雄「縄文時代の家族構成とその性格―姥山遺跡B9号住居址内遺棄人骨資料の再評価を中心として」(前掲註160) ところで、最近、土井義夫は姥山例にうかがわれる埋葬行為と生活用具の除去行為に関連して�「このことに注目した文献は管見ではほとんど見当たらない」とのべ、�「半世紀を越える長い間、5体の人骨たちは、この竪穴住居に生活していた家族と思い込まれてきた。しかし、今、発見当初から知られていた状況証拠を盾に取って、彼らが再審請求を強く求めたとしても不思議ではない」と結んでいる。土井によれば、この論文は一九八五年から一九九一年にかけて提出されたいくつかの短文や報告を新たにまとめたものといわれる。佐々木自身も姥山例に関する土井の見通しの一半の正しさについては率直に評価するところであり、一九八六年の佐々木の論文でも、本例を廃屋葬のバリエーションの中でとらえようとする山本輝久と並んで土井の手になると思われる『物質文化』同人の解釈を姥山論の新しい可能性を示すものとして引用し、両者の限界性は五人同居=五人同時死亡説の明確な否定に立った五体の人骨の歴史的な性格に対する分析の欠如にあったことをはっきりと指摘している。土井の発言は残念ながらこうした事実をふまえた上でのものであったとは到底考えがたく、特に�「このことに注目した文献は管見ではほとんど見当たらない」という部分についてはまったく容認することはできない。土井が主張する発掘資料や学史の正しい評価という意味からも姥山論の現在についての補足的な説明があって然るべきであり、まして佐々木による五人同居=五人同時死亡説の全面的な否定さえも“幻”であったかのような不可解な議論のあり方に対しては、逆に強い異議を唱えるものである。(ど)著名「同人言」『物質文化』四四 一九八五 山本輝久「縄文時代の廃屋葬」『古代』八〇 一九八五 土井義夫「再審請求したいのは姥山人だけではない」『論集 宇津木台』一 一九九五
(167)これに対し、小山修三と間壁葭子の二人は、本年一月発表の最新の論文において、この五人同居=五人同時死亡という“幻の前提”を援用した、まさしくアナクロニズムそのものとしかいいようのない“縄文時代家族論”を一方的に展開している。小山の「中期には住居跡内で複数の人骨が発見される例がある。これは竪穴住居の住人が、全員同時に死亡し、そのまま放置されたとされている。この仮説を受け入れれば・・・男2、女2(三沢、姥山)とな」るという部分、間壁の「古くから著名な千葉県姥山貝塚での例で、成年男女2人ずつに小児1人が同一住居内に、同時死亡のまま遺棄されたように埋葬されていた」という部分がそれであり、小山が豊富な民族例の紹介をあわせて試みていたことを除けば、縄文時代に関する二人の家族論の中には考古資料の正しい分析・引用にもとづく新鮮かつ具体的な問題提起、何よりもかれらのオリジナリティーはまったくみあたらない。 その二人の“家族論”が最新の考古学的成果の集大成を目指したといわれる『考古学による日本歴史』一五の『家族と住まい』をともに飾っている事実は何とも皮肉であり、同じ小山を介して『岩波講座日本通史』でも露呈された縄文時代集落論の絶望的な状況の一端をそこにみてとることは決して難しいことではない(註121参照)。
しかし、日本考古学にとっての本シリーズの高い意義と影響力とを考えるとき、ほとんど十年以上も前の研究水準にとどまっているとしか思われない小山と間壁の見当外れの提起を、東日本を中心とする縄文時代研究の情報から疎遠な位置にある西日本の研究者の単なる勉強不足として片付けることが妥当であるのかどうか。和島誠一や宮坂英弌らの先駆的な作業以来、営々として築かれてきた縄文時代集落研究の成果を正しく継承・発展していく上からも、誤った“考古学による日本歴史”の垂れ流しに対する二人の徹底した自己批判を強く望みたい。小山修三「食料採取時代の家族・親族」 間壁葭子「婚姻の考古学」『考古学による日本歴史』一五 一九九六
(168)原秀三郎「日本における科学的原始・古代史研究の成立と展開」(前掲註40)
(169)前出のセミョーノフはマルクスの『古代社会ノート』を引用しつつ、マルクスがエンゲルスとは対象的に、血縁家族やプナルア家族という二つの集団婚が氏族に先行していたというモルガンの仮説に対しては批判的であったこと、むしろ氏族に直接先行するものとしては「無規則な性関係をもっている群」(K�・マルクス、布村一夫訳『古代社会ノート』合同出版社 一九二頁)、すなわち原始的な乱婚集団の存在を考慮していたことなどを明らかにしている。また、集団婚そのものについては一貫した支持を与えつづけたエンゲルス自身も、『起源』の第四版においては「血縁家族」や「プナルア家族」に関するモルガンの仮説の「ゆきすぎ」(F�・エンゲルス、戸原四郎訳『家族・私有財産・国家の起源』岩波文庫 五八頁)に危惧を表明していたことが注意される。ユ・イ・セミョーノフ、中島寿夫他訳『人類社会の形成 上巻』(前掲註152)
(170)「オーストラリアでおこなわれているような全婚姻階級ごとの婚姻は、いずれにしても集団婚のきわめて低次の本源的な形態であるが、これにたいしてプナルア家族は、われわれの知るかぎりでは、集団婚の最高の発展段階である。前者は、放浪をつづける野蛮人の社会状態に照応する形態のようであり、後者は、共産制的共同体のすでにかなり固定的な定着を前提とし、つぎのヨリ高次の発展段階に直接つながるものである。」F・エンゲルス、戸原四郎訳『家族・私有財産・国家の起源』岩波文庫 六二頁
(171)甲元眞之「農耕集落」(前掲註55)
(172)長崎元広「縄文集落研究の系譜と展望」(前掲註32)
(173)和島誠一・金井塚良一「集落と共同体」(前掲註47)
(174)和島誠一・田中義昭「住居と集落」 和島誠一・金井塚良一「集落と共同体」(前掲註47)
(175)勅使河原彰「縄文時代の社会構成(上)(下)―八ヶ岳西南麓の縄文時代中期遺跡群の分析から」『考 古学雑誌』七八―一、二 一九九二
(176)林謙作「縄紋時代史21〜27 縄紋人の集落(1)〜(7)」『季刊考古学』四七〜五三 一九九四〜一九九五
(177)この問題に関して林謙作は次のようにのべている。「和島の論理の組み立てが演繹的なものである以上、あらかじめ決まっている結論を引きだすために材料を操作している、という批判も的はずれなのだ。ただし、和島の発言のなかに仮説の検証といえる部分がほとんど含まれていないことは否定できない�。」 林謙作「縄紋時代史21〜27 縄紋人の集落(1)〜(7)」(前掲註176)
(178)和島誠一「原始聚落の構成」(前掲註31)
(179)原秀三郎「日本における科学的原始・古代史研究の成立と展開」(前掲註40)
(180)近年、縄文時代集落論を取り巻く深刻な停滞状況に言及した羽生淳子は、その最大の原因を社会的側面の分析に重点を置いた和島誠一の母系的氏族共同体論を核とする一連の集落研究に求め、和島的な「マルクス主義歴史学の理論的枠組」を継承しながら集落論を展開することになった研究者の例として麻生優、市原寿文、岡本勇、菅原正明、勅使河原彰、林謙作、堀越正行、向坂鋼二らをあげるとともに、それにかわる新しい理論的枠組みとして「考古学における生態学的なアプローチ」の導入・活用を強く主張している。しかし、すでに明らかなように、社会的側面の分析に重点を置いた集落研究の実態は、実は和島の氏族共同体論という大枠の中には到底一括できないほど多種多様であったのであり、また、羽生が先に名前を列挙した研究者も、岡本や勅使河原らを除けば、大半は史的唯物論とは立場・方法を異にする者によって占められていたことは、土井義夫、山本輝久、それに佐々木などによって指摘されている。まして、今日における集落論停滞の最大の要因を「マルクス主義歴史学の理論的枠組」の中に求め、社会構造の復元を主目的とした集落研究の多くを和島以来の史的唯物論的な方法に立つものとして退ける羽生の試みは、これまでの学史に対する無知・無理解が招いた独りよがりな作業でしかなく、その独善性をさらに際立たせていたのが、史的唯物論と唯物史観の区別さえおぼつかない羽生の偏狭な“マルクス主義歴史学”観であったことは佐々木の旧稿に詳しい。
縄文時代集落論をめぐって認められる行きづまり状況は、史的唯物論的な方法とも、社会的側面の分析に重点を置いた研究のあり方ともまったく無縁である。縄文時代の社会構造に対するこれまでの分析・復元作業はむしろ不十分であり、列島史としての総合化・体系化を可能とする理論・実証両面にわたる試行を不徹底なものとしてきたところに逆に現在の集落論が抱える問題の一つの大きな根があったことは本稿でも繰り返しのべてきている通りである。羽生の批判は、まさしくこうした視点を放棄したまま、たとえばポスト和島集落論に代表される、和島が遥か数十年も前に呈示した“テーゼ”からほとんど足を踏み出すことをやめた化石のような集落論にこそ向けられるべきであったのであり、その上で、はじめて「生業の季節性や資源の分布とセトルメント・パターンとの密接な関係」に対する視点の重要性が語られるべきであったと考える。しかし、「マルクス主義歴史学の理論的枠組」にかわって「考古学における生態学的なアプローチ」の導入を声高に叫ぶ羽生論にみられるのは、大型獣の狩猟を行うネアンデルタール人、いいかえればヴュルム氷期の狩人の集落・生業システムの復元を主目的にアメリカ人考古学者ルイス�・R�・ビンフォードによって設定されたヌナミュート・エスキモーによる“コレクター・モデル”を、列島の縄文人と直接結びつけようとするエセ“民族考古学”であり、“翻訳考古学”の類でしかない。
和島らの「マルクス主義歴史学の理論的枠組」に激しい批判を加えた羽生は、しかし、自らに向けられた佐々木らからの批判に対しては、一転してまったくの沈黙を守っている。わずかに羽生の一九九四年の論文にはこの点に触れた記述がみられるが、「縄文時代の研究に、環境条件の違うヌナミウトの民族誌例に基づいたモデルを適用することへの疑問」に関連してインフォーマル・モデルとしての“コレクター・モデル”の普遍性がまったくの一般論として語られているだけであって、羽生自身の作業にみられる論理・方法の欠陥や学史・資料評価の誤りなどについては少しも触れられていない。民族考古学のいわば“本場”からの発言であるにもかかわらず、羽生論はそもそも「考古学における生態学的なアプローチ」の出発点において大きなミスを犯しており、民族考古学・プロセス考古学の基本的な理解に関しても誤りが多すぎるというのが一九九〇年の論文に対する佐々木の率直な評価であり、“コレクター・モデル”の縄文時代への適用にあたっても、その普遍性を強調する羽生の言葉とは裏腹に、ヌナミュート・エスキモーの民族誌と縄文文化との、歴史的な観点も生態的な観点もどこかへ置き忘れてしまったかのような安直な比較が目立つというのが佐々木に羽生論への批判を思い立たせた重要な要因の一つであった。それにもかかわらず、自らへの具体的な批判の数々に対しては何一つ具体的な解答を試みないまま、ビンフォードらの一般理論を今更“御神託”のように持ち出したところで、一体、どのような意味があるとでも羽生はいうのであろうか。羽生が見当外れな批判を繰り返した「マルクス主義歴史学の理論的枠組」にかかわる問題は、一体、どこへ消え去ってしまったのであろうか。あまりにも不誠実であり、自論の矛盾・破綻を湖塗するために問題を一般論・抽象論へとすり替えているだけでしかない。
いずれにせよ、自らの理論的水準の低さに加えて、羽生の作業が図らずもうかびあがらせることになった相互批判や論争を回避した身勝手で独善的な姿勢こそは、実は過去の成果や理論の誤った評価、プライオリティーの軽視などと並んで縄文時代集落論の創造的な展開を永らく阻んできた大きな要因であったというべきであり、“新しい考古学”を標榜する、戦後団塊世代に後続するいわば集落論第四世代に見え隠れする保守性を見事に表現している。他者の批判を試みる者こそ、自らへの批判には真摯に答えるべきであろう。羽生淳子「縄文時代の集落研究と狩猟・採集民研究との接点」『物質文化』五三 一九九〇 同「狩猟・採集民の生業・集落と民族誌―生態学的アプローチに基づいた民族誌モデルを中心として」『考古学研究』四一―一 一九九四 土井義夫「一九九〇年の縄文時代学界動向 集落・領域論」『縄文時代』二 一九九一 山本輝久「縄文時代文化研究とエスノアーケオロジー」『縄文時代』二 一九九一 佐々木藤雄「和島集落論と考古学の新しい流れ―漂流する縄文時代集落論」(前掲註1)
(181)佐々木藤雄「和島集落論と考古学の新しい流れ―漂流する縄文時代集落論」(前掲註1)
(182)勅使河原彰「縄文時代の社会構成(上)(下)―八ヶ岳西南麓の縄文時代中期遺跡群の分析から」(前掲註175) 詳しい説明は省略するが、勅使河原は複婚家族と拡大家族、それらを包摂する複合家族の三者を混同して使用している。註281参照
(183)“集団婚―母系的氏族共同体論”の本源的な基盤が明確に崩れ去った以上、和島の本質的な問題提起の数々を矮小化する教条主義的な発言を繰り返してきた独善的なポスト和島集落論そのものについても、一日も早い修正・撤回を望みたい。前号でも批判したように、たとえば「中央に広場が組み合わさるという集落形態」と「氏族共同体的な関係」と「生産と消費がつねに等質な社会」の三者を、具体的な根拠をまったく示すこともなく、どうして勅使河原は直截的に結びつけることができるのか(勅使河原彰「縄文時代集落をめぐる問題」前掲註48)。それとも勅使河原は、「中央に広場が組み合わさるという集落形態」こそは「古い無階級の氏族社会」の重要な表徴とでもあったと真剣に思っているのか。勅使河原も常日頃口にする“歴史科学としての日本考古学”の「自殺行為」(佐々木藤雄「和島集落論と考古学の新しい流れ―漂流する縄文時代集落論」前掲註1)にもつながりかねない、きわめて危うい行為であったといわねばならない。註48・註180参照
(184)甲元眞之「農耕集落」(前掲註55)
(185)林謙作「縄紋時代史21〜27 縄紋人の集落(1)〜(7)」(前掲註176)
(186)丹羽佑一「縄文集落の基礎単位の構成員」『文化財学論集』一九九四
(187)戸沢充則「縄文集落研究の「原点」」(前掲註91)
(188)桐原健「村うちの道―古代集落復原への一作業」『中信考古』創刊号 一九八四
(189)桐原健『自著自註』一九九三
(190)戸沢充則「海戸遺跡における集落(住居址群)の構成」『海戸 第二次調査報告書』一九六七
(191)桐原健「南信・八ヶ岳山麓における縄文中期の集落構造」『古代学研究』三八 一九六四
(192)渡辺誠「縄文時代における埋甕風習」『考古学ジャーナル』四〇 一九七〇
(193)村田文夫「関東地方における縄文前期後半期の生産活動について」『古代文化』二二―四 一九七 〇
(194)向坂鋼二「原始集落の形と特徴」『日本考古学を学ぶ』三 一九七九
(195)宮坂光昭「茅野和田遺跡における縄文中期集落址の分析」『長野県考古学会誌』一一 一九七一
(196)菅原正明「縄文時代の集落」『考古学研究』一九―二 一九七二
(197)丹羽佑一「縄文時代の集団構造―中期集落に於ける住居址群の分析より」『考古学論考 小林行雄博士古稀記念論文集』一九八二
(198)藤野修一「縄文時代の集落構造解明へのアプローチ」『東京考古』四 一九八六
(199)鵜飼幸雄「棚畑遺跡の縄文時代集落の概観」『棚畑』一九九〇
(200)新津健「縄文時代中期後半の集落2」『研究紀要』九 一九九三
(201)三上徹也「縄文時代居住システムの一様相―中部・関東地方の中期を中心として」(前掲註162)
(202)丹羽佑一「縄文集落の住居配置はなぜ円いのか」『論苑 考古学』 一九九三 同「縄文集落の基礎単位の構成員」(前掲註186)
(203)長崎元広「縄文集落研究の系譜と展望」(前掲註32)
(204)三上徹也「縄文時代居住システムの一様相―中部・関東地方の中期を中心として」(前掲註162)
(205)林謙作「縄紋時代史21〜27 縄紋人の集落(1)〜(7)」(前掲註176)
(206)丹羽佑一「縄文集落の基礎単位の構成員」(前掲註186)
(207)都出比呂志「森本六爾論」(前掲註75)
(208)林謙作「縄紋時代史21〜27 縄紋人の集落(1)〜(7)」(前掲註176)
(209)甲元眞之「農耕集落」(前掲註55)
(210)原秀三郎「日本における科学的原始・古代史研究の成立と展開」(前掲註40)
(211)三上徹也「縄文時代居住システムの一様相―中部・関東地方の中期を中心として」(前掲註162)
(212)長崎元広「縄文集落研究の系譜と展望」(前掲註32)
(213)なお、この問題については以下の論文に詳しい。佐々木藤雄「“縄文時代集落論”の現段階」『異貌』二 一九七五 同「与助尾根集落論の再価」(前掲註157) 同「縄文時代の親族構造�」『異貌』一〇 一九八三 同「縄文時代の家族構成とその性格―姥山遺跡B9号住居址内遺棄人骨資料の再 評価を中心として」(前掲註160)
(214)村田文夫「関東地方における縄文前期後半期の生産活動について」(前掲註193)
(215)久保常晴『本町田』一九六九
(216)ふれいく同人会「水野正好氏の縄文時代集落論批判」『ふれいく』創刊号 一九七一
(217)小林達雄「原始集落」『岩波講座日本考古学』四 一九八六
(218)水野正好「なぜ縄文時代集落論は必要なのか」(前掲註97)
(219)水野正好「縄文時代集落復原への基礎的操作」(前掲註92)
(220)菅原正明「縄文時代の集落」(前掲註196)
(221)向坂鋼二「原始集落の形と特徴」(前掲註194)
(222)新津健「縄文時代中期後半の集落2」(前掲註200)
(223)この点に関連してきわめて興味深い報告が高根木戸遺跡の再分析を試みた大村裕によって行われている。馬蹄形集落の典型的な例としてしばしば引用される本遺跡の七五軒の竪穴住居のうち、出土土器の掲示がなかったり出土状況が不明なため、所属時期の追認の困難な住居は実に全体の半数近い三六軒にのぼること、重複する四二軒の住居のうち、切り合い関係についての記述があるものは二七軒、先後関係を知るための土層断面図が掲載されたものはわずか二軒にとどまることの二つがそれであり、他遺跡の例とあわせて「充分に吟味されないままあふれ出た情報洪水」に翻弄される日本考古学の姿を描き出している。群別作業者は、一体、どのような激しい格闘の末にこうしたハンディキャップをのりこえ、七〇軒を超える住居の時間的および空間的関係の確認にこぎつけたのであろうか。高根木戸に対する群別結果には、始期を含めて四段階(水野、新津)、五段階(向坂)というように、その時期区分をめぐっても研究者による大きな差異があったことを付け加えておきたい。大村裕「�「縄文時代像の転換」と歴史教育」 『歴史評論』五四八 一九九五
(224)坪井清足『縄文文化論』(前掲註89) なお、坪井は以上に続けて「小群」の性格にも触れ、「石柱祭壇をもつ統率者群」のもとに�「土偶を祭る女性群�」と「石棒をもつ男性群」とが性別の住みわけを行っていた可能性に言及している。和島誠一の一九六六年の提起とほとんど同一の内容であり、集落全体を「氏族集団」と規定することともあわせてきわめて注目される。註144参照
(225)菅原正明「縄文時代の集落」(前掲註196) 向坂鋼二「原始集落の形と特徴」(前掲註194)
(226)丹羽佑一「縄文集落の基礎単位の構成員」(前掲註186)
(227)長崎元広「縄文集落研究の系譜と展望」(前掲註32)
(228)丹羽佑一「縄文集落の基礎単位の構成員」(前掲註186)
(229)丹羽佑一「縄文時代の集団構造―中期集落に於ける住居址群の分析より」(前掲註197)
(230)佐々木藤雄「縄文時代の親族構造」(前掲註213) 同「縄文時代の家族構成とその性格―姥山遺跡B9号住居址内遺棄人骨資料の再評価を中心として」(前掲註160)
(231)Radcliffe‐Brown,A.R.“Three Tribes of Western Australia,”Journal of the Royal Anthropological Institute,vol.43 ,1913 R・M・キージング、小川正恭・笠原政治・河合利光訳『親族集団と社会構造』一九八二
(232)今日的にいえば、机上の論理ならぬ机上のコンピュータにあわせて生きた歴史をもてあそんでいるだけであり、歴史科学としての考古学的な分析作業とは相容れないものである。藤野修一「縄文時代の集落構造解明へのアプローチ」(前掲註198)
(233)ロビン・フォックス、川中健二訳『親族と婚姻社会人類学入門』一九七七
(234)丹羽佑一「縄文集落の基礎単位の構成員」(前掲註186)
(235)丹羽佑一の一連の群別作業は水野集落論の影響を受けた多くの研究の中でももっとも体系的かつ継続的であり、その問題点についてはいずれ稿を改めて論じなければならないと考えている。なお、評価は異なるが、林謙作は近年の論文においてカリエラ体系をはじめとする丹羽集落論の総合的な検証を独自の視点から試みており、注目される。林自身の家族・親族論も、註165で触れた春成秀爾同様、集落論第二世代の一方を代表する研究として重要な位置を占めるが、やはり本稿の性格上、その詳細にまでは立ち入れなかったことを付記しておきたい。林謙作「縄紋時代史21〜27 縄紋人の集落(1)〜(7)」(前掲註176)
(236)三上徹也「縄文時代居住システムの一様相―中部・関東地方の中期を中心として」(前掲註162)
(237)広義の意味での男女の住み分けについては、すでに明らかなように水野正好、和島誠一の二人もその可能性に触れている。しかし、水野は二軒を一単位とする小群の解釈の一つの例として性別集団、同じく和島も水野の与助尾根分析結果に対する一つの解釈として男と女、それに長老の属するグループ毎の分割居住を考えていたのであり、三上の男女分棟論との違いは決定的である。水野正好「縄文式文化期における集落構造と宗教構造」(前掲註88) 和島誠一・田中義昭「住居と集落」 (前掲註47)
(238)佐々木藤雄「縄文時代の家族構成とその性格―姥山遺跡B9号住居址内遺棄人骨資料の再評価を中心として」(前掲註160)
(239)石毛直道『住居空間の人類学』一九七一
(240)岡本勇「総論」『縄文文化の研究』一〇 一九八四
(241)戸沢充則「縄文集落研究の「原点」」(前掲註91)
(242)小山修三『縄文時代―コンピュータ考古学による復元』(前掲註157)
(243)小山修三「狩猟採集時代の生活と心性」(前掲註121)
(244)前述したように水野集落論の「呪縛」からの自立と新しい群別作業の創造を主張する丹羽佑一と三上徹也の二人は、しかし、そうした言葉の一方で、それぞれの群別結果の解釈に揃って水野の“三家族(二棟一家族)三祭式(石柱・石棒・土偶)分掌論”を積極的に援用している。すなわち、丹羽の「与助尾根遺跡等では宗教活動において2棟は明確に区分されている」、三上の「与助尾根遺跡を分析した水野氏の二棟の一に宗教的遺物を持つという指摘」云々という記述がそれである。群別作業者による“水野批判”の限界性を見事に露呈するものであり、自家撞着も甚だしいといわざるをえない。問われているのは本来の意味における水野集落論からの自立であろう。丹羽佑一「縄文集落の基礎単位の構成員」(前掲註186) 三上徹也「縄文時代居住システムの一様相―中部・関東地方の中期を中心として」(前掲註162)
(245)三上徹也「縄文時代居住システムの一様相―中部・関東地方の中期を中心として」(前掲註162)
(246)ふれいく同人会「水野正好氏の縄文時代集落論批判」(前掲註216)
(247)塚田光「平出遺跡の縄文土器「第3類A�」�」『考古学手帳』二〇 一九六三 同「縄文時代の共同体」(前掲註156)
(248)後藤和民「土偶研究の段階と問題点(?V)」『考古学手帳』二四 一九六四 同「縄文集落の概念�」(前掲註85)
(249)佐々木藤雄「“縄文時代集落論”の現段階」 同「与助尾根集落論の再価」 同「縄文時代の親族構造�」(前掲註213) 同「縄文時代の家族構成とその性格―姥山遺跡B9号住居址内遺棄人骨資料の再評価を中心として」(前掲註160)
(250)この他、同一土器型式期間内における集落や住居の廃絶・移動の可能性を指摘する末木健や石井寛らのいわゆる「集団移動論」も水野正好の「住まいの流れ」の復元にもとづく群別作業に対する批判の一つとして位置づけることができる。さらに黒尾和久は、「土器型式のうえで「同時期」の住居であっても近接住居間に接合資料が認められない」ことに着目し、近接する住居が一体となって「群」を構成したという水野の考えに大きな疑問を投げかけている。末木健「移動としての吹上パターン」『山梨県中央道埋蔵文化財包蔵地発掘調査報告―北巨摩郡長坂・明野・韮崎地内』一九七五 石井寛「縄文時代における集団移動と地域組織」『調査研究集録』二 一九七七 黒尾和久 「縄文時代中期の居住形態」『歴史評論』四五四 一九八八
(251)藤森栄一『井戸尻』(前掲註94) なお藤森は、別の論文の中で与助尾根集落分析をめぐる「時間」の問題にも言及し、水野正好らの集落「理論が、許容される前には、いま一つの手続がぜひとも必要である。それは、いうまでもなく、住居址の同時性の証明である」とはっきりと書いている。藤森栄一「原始古代聚落の考古学的研究について」(前掲註157)
(252)宮坂英弌「八ヶ岳西山麓与助尾根先史聚落の形成についての一考察(上)(下)」(前掲註86) 同『尖石』(前掲註79)
(253)周知のように、与助尾根集落分析作業の実際は、水野正好の一九六三年の論文よりも、その前年に発表されることになった坪井清足の紹介にもっとも詳しい。坪井清足「縄文文化論」(前掲註89)
(254)ふれいく同人会「水野正好氏の縄文時代集落論批判」(前掲註216) 佐々木藤雄「与助尾根集落論の再評価」(前掲註213)
(255)『茅野市史』において「宮坂英弌と尖石・与助尾根遺跡」を執筆し、未発表土器資料をもとに与助尾根集落が四段階に細分されることを改めて示した勅使河原彰は、しかし、ふれいく同人や佐々木らの先行する作業の存在にはまったく触れないまま、�「今回の再調査の結果、その基本となる事実関係について、大きな違いが生じていることが明らかとなった」とのべている。水野正好の二段階説と四段階説との食い違いがあたかも勅使河原の調査によってはじめて確認されたかのような発言はきわめて独善的であり、研究史の正しい評価の確立という本市史の目的とも大きく矛盾するものと考える。水野に対する宮坂の批判的な姿勢(註262参照)とあわせて、与助尾根集落に関する宮坂自身の評価についての記述が少しもみられないことも不可解な点であり、タイトルとは裏腹に宮坂の業績の体系的な理解を難しいものとしていたことは皮肉である。勅使河原彰「宮坂英弌と尖石・与助尾根遺跡」『茅野市史』上巻 一九八六
(256)ここで使用した曽利式土器の編年は、基本的に中部高地縄文土器集成グループ『中部高地縄文土器集成 第一集』一九七九に拠っている。なお、尖石遺跡出土住居群の大まかな時間的構成についてはすでに註157で触れている。一方、尖石と与助尾根の二つの遺跡に挟まれた与助尾根南遺跡では一九七八年の調査で前期前半期一軒、中期後半期四軒、あわせて五軒の住居の存在が確認されており、うち中期後半期の四軒は曽利?U〜?V式、特に?V式を主体とした土器の出土を示していること、一九五〇年に二・三号住居付近で発見された石囲炉址もほぼ同時期の住居であった可能性が高いことなどが報告されている。茅野市教育委員会『与助尾根南遺跡』一九八〇
(257)小山修三は赤澤威・埴原和郎の二人が試みた「長野県与助尾根遺跡の統計学的分析」に対するコメントの中で土器型式を捨象した水野正好の分析作業を擁護する立場を明らかにし、「数百の住居址を考古学者が分類(または時期的同定)するとき、伴出する土器形式のみに依るという間接的方法をとるばあいが多い。そのため、はっきりした土器の伴出のない大部分の住居址が、時期不明ということで考察の対象から除外されてしまう。したがって、復原される一時期の集落はたかだか十数軒という、大規模発掘の目的とはうらはらな結果に終わっている例が少なくない」とのべている。また、水野自身も同じコメントの中で土器型式によらない分析作業の正当性を強調し、「与助尾根遺跡の調査は古く、床面の遺物、覆土中の遺物、凹地化した住居跡に置きすえられた遺物の区別はなされなかったし、調査者の意識にはのぼらなかったようであり記述も欠いている。したがって、各住居を曽利?U式、曽利?V〜?W式といったぐあいに編年することはひじょうにむつかしいのである」とのべている。
一見、もっともらしい意見ではあるが、こうした“正論”は、あくまでも住居内出土土器の精細な検討を経た場合にのみはじめて意味をもつ。水野らにかかる発言を行うに足る資格が備わっていたかどうかはきわめて疑問であり、むしろ「縄文式前期に近い」という炉体土器に関する報告書の記述や明らかに型式を異にする埋甕使用土器の存在すら一顧だにされていない水野の与助尾根分析作業のあり方を考慮に入れるならば、もともと水野らには、住居内出土土器を検討しようとする意欲や、住居群の時間性を云々するだけの縄文土器に関する知識といったものは、まったく欠如していたのではないかという感想を決して拭うことはできない。
小山は水野集落論を縄文時代集落論を代表する研究例として取り上げた前出の啓蒙書の一四〇頁において、与助尾根後期集落の住居数を一五軒、総人口を約九〇人として紹介している。しかし、同書の一六八頁では、一転して一時期の本集落の住居数を一二軒に戻している(小山修三『縄文時代―コンピュータ考古学による復元』前掲註157)。「人類学者から考古学者にむけられる不満の一つは、考古学者が遺物の型式による相対的な時代区分に固執しすぎることにある。・・・人類学の興味は、ある段階での抽象化された復原ではなく、流動する状況の過程をあぶりだすことにある」と高言する小山としてはあまりにも安易かつお粗末な仕事ぶりであり、かれが得意とする“コンピュータ考古学”による縄文時代の人口復元作業(註157参照)の精度そのものについても大きな疑問を抱かせる出来事であったといわなければならない。小山修三「コメント 1」 水野正好「コメント 2」『季刊人類学』九―二 一九七八
(258)宮坂英弌『尖石』(前掲註79)
(259)宮坂英弌によれば、「この石囲炉は、表面が平滑な扁平の自然塊石一二個を平に赤土面に堅く粘着させ、南北の長軸径〇・九三米、東西の短軸径〇・八〇米、深さ六糎、平面を楕円形に囲む」とある(註79参照)。以上の特徴は六号(曽利?U期)および二二号住居出土例との近似性をうかがわせるが、与助尾根集落の復元上、きわめて重要な意味をもつ本石囲炉と二八軒の住居群との関係については、前出の『茅野市史』も何故か一切の明言を避けており、問題を一層不明瞭なものとしていたことは否めない。茅野市『茅野市史』上巻 一九八六
(260)勅使河原彰「宮坂英弌と尖石・与助尾根遺跡」(前掲註254)
(261)宮坂英弌『尖石』(前掲註79)
(262)藤森栄一「原始古代聚落の考古学的研究について�」(前掲註157) なお、本論文の中で藤森は、�「二軒ずつ三組の一グループが東・西にそれぞれ並存しながら同じように移動したという説・・・については、発掘者宮坂氏からの反対もあり、一般を説得するだけの努力をつくされていない」とのべている。調査報告者宮坂英弌による水野正好の与助尾根集落論評価を知る上からもきわめて興味深い発言である。
(263)「発掘範囲、発掘範囲外の遺構の有無、遺構の正確な実測、遺物の詳細な発見状況すら十分に図示されていない現状では、多くの発掘は生きた歴史に連ならないであろう」。以上は、他でもない水野正好の一九六九年の論文のあとがきの文章である。一体、これほどの皮肉と自己矛盾に満ちた言葉というものがどこにあるのであろうか。このあとがきは、何よりも水野自身にこそ真っ先に向けられなければなるまい。水野正好「縄文時代集落復原への基礎的操作」(前掲註92)
(264)前号で佐々木は与助尾根遺跡の東西に細長く伸びる二八軒の住居群の径を約一二〇mと記しているが、報告書所収の「与助尾根遺跡発掘竪穴住居址分布図」および「尖石、与助尾根両遺跡地形及び住居址分布図」などを参照するならば、東西の径は一五〇m前後とするのがもっとも妥当なものと考える(宮坂英弌『尖石』前掲註79)。これに対し、水野正好の集落分析作業を紹介した坪井清足の一九六二年の「与助尾根竪穴住居構成図」(坪井清足「縄文文化論」前掲註89)�、さらに本図をそのまま転用した水野の一九六九年の「与助尾根遺跡のうつりかわり」(水野正好『縄文時代集落復原への基礎的操作』前掲註92)は、一部の住居番号に加えて東西の径を二倍の約三〇〇mと誤って標示しており、しかもこれらの誤りに訂正が加えられた形跡は今日に至るまでまったく認められない。しかも、さらに注意したいのは、与助尾根遺跡のスケールの標示にみられるこのような初歩的な誤りは、単に水野一人の問題にとどまらず、一九七九年の『図説日本文化の歴史』から一九八三年の『長野県史』掲載の「尖石・与助尾根南・与助尾根遺跡地形・遺構分布」図(図17)、一九九四年の『考古学研究』の「教科書に登場する遺跡」�、『縄文時代研究事典』の同種の図に至るまで実に広い範囲に及び、揃って水野の与助尾根集落分析の誤りを助長していた事実である。他の遺跡ならいざ知らず�、「教科書に登場する」ほどの著名な遺跡の図面の誤りが、しかも特に正確性を求められる社会的影響力のある一連の著作を舞台に、何故、これほどの長期間にわたって放置されたままであるのか。註263における水野自身の言葉にもある通り、正しい集落分布図の呈示こそ正しい集落分析作業の基本であるとするならば、この問題の意味するところは大きく、とりわけそこに共通してみられる緊張感と相互批判の精神の欠如に対しては深い憂慮を示さざるをえない。
繰り返しになるが、一体、水野は、自らの集落分析作業にあたって、�「遺跡」からの様々な「問いかけ」(水野正好「なぜ縄文時代集落論は必要なのか」前掲註97)にどれほど真剣に応えようとしていたのであろうか。かれの分析姿勢に改めて根本的な疑問を投げかける象徴的な出来事であったといわなければならない。都出比呂志「ムラとムラとの交流」『図説日本文化の歴史』一 一九七九 長野県『長野県史 考古資料編』全一巻 (三) 一九八三 宮下健司「教科書に登場する遺跡 尖石遺跡�」『考古学研究』四一―一 一九九四 戸沢充則編『縄文時代研究事典』一九九四
(265)註244参照
(266)水野正好「縄文時代集落復原への基礎的操作」(前掲註92)
(267)水野正好「集落」(前掲註101)
(268)三上徹也「縄文時代居住システムの一様相―中部・関東地方の中期を中心として」(前掲註162)
(269)ここでいう方形柱穴列は、近年、東日本を中心に岐阜・三重両県を含めた各地域からその出土が報告されている特異な掘立柱建物遺構群を総称したものであり、正確にはそれは、埋葬儀礼にかかわる祭祀施設や食料倉庫としての“クラ”の可能性があるもの、さらに東北地方北部から北陸地方にかけて分布するいわゆる“長方形大型住居”と相通じる要素を有するものなど、「機能と系譜を異にするいくつかの遺構群の集合体」として存在していたことは以前にも指摘した通りである(佐々木藤雄「方形柱穴列と縄文時代の集落」『異貌』一一 一九八四)。規模・形態ともバラエティーに富むこれらの遺構群の中に竪穴式とは異なる住居が含まれていた可能性は十二分に考えられるところであり、石井寛や麻柄一志らは当該遺構と夏を中心とした季節的な住居との結びつきに注意を促している(石井寛「関東・中部地方の掘立柱建物跡」『研究会資料 阿久尻集落の方形柱穴列をめぐって』一九九一 麻柄一志「夏の家と冬の家―縄文時代の季節的住み替えの可能性」『考古学と生活文化』一九九二)。さらに、前期中葉の「長方形大型建物跡」多数が検出された栃木県宇都宮市根古谷台遺跡では、本例はいずれも長軸線を広場の中心部に向けるようにほぼ放射状に配列されており、同時存在数次第では、この種の大型例をこれまでのようにすべて公共的な、したがって非居住的な施設としてとらえることの妥当性に大きな問題を投げかけていたことが知られる。竪穴式の「長方形大型住居」による同様の配列例は前期中〜後葉の秋田県協和町上の山?U遺跡でも確認されている。竪穴住居例だけをもとに縄文時代の集落景観や規模・構成などを論じてきたこれまでの集落研究の危険性は明白であり、このことは水野正好らの住居群のみを対象とした群別作業についても直接あてはまる問題であったと考える。佐々木藤雄「和島集落論と考古学の新しい流れ―漂流する縄文時代集落論」(前掲註1)
(270)「そもそも『2軒の家族が常に1有機単位となっている』という基本単位や、『2棟3単位といった基本的な構成』という、縄文時代を貫いた単位や構成の固定した考え方に大きな問題がある。先の2棟の住居の住みわけ論を加味する時、結婚や出生はおろか、死ぬこともおいそれとできないことに気付く。・・・だが考えてもみよ。そんなばかばかしいことが常に普遍的に存在するのかと。・・・彼は本当に真剣に人間の歴史を研究し、考えているのだろうか・・・。」 ふれいく同人会「水野正好氏の縄文時代集落論批判」(前掲註216)
(271)レヴィ=ストロースは、たとえば双分組織について次のように書いている。「しかし我々は、むしろ、双分組織は機能的性格をもち、無数の人間集団の中に個々独立して存在しているにちがいない互酬性を基盤にしていると信じる。・・・双分制が互酬性を生みだしたのではない。つまり、双分制は、単に互酬性に形態を与えているにすぎないのだ。」「要するに、半族に共通する唯一の特徴は、数が二つであるということだけである。この二分性は場合に応じて非常に異なった役割を果たす傾向がある。時としてそれは、婚姻、経済的交換および儀礼を規制する。時にはこれらの活動のうちのあるものだけを、時にはただ運動競技だけを。かくして、様式によって区別できる多くの異なった体系が存在することになる。・・・双分組織はまずもって制度ではない。・・・これは何よりも非常に異なった、そしてとりわけ、多かれ少なかれ極端な応用形態をとりやすい組織原理なのである。」クロード・レヴィ=ストロース、馬淵東一・田島節夫訳『親族の基本構造(上)』一九七七
(272)この問題については以下の論文に詳しい。佐々木藤雄「縄文時代の通婚圏」『信濃』三三―九 一九八一 同「集落を通して縄文時代の社会性を探る」『考古学ジャーナル』二〇三 一九八二 同「与助尾根集落論の再価」(前掲註157) 同「縄文時代の親族構造」(前掲註213)
(273)幼児埋設土器(土器棺)の系統の違いを被葬者である幼児と深いかかわりをもつ母親の出自系統の反映とみる異系統埋甕論の登場以後、弥生あるいは古墳時代では、本論を直接援用する形で当該期の土器棺や木棺にみられる型式・系統上の違いを被葬者、もしくは被葬者の親と結びつけてとらえようとする見解が相次いで提出されている。これに比べると、肝心の縄文時代では、異系統埋甕論が抱える問題点を正面から論じた作業は何故か少なく、弥生・古墳時代例との際立った対照をみせている。しかし、使用された土器型式の意味をあいまいにした埋甕の単なる形態分類は無意味であり、まして佐々木が先に資料の集成・分析を試みた八ヶ岳西麓や諏訪湖盆、神奈川県域に限っただけでも当該資料の蓄積が圧倒的に進んでいる今日、特定の地域を対象とした異系統埋甕のあり方に対する総合的な検討作業はきわめて緊要な課題であったことは疑いない。都出比呂志「弥生土器における地域色の性格」『信濃』三五―四 一九八三 福永伸哉「弥生時代の木棺墓」『考古学研究』三二―一 一九八五 真壁葭子「考古学から見た女 性の仕事と文化」『日本の古代』一二 一九八七 春成秀爾「弥生時代の始まり」『UP考古学選書』一一 一九九〇
(274)茅野市教育委員会『よせの台遺跡』一九七八 同『棚畑』一九九〇
(275)会田進ほか『花上寺遺跡』岡谷市教育委員会 一九九六
(276)周知のように春成秀爾は、抜歯型式などの分析から妻方居住婚が優勢な時代から夫方居住婚が優勢な時代への移行そのものは認めつつ、中・後期の東日本はいわばその過渡期として自然生的な選択居住婚・双系制の段階にあったという考えを明らかにしている。なお、当該期の出自関係や婚姻にもとづく人口動態の復元を試みた意欲的な研究例としては、この他にも林謙作による被葬者の頭位方向の分析、渡辺新による貝塚出土人骨の歯冠咬合面の分析などが知られるが、しかし、家族あるいは親族関係そのものに対する縄文時代研究者の姿勢は全体的に第三者的であり、とりわけ近年は、厳密な概念規定や論理的な裏付けを欠いた皮相的・観念的な作業が目立つことは、これまでの議論が明らかにしていたところである。林謙作「縄文期の葬制?T・?U」『考古学雑誌』六二―四、六三―三 一九七七 春成秀爾「縄文社会論」『縄文文化の研究』八 一九八二 渡辺新「権現原貝塚の人骨集積から集落の人口構造を考える」『日本考古学協会一九九五年度大会研究発表要旨』一九九五
(277)小杉康は一九八一年と一九八三年の論文を中心に佐々木の親族組織論に言及し、「佐々木の縄文時代の親族関係についての結論」は「二つ以上の土器型式圏が接触する一定の地域に、一つのまとまりのある親族関係が組織される、と要約できる」とのべるとともに、そこには「通婚圏は同一の土器型式の分布圏内部が基本」であるとしてきた「佐々木自身の通婚圏に関する結論」との「論理的な自己(ママ)撞着を指摘できる」という批判を加えている。一体、佐々木は、いつ、どこで、このような一面的・一方的な「縄文時代の親族関係についての結論」を提出したというのであろうか。 小杉はこの「結論」の根拠を、佐々木の一九八一年の論文の「縄文時代の親族関係が、土器の系譜を異にする複数の集団を包含しつつ、共通の土器型式に示される社会的な紐帯をあえて突き破る形において組織されていた可能性を示唆していたことが指摘されるのである」という八〇頁の記述に求めている。しかし、小杉は、佐々木がその記述のすぐ後に「このことは、もちろんどの地域、どの集落についても等しく指摘できるものではない」という言葉を続けている事実については何故かまったく触れようとさえしていない。本人も預かり知らないような「結論」に対する、一人芝居としかいいようのない見当外れな「批判」は迷惑以外の何物でもない。
すなわち、小杉のためにも改めて問題点をまとめるならば、?@縄文時代の通婚―親族関係はあくまでも同一土器分布圏内の一定の地域を基本として成立していた可能性が高いこと、?Aただし、この問題は個々の集落を取り巻く歴史的・自然的条件などにより一律にはとらえきれない要素を含んでおり、土器分布圏の外縁部などでは隣接する他の分布圏をも包摂した通婚―親族関係成立の可能性についても十二分な考慮が払われる必要があること、?Bこうした遠近の集落を包摂した地域内・地域間という通婚―親族関係の重層的な構造は、限られた集落規模の下で婚姻関係のいうならば安定性と供給の確実性を保証しようとする現実的な要請とも明確に対応するものであり、それは、外婚制そのものが本来的に抱えている集団諸関係の調整機能ともあわせて、共通の通婚圏内にある各集落、各小地域相互の各種の社会的な結びつきを否応なしに拡大・強化する役割を果たすこと、?Cそうであれば、共通の土器分布圏内のそれとも異なる以上の結びつきが土器型式自体のその後の変化や土器分布圏の拡大・縮小といった現象にどのような影響を与えることになったのかどうかはきわめて注目されるところといえるが、いずれにしてもその考古学的な解明は今後の緊要な課題であること、以上が一九八一年の論文その他(註271参照)における佐々木の一貫した主張であり、あたかも?Aの後半部分のみが佐々木の「結論」であるかのような「要約」は、小杉の事実誤認、もしくは基本的な理解力不足にもとづく「異訳」�・「誤訳」の類でしかない。先の羽生淳子に対する批判(註180参照)にも書いた通り、誤った批判・独善的な批判の一方的な垂れ流しこそは縄文時代集落論の創造的な発展を阻害するもっとも大きな要因といえるものである。小杉による速やかな佐々木「批判」の撤回と何よりも徹底した自己批判とを強く望むところである。小杉康「縄文時代に階級社会は存在したのか」『考古学研究』三七―四 一九九一
(278)水野正好「縄文時代集落復原への基礎的操作」(前掲註92)
(279)本稿では触れられなかったが、縄文時代における集団の動態や領域、土器型式の動きと土器分布圏および文化圏のあり方などについては、今日、集落論第四世代による多様なアプローチも盛んに試みられており、現在のテーマとの関連からもその行方が注目される。小林謙一「縄文時代中期勝坂式・阿玉台式土器成立期におけるセツルメント・システムの分析―地域文化成立過程の考古学的研究(2)」『神奈川考古』二四 一九八八 桜井準也「土器型式の流れの数量的分析―南関東地方への曽利系土器の流入をめぐって」『信濃』四三―四 一九九一 谷口康浩「縄文時代集落の領域」『季刊考古学』四四 一九九三
(280)水野正好「縄文社会の構造とその理念」『歴史公論』九四 一九八三
(281)G・P・マードック、内藤莞爾訳『社会構造』一九七八
(282)宮下健司「教科書に登場する遺跡 尖石遺跡」 (前掲註264)
(283)水野正好「なぜ縄文時代集落論は必要なのか」(前掲註97)
(284)長崎元広「縄文集落研究の系譜と展望」(前掲註32)
(285)都出比呂志『日本農耕社会の成立過程』一九八九
(286)坪井清足「縄文文化論」(前掲註89)
(287)近藤義郎「弥生文化論」(前掲註65)
(288)戸沢充則「海戸遺跡における集落(住居址群)の構成」(前掲註190)
(289)戸沢充則「海戸遺跡」『長野県史 考古資料編』(前掲註264)
(290)註68参照
(291)市原寿文・近藤義郎ほか「討論」(前掲註67)
(292)近藤義郎「共同体と単位集団」(前掲註58)
(293)和島誠一・金井塚良一「集落と共同体」(前掲註47)
(294)近藤義郎「先土器時代の集団構成」『考古学研究』二二―四 一九七六
(295)都出比呂志「農業共同体と首長権」(前掲註130) 菅原正明「縄文時代の集落」(前掲註196) 後藤直「農耕社会の成立」『岩波講座日本考古学』六 一九八六 なお、縄文時代集落論第二世代に視点を戻せば、「単位集団」という記述そのものは一九八六年の小林達雄の論文の中にも数多く認めることができる。しかし、小林の場合、この言葉はかれのいう「縄文モデル村」との関連において独自に用いられていたとみるのが妥当であり、同じく第二世代に属する戸沢充則の、近藤義郎の歴史的な提起をふまえた「単位集団」概念の使用(戸沢充則「海戸遺跡における集落(住居址群)の構成」前掲註190)とは明確に区分されなければならない。小林達雄「原始集落」(前掲註217)
(296)原秀三郎「日本における科学的原始・古代史研究 の成立と展開」(前掲註40)
(297)甲元眞之「農耕集落」(前掲註55)
(298)都出比呂志「農業共同体と首長権」(前掲註130)
(299)岩崎卓也「ムラと共同体」(前掲註43)
(300)註51�・52・54参照
(301)甲元眞之は特に「単位集団」の普遍性を強調して次のようにのべている。「弥生時代の集落は、大形住居一軒を中核として、三―五軒の中・小形住居で構成される単位が基本であり、大集落といえどもこうした単位集団が量的に拡大したにすぎないことが指摘できるのである」(甲元眞之「農耕集落」前掲註55)。このような、「はじめに単位集団ありき」的な一方的な議論がかえって単位集団論が本来的に有する可能性を損なう危険性については、佐々木の以下の論文に詳しい。佐々木藤雄「新井三丁目遺跡における弥生後期集落とその問題点」『新井三丁目遺跡』一九八八 同「山王三丁目遺跡と弥生後期の環濠集落」『山王三丁目遺跡』一九九一
(302)近藤義郎・渋谷泰彦『津山弥生時代住居址群の研究―西地区』(前掲註63)
(303)近藤義郎「第四章 縄文時代の生産と呪術」『日本考古学研究序説』一九八五
(304)都出比呂志『日本農耕社会の成立過程』一九八九
(305)都出比呂志ほか「トイレの考古学」『文芸春秋』七二―八 一九九四
(306)都出比呂志「農耕社会の形成」『講座日本歴史』一 一九八四
(307)水野正好�「縄文社会の構造とその理念�」(前掲註280)(308)近藤義郎『前方後円墳の時代』(前掲註69)
(309)近藤義郎『前方後円墳の時代』(前掲註69)
(310)都出比呂志「農業共同体と首長権」(前掲註130)
(311)もし、佐々木の批判が誤りであるというのであれば、都出比呂志は「数棟を基礎とする一単位」の具体的な実例とその分析結果をはっきりと例示した上で佐々木に対する反論を試みるべきであろう。
(312)小杉康「縄文時代に階級社会は存在したのか」 (前掲註278) なお、本論文の中で小杉は、「多くの批判を受けながらも」水野正好の『縄文時代集落復原への基礎的操作』が「評価されるべき第一点は、複数の住居址から構成される集落址の具体的な分解方法―以後に受け継がれるスタンダード―を提供したことである」とのべている。林謙作のいう「ブラック・ボックス」(註176参照)との類似性が注目される発言であるが、他の研究者に対する場合とは異なり、小杉は水野論にかかわる「多くの批判」の内容については、一切、沈黙を守っている。また、水野の業績として取り上げている論文も何故か前出の『縄文時代集落復原への基礎的操作』の一つにとどまっており、与えることになった評価の高さの割には、水野集落論を体系的・総合的にとらえていく視点がまったくみられないことはきわめて不可解というほかはない。
(313)ところで、本論文における小杉康は、縄文時代を中心とする社会組織解明へのアプローチを「親族組織論」�、�「共同体論」、�「階層=階級論」の三つに細分し、「親族組織論」を「仮設集団内または集団間の関係を、婚姻関係の復元を中心として把握する研究方向」、�「共同体論」を�「レヴェルを異にする複数の仮設集団の関係を、空間的かつ構成的に把握する研究方向」、�「階層=階級論」を�「仮設集団内部の関係を階層・階級という垂直方向の区分原理で把握する研究方向」としてそれぞれ定義づけるとともに、実際の場面においては「親族組織論」は�「共同体論」とも�「階層=階級論」とも接点をもつことなく、一定の距離を保った関係にあるといった趣旨の指摘を行っている。
しかし、そもそも家族や婚姻、性の問題などとは無縁な部分で成立しうる�「共同体論」とは、一体、どのようなものであろうか。本源的な意味 いにおける共同体論とは、いうまでもなく“個”と“共同性”とが出会う所に不断にその成立をみるものとしてある。小杉の分類は、その本来の意図はともあれ、本質論的な視点を欠落した現象的・外面的な細分作業に終わっており、三者の関係を含めた以上の内容には明確な異議をさしはさまざるをえない。仮に、ここでの小杉が“共同体”をあくまでも限定的な、狭義の意味合いにおいてとらえているというのであれば、逆に小杉の�「共同体論」や「親族組織論」の定義や実体はきわめて不十分かつあいまいであり、そこに「婚姻関係の復元」という字句が挿入されない限り、両者を厳密に区分する境界線は、実は無いに等しいといっても誤りではない。また、肝心の縄文時代をめぐる「階層=階級論」に対する小杉の考究は、小林達雄や渡辺仁らの作業(小林達雄「日本文化の基層」『日本文化の源流』一九八八 渡辺仁 『縄文式階層化社会』一九九〇)に言及した部分を除けば、まったくの尻切れとんぼに終わっている。水野正好と都出比呂志の二人の�「共同体論」に対する学史的評価の危うさともあわせて、羽生淳子とともに集落論第四世代を代表する小杉の理論的検証作業は、縄文時代集落論の未来にかえって大きな問題点を突きつけていたといわなければならない。註277・312参照
(314)両者を視覚的に区別するものがあるとすれば、まさしくそれは、水野正好のいう、集落を区画する多様な「溝」の有無であろう。水野正好「縄文社会の構造とその理念」(前掲註280)
(315)都出比呂志の“ネオ単位集団論”の抱える問題点については、いずれ稿を改めて詳しく言及したいと考えている。なお、本稿では触れることができなかったが、都出の『日本農耕社会の成立過程』に対しては、これまでにも以下の諸氏による批評が提出されており、都出のもっとも基本的な主張である世帯共同体・世帯群存在の普遍性、およびそれらを導く都出の分析の基準や方法などを中心に多くの疑問や批判が寄せられていることを付け加えておきたい。新納泉「書評 都出比呂志『日本農耕社会の成立過程』�」 吉田晶「都出比呂志著『日本農耕社会の成立過程』�」『新しい歴史学のために』一九六 一九八九 犬木努「書評 都出比呂志著『日本農耕社会の成立過程』�」『史学雑誌』九九―二 一九九〇 河村好光「弥生ムラ・古墳づくり・律令国家―共同体と個別家族�」『考古学研究』三七―四 一九九一 田中禎昭 「古代村落史研究の方法的課題」『歴史評論』五三八 一九九五
(316)佐々木藤雄『原始共同体論序説』一九七三 同 「縄文社会ノート」『異貌』五、七、八 一九七六・七八・七九 これに対し、後藤直は縄文時代における共同労働の比重を一方的に強調したドグマ丸出しの見解を先に披露し、「世帯共同体の労働における自立は未熟であった。いいかえれば、住居のまとまりとしてあらわれる世帯共同体の個別性・相対的独自性は顕在化せず、血縁関係によってそれらを統合し、性別分業に成員を組織する居住集団の中に包摂されていたのである」とのべている(後藤直「農耕社会の成立」前掲註295)。しかし、縄文社会の実際の動きは後藤の予測よりも遥かにダイナミックであり、集落内、集落間、そして地域相互の間で“固有の内的矛盾”の深化を背景においた経済的社会的な不均等性をあらわにしつつあったことはこれまでにも佐々木が指摘を繰り返してきた通りである。後藤論は縄文社会の歴史的自己運動に対する視点を欠如した独善的な推断にすぎず、縄文時代集落論が築き上げてきた成果に対する認識不足も甚だしいといわざるをえない。
(317)佐々木藤雄「縄文時代の家族構成とその性格―姥山遺跡B9号住居址内遺棄人骨資料の再評価を中心として」(前掲註160) 厳密には縄文前期以降について現在は想定している。
(318)拡大家族と並んで当該期に複婚家族が存在した蓋然性についても同様に相応の考慮が払われるべきであろうが、しかし、その場合でもそれは、拡大家族同様、あくまでも従的な位置にとどまっていたと考える。註165参照
(319)縄文中期集落研究グループ『シンポジウム 縄文中期集落研究の新地平』一九九五
(320)註180参照
(321)誤解を恐れずにいえば、水野集落論をめぐる呪縛の構造と三内丸山をめぐる一連の“ためにする議論”の根は同質であり、前者を批判しえない者に後者の批判を行うことはできない。三四年前の藤森栄一の言葉を借りるならば、その意識の奧にはびこっているものは、考古学の行方に立ちふさがっている、眼にみえない、しかも、もう一つの「高い壁」(藤森栄一「日本石器時代研究の諸問題」『考古学研究』九―三 一九六二)にほかならない。佐々木藤雄『侵蝕される縄文時代集落論―水野集落論とネオ単位集団論』土曜考古学研究会一二月例会研究発表要旨 一九九五