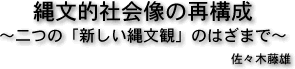
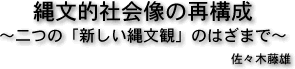
I 西尾幹二の『国民の歴史』
二十世紀も余すところ一年わずかとなった昨年十月末、産経新聞社より『国民の歴史』と題する大部の書が上梓された(1)。著者はドイツ文学者で電気通信大学教授の西尾幹二。「南京大虐殺の虚構性」を批判し、「従軍慰安婦は商行為であった」と主張する東京大学教授藤岡信勝や『新・ゴーマニズム宣言』の漫画家小林よしのりが理事および理事待遇をつとめる「新しい歴史教科書をつくる会」の代表者である。
一九九六年十二月に発足をみた「新しい歴史教科書をつくる会」が編集に参加する本書『国民の歴史』は、西尾が東洋と西洋のいずれの文明にも属さない「一つの文明圏」とみる日本列島の歴史を“大東亜戦争”敗北後の日本を広く覆う自虐的な歴史観の否定とあわせて跡付けようと試みたものであり、その中味も、「日本語確立への苦闘」、「 魏志倭人伝は歴史資料に値しない」、「王権の根拠−日本の天皇と中国の皇帝」、「「世界史」はモンゴル帝国から始まった」、「秀吉はなぜ朝鮮に出兵したのか」、「鎖国は本当にあったのか」、「アメリカが先に日本を仮想敵国にした」、「日本が敗れたのは「戦後の戦争」である」等々、従来の通史一般にはみられない独自の主張と視点で貫かれている。
こうした主張や視点は縄文時代に関連した記述の中にも色濃く投影されており、「一文明圏としての日本列島」や「世界最古の縄文土器文明」などでは、縄文時代以来の伝統的な家屋としての高床式構造、一万六千五百年前にもさかのぼる世界最古の縄文土器、一定規模の栽培農業や神殿、天文学的知識、家畜の飼育を伴った長期無変動文明の存在、稲作文化の担い手としての縄文人、などがユーラシア大陸と対峙する日本列島の独自な特殊性を一層際立たせる事例として列挙されている。
もちろん、竪穴式住居の普遍的な分布に知られるように、中国文明と日本文明の異質性を示す根拠の一つとして土間式構造を主体とする中国の家屋と高床式構造を主体とする縄文時代以来の日本の家屋とを対置させる考えは、富山県桜町遺跡出土の高床式建物例などの意義を一方的に拡大した西尾の明らかな作為、ないしは誤り以外の何物でもない。エジプト文明と並ぶ長期無変動文明論も、青森県三内丸山遺跡の発見を端緒とした安田喜憲の幻の縄文文明論(2)の単なる受け売りに過ぎず、縄文文明論の虚構性と論理的・実証的な破産については佐々木が前稿で批判を加えている通りである(3)。
西尾はまた、「縄文火焔土器、運慶、葛飾北斎」の中で白鳳から天平、鎌倉に至る日本の仏像彫刻を「世界美術史上、類例のない到達度に達した彫刻群」として位置づけるとともに、これらの仏像彫刻、とりわけ怒りで髪の毛を逆立てている忿怒像の激しい情念のほとばしりの中に「四千年前にさかのぼる火焔土器」の姿を連想し、「縄文文化が四千年の時を経て天平の仏教文化のただ中に、ふたたび姿を表したといえないだろうか」とのべている。この種の歴史学以前の思いつき的な発言や感想の是非については議論するまでもないが、ともあれ、西尾のこうした過剰ともいえる数々の縄文賛美論の陰に、縄文時代をめぐる「輝かしい考古学的成果」と、それに伴う縄文と弥生との相対的な比重の変化という、日本考古学を取り巻く近年の事情が存在していたであろうことは容易に想像される。
しかし、本書の全体を通してもっとも注目されるのは、縄文から弥生への歴史的な転換、すなわち弥生式水稲農耕社会の成立を「弥生革命」、あるいは「古代化」への第一歩として明治維新にも匹敵する日本史上の一大変革期とみなしてきた日本考古学の“常識”(4)が真っ向から否定され、それにかわって「縄文から弥生にかけての変化は新生活への転換ではなくて移行であり、歴史の断絶ではなくて連続であった」という大胆な見解が提起されていたことである。その根拠として西尾が取り上げるのが、前述した一定規模の栽培農業を伴う長期無変動文明の存在や、近年の弥生時代研究者の提起を下敷きとした稲作文化の担い手としての縄文人という考え(5)であり、そこから西尾は「大いなる“母なる母胎”」、「日本史のたんなる前史なのではなく、いわば基盤をなす土台」という独特の縄文文化観を披瀝している(図1)。縄文時代を旧石器時代と並んで列島史の単なる前座的な位置にとどめ、当該期に直接かかわる記述としてはわずかに“社会人類学者”小山修三の『狩猟採集時代の生活と心性』をみるだけであった一九九三年の『岩波講座日本通史』(6)に比べれば、思わず拍手を送りたくなるような縄文文化の取り扱いであるが、しかし、西尾が次のようにつづけるとき、われわれのそのような他愛のない思いは一瞬にして瓦解を余儀なくされる。
西尾は書いている。「われわれは自国の過去をどこまでさかのぼらせることができるかという一件について、第二次大戦後ひどく臆病になり、すべては王権がつくった作為であり、ナショナリスティックな自覚は恥ずかしいことであり、それに先立つ氏姓社会は原始的で未開だと決めつけ、「倭」の国がまるで土侯国のように、古代中国大陸の王朝に臣従していた野蛮人であるかのごとき歴史を描くことに、慣れてきてしまっている。」「私は、今、何世紀までさかのぼって神武東征があったか否かを論ずるつもりはないし、それがここでの課題ではない。しかし七、八世紀の国号と天皇号が定まったあの国家形成の自覚史の時代よりも、はるか先立つ時代にこの民族の歴史があったことだけは、まず間違いない。しかも、その後の今日に至るまでの天皇譜の継続の意思を見るなら、そこからさかのぼって歴史を振り返り、考察し、判断することも、歴史解釈のための決め手となる重要な要素なのではないだろうか。誤解を恐れずにいえば、仮に天皇号が天武・持統朝の木簡で証明されたときを、謝りのない確実なスタートとすることにして、(たとえば推古朝の説を仮に退けるとしても)、それからでさえ千三百年を経過していて今日なお継続している王朝の系譜は、先立つ時代の国民的な継続の意思を表現していたと解釈することに、なんのためらいがあるであろう。」
西尾はこうも書いている。「歴史をたんに目先の記録や目録の類だけで、科学的に立証できるか否かだけに限定して議論する視野の狭さを言いたいのである。はっきり自覚された七、八世紀の初期国家形成の頂点から遠い過去へさかのぼって、そのエネルギーと上昇への意思を確かめるためには、片々たる記録だけに頼るべきではない。その日から千三百年も展開してきた、この国の今日までの歴史が示したひとつの意思もまた、証拠として採用されてしかるべきではないだろうか。」「地域によってかなり凹凸があるが、どこでも食料採集段階→農耕社会の段階→王権の成立の順序で歴史が進んでいくさまが見てとれる。これを見ると、日本の場合だけが特異であって、食料採集段階が非常に長くつづき、農耕社会の段階が短くて、すぐに王権の成立を見る。」「日本だけがなぜこれほどに特別な例外をなしているのであろうか。縄文時代と弥生時代の二つを、これまでのようにあまりにはっきりと食料採集の段階と農耕社会の段階とに区別してしまったことが、実情に合わないからであろう。縄文時代は二つの段階が微妙に折り重なっている。・・・たしかに、稲作文化と呼べるような経験は弥生にまで待たなければならないが、それも水田稲作が長く必要とされなかっただけの話で、縄文時代が未開の原始社会だったという意味にはならない。ほどなく王権の成立期を迎えるに足るだけの、文明的な成熟状態にすでに到達していたということを意味するのではないだろうか。」
そもそも、わが列島には今日に至る王権・王朝の継続を希求する「国民的な意思」が連綿として地下水のように流れており、しかもその強固な国民的意思、広義の民族的意思は、実は弥生時代はおろか、それに先立つ縄文時代の少なくとも後半段階にまでさかのぼって確実に存在していた。この、歴史的な一つの事象から「この国の今日までの歴史が示したひとつの意思」なるものを強引に導き出し、その淵源を遥か数千年の昔にさかのぼって辿りうるとする西尾の、霊能者も顔負けのあまりにも壮大無比な“ご託宣”(7)の前に、日々、片々たる考古資料の分析に追われ、土器型式をめぐる瑣末な議論に他愛のない一喜一憂を繰り返す凡百の考古学研究者は、自らの拠るべき基盤を崩され、呆然と立ち尽くすしかないのである。
世界史に占める日本列島および民族史の一体性・継続性を高らかに謳い、返す刀で弥生式水稲農耕社会の形成をめぐる朝鮮半島や大陸の影響をことさら過小評価しようとする西尾の主張の背後に見え隠れするのは、一言でいえば、より近代的な外皮を纏ったやわらかな皇国史観、ネオ皇国史観であり、その誕生に青森県三内丸山遺跡の発掘を契機とした縄文文明論のきわめてヒステリックともいえる大合唱が大きく貢献している事実に、われわれは強い危惧と疑念とを抱かざるをえないのである(8)。
II やわらかな皇国史観
考古学的な遺構・遺物に「最古」あるいは「最大」といった冠詞が付与されるとき、それがしばしば村起こしや町起こしといった次元を飛び越えたところで国家意識や民族意識の高揚へと結びつけられてきたことはこれまでの歴史が教えるところである。しかし、西尾論の斬新さは、近年の考古学的成果をふまえた形で進められつつある縄文文化の見直しの動きを、皇紀二千六百年、たかだか弥生文化成立前夜という限られた舞台の上でしか生を享受できなかった王権の起源をめぐる“肇国史観”、“肇国の考古学”(9)の見直しへと巧みに結び付けていたことであり、またこの点にこそ、天孫降臨神話や神武東征神話を軸とした旧来の硬直的な皇国史観の止揚と裾野の拡大とを模索する、西尾のやわらかな皇国史観、ネオ皇国史観の大きな所以があったということができる。
そして、ここでさらに注意したいのが、西尾によるこのようなネオ皇国史観と一体のものとなった新しい日本史区分法の提起である。すなわち、古代・中世・近世・近代という形で一般化されてきた従来の時代区分は日本独自の歴史観念に由来するものでは決してない。それは古代・中世・近代というヨーロッパ流の三区分法を日本史に強引にあてはめ、どことなくこれと一致しない江戸時代のみを近世として別扱いした、きわめて変則的な区分法でしかない、というのが西尾の基本的な主張であり、以上の立場から日本に固有の歴史のリズムを重視した独自の二区分法を次のように提起している。
「いったい日本に中世はあるのだろうか。あるいは世界のどこでも使われていない、近世などというきわめて特殊な時代区分法を用いて江戸時代を説明することは、はたして適切であろうか。あえて日本の歴史を室町末で区切ってそこまでを古代とし、そのあとを近代とするという、二つだけしかなかったと考えることになにほどか不明な点があるであろうか。」「考古学者によると、この列島内で環濠や掘割がつくられ、大規模な防衛設備が施され、内乱が熾烈をきわめた時期は、古代国家が建設された直前と、南北朝から戦国時代へかけての動乱の時期と、この二度だけであったといわれる。してみると、日本史は縄文弥生の一万年以上を第一期とし、大和朝廷の確立から鎌倉室町までを第二期とし、これを古代と称し、戦国の動乱の後の統一政権以降を近代と名づけるのがむしろふさわしいのではなかろうか。」
日本史の時代区分としてもっとも一般的に用いられているのは古代の前に原始を置き、これに農耕社会成立以前の旧石器時代と縄文時代とをあてはめる方法であり、先の『岩波講座日本通史』も基本的にこのスタイルを踏襲している。これに対し、西尾によれば、原始時代という言葉は字義通り歴史以前の未開野蛮の深い闇に沈んだ段階を指すものであり、近年の新しい考古学的な知見の蓄積の結果、大陸とはまったく異質な日本文明進展の根幹を形成していたことが明らかとなった縄文時代とは根本的に相容れないという説明が与えられる。
西尾が自らの歴史観にもとづいて縄文と弥生を第一期とし、また、日本史全体を大きく古代と近代に二分すること自体にさしたる意味はない。しかし、原始時代を未開で野蛮な歴史以前の概念であったとする西尾の理解は、まぎれもなくかれが批判するヨーロッパ流の、しかも前世紀的な発想のそれであり、西尾が自らの時代区分の大きな根拠とするエジプト文明に並ぶ長期無変動文明の存在も考古学的にはまったくの幻想の産物でしかなかったことは前章でも指摘した通りである。むしろ、日本史の時期区分を列島の歴史のリズムや特殊性の尊重に立って進めるという西尾の考えに従うならば、縄文時代、さらには縄文から弥生に至る歴史は西尾が予想するより遥かに複雑かつ地域的にも多様であり、三内丸山遺跡や桜町遺跡などの発見を契機とした縄文文化観の見直しの動きが、実は西尾論の中核にある「縄文人」や「縄文文化」の歴史的・民族的一体性という基本的な枠組の再検討をも促しつつあったという近年の日本考古学をめぐるもう一つの事情を、西尾ははたしてどのように受けとめるのであろうか。
戦後、日本人は王権成立以前の氏姓社会については「すべて未開で原始的で闇だといって消去し、見えないこととしてしまう見方」を取りつづけてきた。西尾は先の説明につづけて、かれが従来の時代区分法を排し、かわって縄文・弥生を一体とした古代の再評価を促す今日的な理由を以上のようにのべている。
しかし、そもそも静岡県登呂遺跡から三内丸山遺跡へと至る戦後の考古学研究、古代史研究の軌跡こそは、戦前・戦中、タブーとされ闇の中に消去されてきた列島の原始・古代史像の掘り起こしの歩みではなかったのか。原始社会が未開で野蛮で深い闇の底に沈んでいるという見方は、実は王権の淵源を辿ることが困難な「古代」以前の社会に対する西尾自身の差別的な見方、評価そのものではなかったのか。日本史の実態に即した古代・近代という二区分法を提起する西尾の論理はここでもひたすら作為的であり、何よりも縄文・弥生を第一期として一括して古代に編入する考えの背後に、列島史を王権の発展段階そのもの、まさしく王朝史として再編しようとする意図が垣間みえることに対しては、改めて大きな驚きと息苦しい思いとを禁じえないのである(10)。
III 泉拓良『新たな縄文観の創造に向けて』の陥穽
ところで、西尾の『臣民の歴史』ならぬ『国民の歴史』が刊行された昨年秋、これと前後するように『季刊考古学』第六九号において「縄文時代の東西南北」と題する特集号がまとめられた。この特集号は、副題にもあるように「縄文文化の本質と多様性」を列島各地の研究者の広汎な分析視点から追求しようとしたものであり、取り上げられているテーマも集落の構造から墓制、生業、植生、土器型式の受容と変容をめぐるメカニズムに至るまで幅広い構成をみせている。本稿ではこれらの詳細に立ち入る余裕はないが、以上の論文中、西尾の独自の時代区分との関連という意味ではもちろん、縄文観の根本的な転換という今日的な命題との関連においても大きな問題を投げかけていたのが、『新たな縄文観の創造に向けて』と題された、本特集号の編集者でもある泉拓良の論文である(11)。
泉の論文が注目される理由は、かれが縄文時代の年代観と縄文観そのものの二つの変更をこの中で明確に企図していた点に求められる。泉によれば、現在至極当然のように使われている草創期・早期・前期・中期・後期・晩期という縄文時代の六期区分は等時期区分という当初の原理からは逸脱しており、C14年代測定法などにもとづく現状の年代観とも合致しない。六期区分の提唱者である山内清男の基本的な考え方(12)を尊重し、できるだけ等時間的な時期設定を試みるのであれば、縄文時代約一万一〇〇〇年を三分割するのが妥当であるというのが泉の基本的な主張であり、その上でかれは、従来の草創期(約一万三〇〇〇〜一万年前)を?T期、早期(約一万〜六三〇〇年前)を?U期、前期以降(約六三〇〇〜二五〇〇年前)を?V期とする試案を提出し、各時期の歴史的意味の検討を通した縄文観の変更、新しい縄文観の創造を試みている(図2)。縄文文明論に立つ西尾と、縄文文明論の一定の効用(13)を認めつつ、当該期を基本的に狩猟採集社会とみる泉との間には大きな隔たりがあるが、この時代の基本的な歴史像を根本から見直す作業が考古学の内と外から相次いで提出をみたという事実は、偶然の一致とはいえ、きわめて興味深いものがあったといえるだろう。
しかし、泉の呈示する年代観と縄文観の内容そのものについていえば、西尾論とはまた別の意味での危惧と疑念とを拭うことができない。
泉は、先に示した?T・?U・?Vの各期についてそれぞれ模索期・実験期・安定期という名称を与え、土器や竪穴住居、縄文的石器の出現など準備段階的な様相を中心とする模索期、定着的な集落の出現や本格的な漁業の開始、石皿の爆発的な増加などを特徴としつつ、全体としてゆるやかな発展段階にあった実験期、定住的集落や安定した墓地、多彩な祭祀的遺物を中心に典型的縄文文化の繁栄した成熟期であると同時に、後半には狩猟採集経済の限界が明らかになる安定期、というように各期の内容を説明している。
泉が目指しているのは年代学上の単位としての機械的・相対的な時期区分なのか、それとも歴史的評価を含んだ本質的な段階区分なのか。かれの作業で先ず気にかかるのは、この点に対する区別をあいまいにした発言が少なくないことである。しかも、山内の基本的な考えに従い、できるだけ等時間的な時期設定を試みたとしながら、泉の設定する各時期の時間幅が最大一〇〇〇年、最小五〇〇年の差をもっていることも不可解な点であり、何よりも三〇〇〇〜四〇〇〇年という時間幅は年代学上の物差しの単位としてはいかにも粗いといわざるをえない。むしろそれぞれの出発点や方法において、「可及的同数位」の土器型式を単位に編年の体系的な整理を試みた山内の時期区分とC14年代から設定された時間幅を単純に三分割する泉の時期区分との間にはすでに看過しがたい差異が存在していたのであり、そうした両者を単純に対応させようとすること自体に大きな無理・矛盾があったことは明らかであろう。
加えてこうした泉の年代観を一層不可解なものとしているのが、かれが呈示する「新しい縄文観」と呼ばれるものの中味である。
泉は先の三期区分案の指摘につづけて、従来の縄文観に大きな変更を促すことになった近年の顕著な考古学的成果を次のように説明している。「つい最近まで、縄文文化は狩猟採集の文化であり、そのような文化は「遊動生活を送り、人口は希薄で、階級や階層の分化は認められず、分業も性差によるものを除くと(このような性差があるかについても、欧米では問題になっている)、ほとんど認められない」とされてきた。最近の報道で問題にされてきたのは、この点である。縄文文化は定住・貯蔵の文化であり、人口は予想以上に多く、階級はともかく階層が存在し、個々人や集落間の分業もかえって発達していて、交易も日用品に関しては、弥生時代よりも盛んであったことが解ってきたからであろう。」
一体、泉は、この三〇年間というもの、日本考古学の何を学んできたというのであろうか。
泉は、縄文時代研究者を「古い縄文観」に縛りつけてきた大きな原因として十九世紀以降脈々と受け継がれてきた社会進化論的な歴史観、狩猟採集民に対する農耕・文明民の偏見、中心としての中国に対する周辺意識、などの存在をあげ、それにかわる「新しい縄文観」登場の契機を同じく次のように説明している。すなわち、「以上のようなステレオタイプな考え方の中で、縄文研究が進行してきたわけであるが、このような考えは、人類学者や民俗(民族の誤りか―佐々木註)学者から突き崩されることになった。西田正規であり、渡辺仁の研究であった。海外での狩猟採集文化の見直しは、ポランニーやサーリンズやテスタールに代表される。まずは狩猟採集経済活動の評価であった。狩猟採集民がけっして現代人にも劣らない豊かさを保持していることを提示した。彼らの研究はさらに、狩猟採集社会には、移動型の社会と定住型の社会があり、定住型の社会にはその契機となった貯蔵のシステムがあり、これが社会的不平等、階層化をも生み出すとした。」
縄文社会を氏族共同体的な社会として性格づけ、 環状あるいは馬蹄形の集落配置の出現をもとに当該期における定型的・定着的な集落の問題を論じることになった和島誠一の学史的な論文、「原始古代集落論の原型」(14)ともいわれる『原始聚落の構成』(15)が提出されたのは、泉が誕生したのと同じ一九四八年であり、三内丸山遺跡の発見を端緒とした縄文都市論が大流行する以前の一九八〇年代後半から九〇年代前半には、定型的・定着的集落論の見直しを迫る“小規模集落論”や“横切りの集落論”からの激しい「批判」にさらされたことはよく知られている(16)。
縄文時代における階層分化や奴隷の問題についても小林達雄は八〇年代後半より独自の主張を繰り返しており(17)、渡辺仁の『縄文式階層化社会』(18)とあわせて小杉康の『縄文時代に階級社会は存在したのか』の「批判」の的となったことは記憶に新しい(19)。
佐々木自身についてみても、縄文時代の貯蔵穴(ヂグラ)の総合的な分析から食料の長期的・安定的な確保とその供給を保証する大量の貯蔵植物の存在が、同時に縄文集落の定着化と定型化、集落規模の拡大と分布の増大、それに経済的・社会的な不均等性の進展と構造的に一体のものとして顕現していた可能性をはじめて指摘し、縄文社会を原始的な平等性がつねに支配した社会とみる“常識”に大きな疑問符を突きつけることになったのは一九七三年の最初の論文、『原始共同体論序説』(20)であり、この中で、新しい考古学と呼ばれるテスタールの貯蔵経済論の基本的な主張の多くが、かれの『狩猟―採集民における食料貯蔵の意義』(21)に先行する形で呈示をみていたことは改めてのべるまでもない(22)。
ほぼ殯説一色に染められていた方形柱穴列、縄文時代の特異な掘立柱建物遺構が「機能と系譜を異にするいくつかの遺構群の集合体」であることを明らかにし、その中に埋葬儀礼や長方形大型住居などに関連する施設に加えて食料倉庫としての“クラ”、まさに富山県桜町遺跡例に示されるような高床式を含めた“クラ”が存在した可能性を佐々木が指摘したのも一六年前の一九八四年のこと(23)であり、当時の「古い縄文観」とは相容れないこれらの新しい提起に対しては、縄文時代の不均等な発展や住居を単位とした個別管理型貯蔵穴の存在を否定する堀越正行(24)や、クラとヂグラという形態・構造を異にする貯蔵施設の縄文時代における複合的な展開に懐疑的な今村啓爾(25)などからの、今からみてもきわめて的外れとしかいいようのない「批判」が相次いだことも学史が示す通りである。
さらに泉は、今回の特集の目的を「従来一系統と言われていた縄文文化が、いくつもの系統に別れていることと、一面的なモデル村や、モデル的生業では語りきれないことを、地域と言う場を借りて、表現しようと試みたものである」とのべている。多様な系統性の認識に立った縄文文化の根本的な見直しについても岡本孝之(26)や大塚達朗(27)らの精力的な問題提起があったことは周知の事実であり、この問題に言及した岡本の『東日本先史時代末期の評価』が『月刊考古学ジャーナル』誌上を賑わしたのは一九七四年、今から二六年も前のことである。 泉が「新しい縄文観」として列挙する事例の多くは、もっとも古い例では最初の提起からすでに半世紀以上を経過しており、その意味では少しも「新しい縄文観」といえるものではない。それらを「新しい縄文観」と強弁するのは泉の認識不足、勉強不足も甚だしく、ましてステレオタイプ云々とは、これらの先駆的な問題提起や作業に対する冒涜以外の何物でもない。しかも「縄文時代の東西南北」といいながら、引用されているのは東日本の既成の成果がほとんどであり、「縄文文化の平板には語り得ない複雑な内容」が泉の本来のフィールドである西日本をも含めた広い視点から少しも語られていないことにもわれわれは大きな戸惑いと失望を感じざるをえないのである。
にもかかわらず、こうした一種の作意、あるいはアナクロニズム丸出しのお粗末な発言が『季刊考古学』という、日本考古学にとってはメジャーな商業誌を通して広く喧伝され、それが新しいものの見方としてまかり通るのであれば、近年の縄文文明論・縄文都市論を引き合いに出すまでもなく、日本考古学はフィクション、それもたちの悪いフィクションにほかならず、その拠って立つ土壌は西尾の『国民の歴史』とまったく変わらないといわざるをえないだろう。
結局のところ、泉が高らかに掲げる「新たな縄文観の創造」、あるいは「縄文文化の本質と多様性」とは、一体何であったのか。二、三十周遅れのランナーが、いつの間にか先頭とすりかわっている。思わずそんな奇妙な光景さえ思い浮かぶ以上の滑稽な議論のあり方の中に、ともあれ、プライオリティーの尊重に立った活発な論争と相互批判の徹底という歴史科学の基本原則を繰り返し踏みにじり、既成の枠組にとらわれない豊饒でしなやかな発想に支えられた論理・方法・歴史像の主体的な創造をつねに怠ってきた日本考古学の否定的な現状の一面、つまりは学問的なレベルの低さと緊張感の欠如が、見事にうきぼりにされていたことだけは確かであろう。
IV 縄文時代の三つの歴史的区分
谷口康浩は『揺らぐ「縄文文化」の枠組』と題した昨年暮れの論文の中で、近年蓄積されつつある考古学的な新知見が縄文文化の根幹を揺るがしている現状を自らが調査した青森県大平山元?T遺跡の問題をまじえて概観している(28)。本論文における谷口の視点は縄文時代の年代的上限と年代的下限、縄文文化の地理的範囲、縄文時代の段階区分の各領域にまたがっており、大平山元?Tの長者久保石器群に伴う無文土器の一万六五二〇年cal B.P.という暦年較正値と縄文文化の起源、縄文時代の初期農耕と本格的な稲作農業との関連、東西日本の地域性とさらには縄文文化の北限と南限、山内清男の土器型式の編年にもとづく便宜的・年代学的な時期区分と縄文文化の歴史的な段階区分などについて問題点の摘出と今後の展望が試みられている。
いずれも先の西尾論や泉論と基本的に複合するテーマであり、それらが一九九九年の秋から冬にかけて集中的に提出されていることは改めて興味深いが、特に谷口は縄文時代の歴史的評価を含んだ本質的な段階区分をめぐるこれまでの学史を整理し、この問題にかかわることになった従来の作業を大きく次の三つに分類している。
その一つは、弥生式水稲農耕社会の成立から最初の統一国家形成までの期間の短さに比べて実に十倍以上もの長さをもつ縄文時代の歴史の中に「ゆるやかな発展と克服できない限界」を認める見解である。縄文時代を成立段階(草創期および早期)、発展段階(前期からおおむね中期にかけて)、成熟段階(中期末ないし後期から晩期の前半まで)、終末段階(おおよそ晩期の後半)の四段階に区分する岡本勇(29)がその代表であり、縄文時代を生成・発展・消滅の三段階に区分する後藤和民(30)もこれに含まれる。完新世の温暖な気候条件の下、縄文時代の生産力はゆるやかな発展をみせ、一定の成熟を果たすが、自然の再生産を上回る生産力の行使が不可能な採集経済そのものの限界・矛盾は克服されず、やがて社会の停滞を必然化するのであり、この採集経済の矛盾は弥生農耕の成立によってはじめて克服される、というのが岡本が説明する「ゆるやかな発展」論の概要である。
第二の歴史観は、これとは対照的に「着実な発展段階」という評価を核心とする見解である。着実な発展段階を経て経済的・文化的蓄積がなされた結果、後の農耕の受容と発展がはじめて可能になったという佐々木高明らの見方であり、佐々木は縄文前期に原初的な農耕、さらに西日本の後・晩期には雑穀・根茎作物型の焼畑農耕が行われていた可能性を指摘する一方、この間の変化は基本的に量的なものであり、縄文時代には質的な変化はみられなかったと説明する(31)。
第三は、縄文時代の歴史の方向性を来るべき農耕社会に向かっているとは考えない点で、前二者と激しく対立する歴史観、いわば「発展史観」に対する「異文化史観」である。縄文と弥生の問題を列島における東西二系列の異質な文化系統の対立と相克の歴史としてとらえ直そうとする先の岡本孝之の見方(32)はその代表的なものである。さらに小林達雄は、多種多様な食料資源の利用を基盤とし、特定少数の栽培種の食料資源に依拠する農耕経済への傾斜を拒みつづけた縄文時代の生産力はすでに早期には高い水準に達して安定しており、弥生農耕の開始までその基本性格に大きな変質はなかったこと、したがって縄文から弥生への変化については、単なる経済的変革という一面から評価するのではなく、異質な文化論理との接触による縄文的価値観・世界観の終焉として理解すべきこと、などを促している(33)。
岡本勇の「ゆるやかな発展」論に代表される第一の見方は学史的にもよく知られた歴史観であるが、それぞれの用語法や三期区分・四期区分といった違いにかかわらず、そこに共通して認められる当該期の時期別人口変動模式図にも似た生成−発展−没落型のピラミッド状の発展図式は縄文時代の実際の歴史をあまりにも単純化し過ぎており、特にその多様性や高度性を示唆する近年の新たな考古学的知見との齟齬は大きい。成立期から発展期、成熟期への上昇を可能とした生産力の着実な発展を保証する要因として岡本が「単位集団の増大による共同労働の発展」のみをクローズアップするのも一面的であり、階級以前の社会ではつねに「人間と自然とのあいだの矛盾」が主要な矛盾であったという見方とあわせて、人間と社会との間の矛盾を縄文時代の発展段階に即して正当に評価していこうとする、まさしく人間社会史的な動的な視点に大きく欠如していたことは後述する通りである。 谷口がまとめた縄文文化の歴史的区分をめぐる三つの見方のうち、前章で取り上げた西尾や泉の歴史観との関連で注目されるのは第二と第三の見方である。とりわけ注意されるのが第二の佐々木高明のそれであり、稲作以前の農耕の存在を主張しつつ、縄文文化を日本文化の基層に位置づけ、その発展段階の一つに組み込もうとする点は西尾論との際立った共通性を示している。さらに佐々木が呈示する三期区分、草創期を旧石器時代から縄文時代への「移行期」あるいは縄文文化の「胎動期」、早期を縄文文化の「形成期」、前期以降を縄文文化の「成熟期」と位置づける考えも、何故か泉の?T・?U・?Vの各期との著しい年代的な対応性をみせていたことに驚かされる。「模索期」・「実験期」・「安定期」という言葉こそ違え、泉の時期区分案は佐々木の区分案そのものといっても誤りではなく、この点でもわれわれは泉の独自性・主体性といったものに改めて大きな疑問符を付けざるをえないだろう。
これに対し、西尾の歴史観とは根本的に相容れないのが岡本孝之や小林達雄の「異文化史観」であり、特に一系列の日本文化という既成概念を近・現代をも含めた広い視野から激しく批判する岡本の主張は西尾のそれとの鋭い対立をみせている。また小林も、近年とみにその可能性が指摘される縄文農耕を自然との共生という「縄文姿勢方針」にのっとった多種多様な資源利用の一環とみなし、自然を積極的かつ人工的に変更することによって効率を高めようとする弥生時代の農耕経済とは、その世界観においても反対の極に立つものであったと断じている。さらに岡本と小林の二人が、東西二つの地域性の評価という点では微妙なニュアンスの違いをみせつつ、ともに縄文から弥生への転換にあたっての朝鮮半島からの外部的影響を重視し、縄文と弥生との対立や戦闘といった事態をも想定している点は重要であり、西尾論との視点の違いを際立たせている。
もちろん、弥生文化は少数の渡来者と多数の在来者との融合の下に比較的平和裡に形成されたという考え、新しいパラダイム(34)が、近年、西日本の弥生研究者を中心に熟成されつつあることは確かに西尾も指摘する通りであり、そもそも「完成された「弥生文化」が当初から存在したかのような考え」は採るべきではないという意見も日本考古学の内部にはある(35)。
しかし、「大変革の主体」としての縄文人を「稲作文化の担い手」としての縄文人に置き換え、弥生前期終末に至ってもなお残る「コロニー」の問題には触れないまま、弥生文化の成立とその性格をめぐる議論をあたかも紀元前三世紀前後の在来者と渡来者の構成比率の問題に単純化できるかのような『国民の歴史』における西尾の主張はきわめて一面的かつ恣意的であり、列島史の根幹にかかわるすぐれて質的な問題を量的な問題へと矮小化している。縄文から弥生への移行を二者択一的な論理で裁断し、あるいは弥生時代の西日本をごく当然のように同一時代・社会概念の中に組み込んできたこれまでの“常識”の妥当性については、新しいパラダイムを模索する研究者も率直に疑問の目を向けるところであり、まして在来の「縄文人」や「縄文文化」の歴史的・民族的な一体性・一系統性(36)の考古学的な証明は、さらに遠い課題としてかれらの前に残されていたのである(図3)。「北海道早期の石刃鏃文化や九州前期の轟式・曽畑式土器などにみられるように、日本列島の枠を越え、サハリンや朝鮮海峡を通過した文化的交流が活発に行われた場合があることを、多くの舶来文物が証明している。そのため、東北アジア全体との関連性を視野に入れて日本列島における先史文化を理解するためには、縄文文化という既成の枠組そのものを解消すべきだという意見さえある」。谷口は縄文文化の範囲に関する現在的な問題点を「縄文時代における日本列島内部の多様な地域差が明確になるにつれて、縄文文化がはたして一枚岩だったのかどうかという根本的な疑問も生じてきた」と要約した上で、以上のようにのべている。まさしく「縄文文化の本質と多様性」に対する本源的な問いをあいまいにした、今日の多分に政治的な「国内的」視点・枠組に合わせた「縄文文化」と「弥生文化」の対比、前者から後者への移行論の限界・矛盾は明らかであり、それは、西尾がかれのやわらかな皇国史観、ネオ皇国史観の基軸に据える長期無変動文明論の幻想性、王朝に遥かに先立つ時代の民族的な「継続の意思」の虚構性をも、さらに鮮明に写し出していたのである。
V 結―縄文式階層化社会への多様な道
第III章でものべたように、かつて佐々木は 一九七三年の『原始共同体論序説』において縄文時代の貯蔵穴(ヂグラ)の分析を試み、当該期には共同管理型屋外貯蔵穴とあわせて個別管理型の屋内・屋外貯蔵穴が確実に存在すること、これら三者の時空的な分布には東西日本の間で大きな差異・不均等があり、西日本では全時期を通して個別管理型の貯蔵穴が未発達であること、個別管理型貯蔵穴が発達する東日本でも当該貯蔵穴と住居との対応関係は集落を構成するすべての住居群には認められず、いわば不整合なあり方を広く示していたこと、などを明らかにするとともに、これら各タイプの貯蔵穴が多様な展開の姿をみせる東日本のあり方を縦軸に縄文時代の三つの画期を設定したことがある。すなわち、当時の貯蔵穴資料の上限期であり共同管理型貯蔵穴を伴う集落と個別管理型貯蔵穴を伴う集落の両者が登場する第一の画期(前期中葉期)、前二者に加えて同一集落で共同管理型と個別管理型の併存現象が認められるようになる第二の画期(中期中葉〜後半期)、そして弥生式水稲農耕社会への過渡期としての第三の画期(晩期終末期)、の都合三つの画期である(37)。
この、貯蔵穴資料が不明瞭であった前期以前を含めれば縄文時代を大きく四区分する作業は、貯蔵穴からうかがわれる労働生産物の分配・占有主体のあり方というすぐれて経済・社会的な視点から縄文時代の歴史的・質的な段階区分を模索したものであり、原始的な平等性を基盤とする縄文社会をその内側から突き破ろうとするこの時代の“固有の内的矛盾”を共同労働にもとづく共同所有と個別的労働の成果の個別的占有との矛盾として明確に位置づけ、各画期を個別的生産諸力=分業の発展を基盤とした内的矛盾の深化、いいかえれば家族単位的な個別的労働の前進に対応した労働生産物の個別的な占有と共同所有との間の矛盾の深化の過程としてとらえようとした点でも学史的にも重要な意義をもっていたと考える。 また、個別管理型貯蔵穴の偏在現象にみられるように、当該期における個別的労働の進展が同時にその成果に対する個別的占有の不均等な展開としてあらわれていた可能性については、以上のあり方を共同規制の網に覆われた強固な統一体である縄文集落内部での家族の個別化・自立化の顕現と、それらを契機とした経済的・社会的な不均等性の醸成としてとらえかえし、縄文時代における家族や集落の動勢を集落内からさらに集落間、地域内、地域間という各種のレベルの不均等性との重層的な関連において跡づけようとした点に、同様の意義が存在していたということができる。
したがってこうした、縄文時代の特殊かつ普遍的な問題を当該社会の歴史的な自己運動に即して論理的かつ具体的に明らかにしていこうとする佐々木の動的な視点に対しては、「人間と自然とのあいだの矛盾」(38)を絶対的なものととらえ、この時代を「生産と消費がつねに等質な社会」(39)と結論づける、当時の縄文社会論の主流ともいうべき研究者からの教条主義的な「批判」や「無視」が繰り返されたことは先にも触れた通りである。また、縄文社会の側の内部的な矛盾や質的な変化の評価という点では、前章で取り上げた岡本孝之や小林達雄らの第三の見方とも相容れない部分を含むが、新しい縄文観をめぐる議論そのものが示していたように、その後の考古資料のあり方は、佐々木のこの時の視点と見通しの正しさを裏付ける方向に基本的に推移しつつあったことはすでに明らかである(39)。
もちろん、こうした意義とは別に、前述の画期論の蓋然性そのものが問われるとすれば、貯蔵穴の分布が草創期はおろか旧石器時代にさかのぼる可能性をみせ、さらにヂグラに高床式のクラをあわせた貯蔵施設の複合的な展開が確実視される現在、貯蔵穴資料を核とした三つの画期論の限界性は明らかである。また、歴史的な段階区分としても、三つの画期論が生成―発展―没落というピラミッド型の発展図式の限界性の中になおとどまっていたことは否めず、加えて当該期の社会関係との関連についての吟味も不十分であったことなどを考慮するならば、この時の考えは、縄文社会をめぐる新たな知見をふまえた基本的な再検討を迫られていたことは確かであろう。
以上の諸点をふまえた上で、本稿では、縄文時代、とりわけ東日本を中心とする当該期を、生成・発展・変質・爛熟の四つの段階に区分する考えを新たに提起したい。それぞれの概要は次の通りである。
《生成期》草創期 早期段階にほぼ該当する。草創期を縄文時代から外し、旧石器時代に含めようとする根強い意見(40)があるが、旧石器から縄文への「移行期」としての側面をも含めて、ここでは草創期と早期を一括して生成期に位置づける。先にものべた通り、ヂグラの分布はすでにこの段階から確認することができる。
《発展期》前期、とりわけその中葉から中期後半段階に該当する。前述した第一の画期と第二の画期を含む。定型的・定着的集落の発展とあわせて、ヂグラにクラを加えた貯蔵施設の複合的な展開がみられる段階である。中部・関東地方を中心に集落の構成単位である家族の個別化・自立化が顕著となる一方、集落内・集落間・地域間の不均等性もその影を大きくする。
《変質期》中期終末から後期後半段階にほぼ該当する。前段階にみられた個別化・自立化および各種の不均等性に質的な変化が認められる段階であり、それとあわせて、家族、集落、地域をめぐる従来の関係や構造にも前代までとは異なる動きが顕在化するようになる。林謙作も当該段階を変質期と位置づけ、この時期にみられる大規模モニュメントの登場を、その建設のために消費することを計算に入れた貯蔵、累積されない剰余の登場と結び付けるすぐれた視点を呈示している(41)が、変質期の内容・性格の基本的な評価という点で、林と佐々木との間には大きな差がある(42)。
《爛熟期》後期後半から晩期段階にほぼ該当する。縄文文化の解体が着実に進行する時期でもあるが、「爛熟」という言葉が示す通り、この段階は、見る側の角度によって決して一つの枠組にはおさまらない、多様な貌をうかびあがらせる。 以上の詳細についてはいずれ稿を改めてのべることにするが、今回、呈示を試みることになった四期区分案の大きな目的はといえば、家族の個別化・自立化のうねりと一体となったこの時代の不均等化の質とその行方を、縄文時代における階層関係形成をめぐる議論との区別と関連において歴史的・論理的に見極めていこうとする点に求められる。
一体、原始共同体の“固有の内的矛盾”の深化とも相俟って縄文時代の中葉、すなわち発展期段階にはすでに明瞭な形をとるまでに成長するこの時代の経済的・社会的な不均等性と、いわゆる階層差との間を隔てるものとは何か。かかる階層差とは、当該期をめぐる経済的・社会的な不均等性のどのような延長線上に顕現するのか。そもそも当該期における階層化への歩みは、東西日本をはじめとする各種の地域的な不均等性の進展にもかかわらず、基本的に列島のどの地域でも、ほぼ同じようなプロセス、同じような方向性を辿るものとしてあらわれるのか。そして何よりも、列島における初期階層化社会の歴史的な性格、特質とは、はたして何であるのか。
すなわち、これまでに概観した縄文社会の不均等な発展のあり方が強く暗示していたのは、縄文式階層化社会に至るまさしく多様な道の存在であり、その具体的な検証と、それにもとづく縄文的社会像再構成に向けての基礎的な作業として、ここに本稿を提出するものである。
註
(1)西尾幹二『国民の歴史』新しい歴史教科書をつくる会 一九九九
(2)安田喜憲「縄文文明の発見―まとめにかえて」梅原猛・安田喜憲編『縄文文明の発見』一九九五ほか なお、西尾の『国民の歴史』が安田の縄文文明論に高い評価を与えていること自体、すでに歴史書としては十分にいかがわしいということができるが、西尾は安田の長期無変動文明論を「エジプト文明に並ぶ長期無変動文明」という見出しで長々と引用した後、「私は縄文文明が世界の有力文明のひとつであるか否かということ自体に、自分なりの論点をもちだせる資格をもたない」という断り書きを、大新聞の訂正記事よろしく、ほんの申し訳程度に付け足している。読者にさんざん誤った縄文観を植え付けながら、それに対する批判には西尾はどのような「弁明」も許されている、というわけである。歴史小説やエッセイの類ならともかく、「新しい歴史教科書」のモデルとなる『国民の歴史』の記述としては、あまりにも客観性と主体性に欠けたアンフェアな姿勢といわざるをえない。西尾自身が指摘するように、「複数の反対証言に耐えないものは史料とはいえない」のである。いちいち取り上げることはしないが、この他にも西尾の『国民の歴史』には、この種の作為や思いつき、神がかり的発言、恣意的な引用、さらにはそれらを総動員した各種の論理のすり替えが全編にわたって登場する。後述するように日本の仏像彫刻を賛美してやまない西尾が、その最大の危機でもあった明治政府の神道国教政策にもとづく廃仏毀釈の愚かな歴史にはっきりと触れないのは、ご都合主義の最たる例といえるだろう。
(3)佐々木藤雄「北の文明・南の文明―虚構の中の縄文時代集落論」『異貌』一六、一七 一九九八、九九
(4)春成秀爾『弥生時代の始まり』UP考古学選書一一一九九〇 佐原真「王墓にみる世界と日本」『週間朝日百科 日本の歴史』四三 一九八七
(5)金関恕・大阪府立弥生文化博物館『弥生文化の成立―大変革の主体は「縄紋人」だった』角川選書 一 九九五 ただし、『弥生文化の成立―大変革の主体は「縄紋人」だった』というタイトルにも明らかなように、西尾の引用はここでもきわめて恣意的であり、自説に合わせた「加工」を多くの部分で施している。註2参照
(6)小山修三「狩猟採集時代の生活と心性」『岩波講座日本通史』二 一九九三
(7)西尾は別のところで書いている。「縄文の祭りには祝祭と祭儀の二つがあった。祝祭ははでやかなお祭りで、祭儀は粛然たる儀式であったらしい。今の日本各地の神社で行われる祝祭と祭儀に似たものが想像されている。」一体、どうすれば、このような“想像”が可能なのであろうか。註2参照
(8)後でも触れるが、泉拓良は新しい縄文観を論じた最近の論文の中で次のようにのべている。「縄文文化イコール縄文土器、華麗で芸術的であり、世界最古の一つである縄文土器という構図から脱し始めたのは、いわゆるマスコミからだった。・・・もちろん、『縄文文明論』のように、マスコミにだけしか登場しない、的を得たとは言えないものもあるが、議論を喚起するには十分な役割を果たしただろう。」しかし、すでに明らかなように虚構の縄文文明論は、一部の野心的な研究者や大新聞、行政それぞれの「思惑」、さらには世間知らずの考古学者の予測を遥かに超えたスピードと次元で日本の「正史」、日本の「定説」への道を一気に駆け登りつつある事実を、泉ははたしてどのように総括するのであろうか。あまりにも現実感覚の欠如した、能天気な発言といわざるをえない。泉拓良「新たな縄文観の創造に向けて」『季刊考古学』六九 一九九九
(9)“肇国の考古学”をめぐる問題点については次の論文に詳しい。柳澤清一「杉原荘介と“登呂”肇国の考古学」『土曜考古』一五 一九九〇 岡本孝之「杉原荘介と山内清男の相克―または弥生文化と大森(縄文)文化との関係について」『神奈川考古』二七 一九九一 佐々木藤雄「水野集落論と弥生時代集落論―侵蝕される縄文時代集落論」『異貌』一四、一五 一九九四、一九九六ほか
(10)「天皇制国家のもとでは、考古学・考古学研究者に制約や弾圧がつきものである。昔もいまも、程度の差はあっても事情は変わらない。しかし、考古学・考古学研究者を被害者の立場だけでとらえることはできない。くわしく説明する余裕はないが、江上波夫の騎馬民族説のように、日本の歴史を天皇族の歴史にすり替えるマヤカシは、昔も今も(残念ながら将来も)跡を断たない。われわれ自身が、どこまで天皇制のなかででき上がった通念や俗説から自由であるか、その点がもっとも問題である。」林謙作「縄紋時代史22 縄文人の集落(2)」『季刊考古学』四八 一九九四
(11)泉拓良「新たな縄文観の創造に向けて」(前掲註8)(12)山内清男「縄紋土器型式の細別と大別」『先史考古学』一−一 一九三七 同「縄文式土器・総論」『日本原始美術1』一九六四ほか
(13)註8参照
(14)長崎元廣「縄文集落研究の系譜と展望」『駿台史学』五〇 一九八〇
(15)和島誠一「原始聚落の構成」『日本歴史学講座』一九四八
(16)土井義夫「縄文時代集落論の原則的問題―集落遺跡の二つのあり方をめぐって」『東京考古』三 一九 八五 黒尾和久「縄文時代中期の居住形態」『歴史評論』四五四 一九八八 羽生淳子「縄文時代の集落研究と狩猟・採集民研究との接点」『物質文化』五三 一九九〇ほか
(17)小林達雄「日本文化の基層」『日本文化の源流』一九八八 同『縄文人の世界』朝日選書 一九九六
(18)渡辺仁『縄文式階層化社会』一九九〇
(19)小杉康「縄文時代に階級社会は存在したのか」『考古学研究』三七―四 一九九一
(20)佐々木藤雄『原始共同体論序説』一九七三 以上の問題については次の論文でも詳しく触れている。佐々木藤雄「原始共同体論の陥穽」『異貌』一 一九七四 同「縄文社会論ノート」『異貌』五、七、八 一九七六、七八、七九
(21)アレン・テスタール、親澤憲訳「狩猟―採集民における食料貯蔵の意義」『現代思想』一八―一二 一九九〇
(22)この問題については次の論文に詳しい。佐々木藤雄「和島集落論と考古学の新しい流れ―漂流する縄文時代集落論」『異貌』一三 一九九三
(23)佐々木藤雄「方形柱穴列と縄文時代の集落」『異貌』一一 一九八四
(24)堀越正行「小竪穴考」『史館』五、六 一九七五、七六
(25)今村啓爾「群集貯蔵穴と打製石斧」『考古学と民族誌』一九八九
(26)岡本孝之「東日本先史時代末期の評価」『月刊考古学ジャーナル』九七、九八、九九、一〇一、一〇二 一九七四 同「桃と栗―中部・関東弥生文化における弥生文化と大森(縄文)文化の要素」『異貌』一三 一九九三 同「考古科学としての考古学」『異貌』一四 一九九四ほか
(27)大塚達朗ほか「文化の東西対決 縄文時代から」『福島民報』一九九八年一月一日付朝刊ほか
(28)谷口康浩「揺らぐ「縄文文化」の枠組−縄文文化の範囲と段階区分」『白い国の詩』一九九九
(29)岡本勇「原始社会の生産と呪術」『岩波講座日本歴史1 原始および古代1』一九七五ほか
(30)後藤和民「縄文時代における生産力の発展過程」『考古学研究』二九―二 一九八二
(31)佐々木高明『日本の歴史?@ 日本史誕生』集英社 一九九一ほか
(32)岡本孝之「東日本先史時代末期の評価」 同「桃と栗―中部・関東弥生文化における弥生文化と大森(縄文)文化の要素」 同「考古科学としての考古学」(前掲註26)ほか
(33)小林達雄『縄文人の世界』(前掲註17) 同『縄文人の文化力』一九九九ほか
(34)金関恕・大阪府立弥生文化博物館『弥生文化の成立―大変革の主体は「縄紋人」だった』(前掲註5)
(35)石川日出志「岡本孝之氏の弥生時代観を排す」『西相模考古』四 一九九五
(36)西尾自身は歴史の連続性や文化の同一性と人種的・民族的同一性とは異なるという発言を行っているが、両者の区分は実際にはきわめてあいまいである。註1参照
(37)佐々木藤雄『原始共同体論序説』(前掲註20)
(38)岡本勇「原始社会の生産と呪術」(前掲註29)
(39)「縄文時代をとおして、個々の住居はいうにおよばず、集落の規模の大小などにかかわらず、生産と消 費がつねに等質な社会が貫徹されたのである」という勅使河原彰の言葉にみられるように、この種の、歴史のダイナミズムとは無縁なドグマ丸出しの縄文社会観は今なお一部の研究者に引き継がれ、マルクス主義歴史理論の誤った枠組の宣伝に「貢献」しつづけていることは、佐々木がこれまでにも批判を繰り返している通りである。勅使河原彰「縄文時代集落をめぐる問題」『歴史評論』四六六 一九八九 同『縄文時代』新日本新書 一九九八ほか
(40)勅使河原彰『縄文時代』(前掲註39)ほか
(41)林謙作「考古学研究会第四三回総会研究報告 縄紋社会の資源利用・土地利用―「縄文都市論」批判」『考古学研究』四四―三 一九九七
(42)林謙作「階層とは何だろう」『展望考古学』考古学研究会 一九九五
本論文は「異貌」18 共同体研究 2000年5月1日に掲載されたものです。今回、著者の佐々木藤雄さんからの資料提供により、皆様にご紹介できることとなりました。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。
なお、原典は縦書きのため、年号等が漢数字のままになっていますが、ご了承下さい。また、図・表は都合により省略しました。