「澤田教一、寺山修司の思い出」 青森高校4回生 藤巻健二
私たち昭和29年卒業の4期生の中では、澤田教一と寺山修司が一際目立っている。なにせ、二人とも世界を舞台に活躍して大きな業績をあげた。同期生にとっては自慢の種なのである。
才子薄命というが、残念ながら澤田は34歳、寺山は47歳という若さで、とうの昔に鬼籍に入ってしまった。
私たちの高校時代と言っても、もう50年近く前のこと、いわば遙はるか雲煙の彼方である。あのころの二人のこと、その後の二人のことを思い出してみたい。
澤田教一のこと
彼も私と同じ写真部だった。彼は入部したころ、アルバイトで買ったというオリンパスシックスを持
っていた。笑うことも少なく、悪く言えば表情の乏しいむさいタイプであった。ニキビ面の顔が大きいことから「アタマデカ」と呼ばれていた。赤ら顔のニキビを指でつぶしたりしていた。
そんな彼ではあるが、着ているワイシャツは常にアイロンを掛けてお洒落であった。二人で修学旅行のスナップ写真を撮って金儲けをしようとしたことがあったが、思惑外れでたいして売れず、小遣いにもならなかった。
写真部の暗室は旧五連隊の建物の中にあったが、先輩たちはよくここで隠れてタバコをすっていた。
先生が来て、「何してる、開けろ!」と言われて、「今現像中で開けられません」。慌てて窓を開けて印画紙の袋で煙を扇ぎ出したり、先生に追いかけられて堤川の土手を逃げたりしたものだった。澤田も私も在学中はもちろんその後もタバコを吸わなかったのは、あのころの先輩たちの騒ぎを見ていたせいかもしれない。
彼と私が並んで写っている写真が手元にある。文化祭の写真部の展示の前のスナップである。私は笑顔なのに、カメラを肩にした澤田はいつもの通りむっつり顔である。
ピュリッツァー賞「安全への逃避」受賞後のある日、日本に戻っていた彼から電話があって、ホテル青森で会った。友人5、6人が集まった。そのころは私も新聞カメラマンをしていた。「ずいぶん良い写真撮ったなあ」と私が言うと、彼は「ナーニ……水を泳いでいるところを撮っただけダネ……」と、はにかみながら答えたのを今でもよく覚えている。
お喋しゃべりの私は、「良い写真を撮るには『突撃』のときには前に出ないといけないんだろうなあ」と言うと、彼は、「そうだ、何としてでも人の前に出ないといけないが、自分には神様がついているから大丈夫」と言いながら、ヘリコプターの中で笑っている写真をくれた。
彼はシルバーのライカを持ってきていた。私は「白いカメラだと目立つし、ピカピカ光って撃たれるぞー」と言って、無理やり私の持っていた黒のニコンFと交換してもらった。このときが彼に会った最後だった。
それから間もないころの夕方、プノンペンからジープで取材に出かけた道中で、彼は撃たれて死んだ。茶目っ気のないむっつりした澤田教一らしい死に方だったように思う。
寺山修司のこと
寺山修司は、ニックネームというわけではないが「テラシュー」と呼ばれていた。似た名前だった野球部の寺山俊司は「テラシュン」、寺山と俳句仲間の松村圭造は「マツケー」だったから、あのころはそういう呼び方が流行っていたのだろうか。
寺山は野球と相撲が好きだった。負けるのが嫌いだった。休み時間など、よく相手を見つけてピッチングをしていたし、相撲やるべ、と挑んでいた。彼の本業は文学部だが、新聞部にも入っていて、季節を写した私の写真に俳句を添えてくれた。ともかく旺盛過ぎるくらいの好奇心の持ち主だったしエネルギッシュな行動派だった。青白い顔をした文学青年というタイプからはほど遠かった。
頭の良さは抜群だった。試験のとき困っている級友たちに自分の答案用紙をまわしてくれたこともしばしばあったと聞いている。心優しい男だった。試験のときに彼に助けられた学友もけっこう多いと思う。
寺山が映画「書を捨てよ町へ出よう」を持って、講演のため青森に来たことがある。前日に建設会館に50~60人の同期生が集まって歓迎会を開いた。学校時代と変わらない猫背で下駄を履いて現れた。先生方も来たし、けっこう盛り上がった。翌日の催しには何人かの同期生が見に行った。寺山の死後、天井桟敷の劇団員だった人が、追悼集に、このときのことについて、寺山が「同級生ほど当てにならないものはない。弁護士とか医者とかテレビ局でエラくなっているやつとか集まって酒飲んで『ガンバレー、ガンバレー、テ・ラ・ヤ・マ、明日はみんなで見に行くからな』なんて言ったのに、ほら見ろよ、誰も来ちゃいない」と言っていたと書いている。
実際には誰も行かなかったというわけではないのだが、彼はもっとたくさんの人が来てくれると期待していたに違いない。学校仲間からも敬遠されていると感じて悔しく思ったのだろう。
あのころは演劇や映画を中心とする「寺山芸術」は前衛的過ぎて田舎に住む同期生たちには素直に受け入れられるものではなかった。
没後20年、彼の人気は若い人たちを中心に衰えるどころか益々高まっているし、これからも多くの人から愛され続けることだろう。寺山はやはり心優しい男だったのだ。あの催しのときに来た同級生が少なかったことが苦い思い出として彼の心に長く残ったかもしれないと思うと、今でも気持ちが重くなるのである。(「青森高校100年史」平成15年)
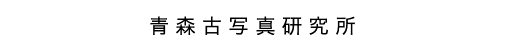
 ホーム
ホーム ニュース
ニュース 古写真集
古写真集